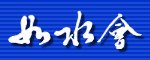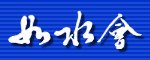入社後最初の赴任地福島で始めた坐禅の修行時代に、励まし合い共に汗を流した在家の道友が一人いた。上京後続いていた音信が途絶え、人伝てに不治の病に罹ったことを知ったが、見舞いにいくチヤンスを都度逸していた。
ある夜彼の夢をみた。凛然と歩く後姿に、「布施さん元気になったんだね」と思わず呼びかけると、振り向いてにっこりと笑いかけてくれた。そこで目が覚めたがまだ払暁、しかし何とも胸が苦しくそれ以上寝ていられない。起き上がって坐禅を始めた。
二十分も経ったろうか。電話が鳴り、取ると福島の老師からで、「先ほど布施さんが亡くなられました」と仰しゃる。えっとしばし絶句のあと夢のことを申し上げ、「あんなに元気だったのに」と呟くと、「そうだね。元気になったんだね」と静かに言われた。禅者らしいからっとした死に際を、老師も肯われたに違いない。
その老師も、もうこの世には居ない。
玉木老師に初相見したのは福島の禅寺においてであった。
赴任した工場の独身寮で一年間同居した男は、日本の精神文化の探求に余念のない日々を送っていた。結婚で寮をでた私をその男がある日ひょっこり訪ねてきて「坐禅をやらないか」という。正直即答はできなかった。というのも抹香臭いことの大嫌いな性分で、凡そ寺などには縁のないそれまでの人生であったからである。ところがその時は何故であったろうか、しばしの考慮のあと一度寺へ同行することに同意したのである。
当日特別の感懐もなく老師の前に座った私は、やがて始まった説教に不遜なことに居眠りを始めた。しかしその話のなかでひとつだけ、「自分の前の佛を拝むのではないぞ」と言われた時にはびっくりした。
一通りの説教が終わって、「では実地に坐ってみましょう」ということになり、足の組み方、手の置きどころ、姿勢の保ち方を教わり、最後に「数になりきって数えなさい」と言われた。
言われるがままに数を数えて十分ほどたった頃、「今日はここまでにしましょう」と言われて我に返った。驚いたことに頭がスッキリと澄み渡っている。その時の「おや、これは何かあるぞ」という印象が、その後の修行に私を駆り立てたといえる。
暇があれば寺に通うという段階から、やがて強く勧められて夏の接心に参加するところまできた。接心とは寺に泊り込みの5泊5日の猛修行で、熱が加わってくると殆ど不眠不休となる。容赦なく肩に打ち下ろされる警策は、やがて皮膚を破り血は単衣を汚す。現在の私の肩には、未だにその時の旧創が斑となって残っている。何を目指すのか。言うまでも無く見性である。見性とは、外に見ていた仏が実は自分自身だったと気付く最初の悟りであり、この一関を突破しない限り何事も始まらないからである。
四日目の朝あたりから、孵卵間近の卵の殻の内をコツコツと雛の嘴がつつくように、自分の内部で何らかの変化が起こりつつあった。その日の夜坐で「ムーーーー」と、地軸を裏側まで貫く息を透したその刹那、身心を宇宙の果てまで鋭く突き抜ける大きな感覚に襲われ、思わず「判ったぞー」と叫んでいた。
見性を許されてからは、公案拈提に寸暇を惜しまない毎日となった。公案とは、悟りを深め大悟徹底に導くための禅の問題であり、千七百と言われるほどの膨大な数がある。師匠から一則一則の綿密な点検が行われ、ひとつを透過しなければ次へは進めない。
師匠の室内に朝夕必ず入り、公案の見解を呈し、透ったかどうかの点検を受ける一対一の真剣勝負(独参という)に全力を集中し、結果に一喜一憂したのも懐かしい思い出である。坐りこめば容易に透り、頭ででっち上げても決して透過できない性格のものであり、兎に角坐るしかなかった。
朝は4時からの暁天の坐禅に駆けつけ、退社後は7時からの夜坐でじっくり坐りこみ、一日を3~4時間の睡眠で過ごす毎日であった。若かったこともあり体が持ったのと、何よりも常に意気軒昂、一歩一歩と真理の高みに近づいて行く充実感は、何物にも代え難いものがあった。人生誰にでも華の時期があるとすれば、私のそれはまさしくこの時期であったろう。
6年間の修行の間に、あたかも熟した実が落ちるように老師のもとで在家のまま出家し「大禅」の名を頂戴した。後に老師に嗣法し、釈尊以来滴々相承してきた血脈を受け継ぐことになる。
愈々福島を去る日がきた。往時の偽らざる心境は「このまま老師のもとで一生を仕えたい」というものであった。しかし老師からは東京へ出て仏教学を修めることを強く勧められたことと、これまでの叢林の修行を世に出て事上練磨せよとの指示もあり、後ろ髪を引かれる思いで上京した。禅の修行には限りがない。現実の自分の生活のなかに禅を生かし実践していく工夫三昧の日々が、次に待っていたのである。
時に昭和49年8月のある暑い日であった。
玉木祥通老師の遷化は昭和58年6月15日、私の名古屋支店勤務時代である。
老師の遺偈は次の通りであった。
七転八転 七十一年
売水河頭 呵呵大笑
遇遇大笑者誰
「七十一年の間、河の傍で水を売りつづけてきた。『水など傍にいくらでもあるではないか。何を無駄なことを!』と呵呵大笑できるほどのど偉い奴がこの場にいるかー」との、我々への強烈な問いかけである。仏であることを忘れ、喉の渇きを癒さんと水を買うのに躍起となっているのが我々である。もともと仏であることに気付かせるために、あの手も使おうこの手はどうだと暦日無かった老師の生涯であった。
思い起こせば、最初に私が仏たる自分に気がついた大感激の涙をもって、世を捨てて出家しこの道を真一文字にと決心した時、すでに妻と彼女の腹には子とがいた。思い余って問うた私に老師は、「家族を守っていくのも立派な菩薩行だぞ」と静かに答えてくれた。
あれから四十年、苦しい時の夢枕に今も立ってくれる老師である。その度に、福島の修行時代に受けた朝夕の、厳しくも思い遣りに満ちていた老師の鉗鎚を思いだす。
明易し来し方問へば波の音 浪雅(俳号)
*鉗鎚(けんつい)――禅家で用いる棒・言葉などによる策励
|