インド・ネパール旅行記(written by Y.H.)
Traveling Period: 19 Feb - 26 Mar 2003
Traveller: Y.H.
「インド」と言うと、わたしは「弱さ」を感じない。それはあくまでもわたしが感じたインドの姿。ただ1ヶ月と少し旅行をさせてもらった「今」の印象だ。
2月19日早朝、国立の家を出る。こうして重いバックパックを担いで、しばらくは帰ることのない家に鍵をかけるのは今回が4回目。飛行場までの道のりはこれから始まる旅行のことを思えば足取りも軽いし、通勤する人々の視線も気にはなるが不快ではない。
成田発バンコク行きのエア・インディア(305)に乗る。カルカッタまでの直行便はなく、バンコクでの乗り換えが必要で、確か月曜日と木曜日以外は当日乗り換えができない。やむなくバンコクで1泊し、翌20日にAI353でカルカッタへ向かった。
カルカッタ
ダージリン
カトマンドゥ
ポカラ
バラナシ
カジュラホー
デリー
カルカッタに到着したのは21時20分。比較的乗客は日本人が多かった。わたしは正直インドが怖かった。某ガイドブックを読み込み、デリーinはリスクが大きいと結論を下し、少々高くなるがカルカッタinにした。1泊目の宿も日本から予約をし、空港からホテルまでのトランスファーもお願いをしていた。
夜の見知らぬ国の空港。しかも薄暗い、ときたら夢の中の様な不安に襲われる。蛍光灯の力が夜の暗さと拮抗しているような、そんな空港。ここがわたしのインドの入り口。
トランスファーのタクシーはカルカッタ市街に向けて猛スピードで走っていく。道は、暗い。わたしはオレンジ色の街灯にできるだけ注意を集中させ、逆に運転手ともう一人の男からの注意を引かぬよう意味のない努力をしていたが、そんなこと無理だった。
23日までわたしはカルカッタにいた。ウェスト・ベンガル州の州都。早くからイギリスの統治の下にあったため西洋思想をより早く吸収し、民族運動や宗教改革の担い手となったという都市。インド唯一の地下鉄も走っている「大」都市。近代都市?
わたしは1泊ドミトリーで70ルピーの宿「マリア」に移った。色々な国の安宿を見てきたつもりだけれど、ここのドミはすごかった。寝相が悪くてもベッドから落ちる事はない。なぜなら隣の人のベッドとの間に落ちられる程の隙間がないから。蚊もものすごく多く、しかも日本の虫除けスプレーの効果は無かった。またものすごい悪臭の原因はベッドの下で死んでいた猫のせいだった。それでも居心地が良かったのは、何故だろう?
インドで旅行中、「カルカッタはすることが、無い。」と言う人が少なくなかった。かのマザー・テレサの意志を継ぐ「マザー・ハウス」でのボランティアなどの目的がある人は別として、確かにカルカッタにはさして大きな観光の呼び物は無いかもしれない。
しかしわたしにとってインド最初の地ということも関係するかもしれないが、カルカッタは面白い。
黒い女神が祭られているカーリー寺院、セント・ポール寺院、ヴィクトリア記念館、プラネタリウム、一応「見所」と言われているところも見たが、面白いのはそこへ行く道中、もしくは宛ての無い散歩の途中にあった。
宿から一歩出れば、そこはインド人の生活の場であった。肩をいからせながらリキシャーを引く痩せた男性、道路の水道を利用して全身を洗う老人、路が「住む場所」である女性は観光客に手を差し出す。共通していたのは、皆みけんに深い皺が寄っていること。良くも悪くも日本でこのような表情に大量に出くわすことはない。
安宿街サダル・ストリートから出ると、チョーロンギ―という大通りとぶつかる。ここの歩道には大量の陽射しと排気ガスを浴びながら大勢の人が様々なモノを売っている。靴の紐、洗濯バサミ、人形、本、野菜、シャツ、下着などなど。
朝そこを通り、夕方また同じ場所を通る時、朝と同じように空気をポンプで送り先端のプラスチックの蛙をジャンプさせるおもちゃを変わらず独りで売り続けている老人を見る。今までも、そしてこれからも続いていくその老人の周りの時間の長さに少し落ち込んだ。しかし、その時間に関する感覚は、日本という「合理」を優先させる世の中で育ったわたしのあくまでも限られた感覚であるはずだ、と言い聞かせた。
23日、宿で隣のベッドになったアメリカ人の女性と共にダージリンへ向かう。彼女はインドに1年ほど居て伝統舞踊を習っているという超巨大なドレッド・ヘアーの素敵な人。インドにはたくさんの表情や感情があるから、好きと言っていた。
カルカッタのシャルダー駅を19時15分にニュー・ジャルパイグリに向かう列車は出発した。2等寝台。幅1メートルほどの寝台が上に3段吊られている。インドの列車は盗難が多く、特に女性は大変だ、というように聞いていたけれど、確かに目が回るような混乱を抜きにすれば体がさほど大きくないわたしにとって1メートルの寝台は快適なものだった。
またわたしのコンパートメントには鉄道警察のおじさんたちが乗り込み、銃を持っていたりして物騒だとは思ったが、さりげない気遣いを受けたり、豆をもらったり色々お世話になった。
翌日24日の朝8時15分、カルカッタとダージリンのちょうど中間あたりに位置する都市、ニュー・ジャルパイグリに到着。大分北上したので心なしか、寒い。カルカッタでのTシャツとチノパン姿にフリースを着た。
ここは世界遺産に登録されているダージリン・ヒマラヤン・レイルウェイ別名トイ・トレインの始発駅でもある。先を急ぐアメリカ人姉さんは乗合ジープで行くということで別れ、わたしは9時初のトイ・トレインに乗った。
これは、凄い。すごい列車だ。車幅は2メートル無いだろう。最高時速も30キロ程度。はじめのうちはスラム街のような中、人々の鼻の先を通っていく。しようと思えば握手もできる目線の低さ、速度。子供たちが走って列車を追い抜いていく。裸の子供が、手を振る。
バナナの皮で屋根ができた家々の庭には豚がごみを食べている。子供は誰に教わったのか、生きていくことには必要ないと思われるのに、皆列車が通ると手を振る。泣いている子も、遊んでいた子供も、目が虚ろな子でさえも。とても不思議なことに思えた。
トイ・トレインはしだいに坂道を登っていく。山の中を走っている感じが出てきた。列車はディズニーランドのスモールワールドにいるかのように、緑のトンネルをくぐり、花畑を横切り、小さな村の中心を突っ切っていく。スイッチバックを繰り返しながら次第に空気が肌寒く感じるくらいにまで高度をあげていく。
列車から見る人々の顔も、しだいにチベット系のわたしに似たような顔が増えここがインドであることを忘れてしまいそうになる。標高が高まるにつれ唯一の防寒着であるフリースのジャケットでも心もとなくなる。停車駅で飲む熱いチャイが最高に美味しかった。
9時間のトイ・トレインの乗車後ようやくダージリン到着。ちなみにジープだと4時間で着くそうだ。標高2134メートルの地。イギリス人が避暑地として利用し、また紅茶の名産地。街は山にそって張り付くように上へと広がっていく。霧があたり一帯を覆い尽くし、とても寒い。インドの誇る山カンチェンジュンガはガスで覆われていてみることができなかった。
重いバックパックを背負い坂道を登りながらの宿探しは一苦労だった。オフ・シーズンの今、殆どの宿が休業状態。かろうじて開けていてもそこは各国のバックパッカーで満員状態。普段以上に心臓がドキドキし、息が上がっていることを自覚しつつ山をどんどん上がっていき街のはずれあたりにきてやっと空いている宿を見つけた。
寒い、とにかく寒い。暖房器具などあるはずもない。しかもシャワーからは水しか出ない。ここで意地でシャワーを浴びたのが原因だろうか?これから1週間下痢に悩まされることになった。それから熱も出た。旅行中、ひとりで風邪を引いた時ほど日本に帰りたいと思う時はない。寒くて眠れず、目を開けて横になっている時間の長かったこと・・・。
ダージリンにはチベットからの難民が多く住んでいる。日本人に近い顔をした人々にはやはり安心感というか親近感を感じた。とにかく高低差のある街で街の低部にある植物園へ行くのに、行きは15分で行けたのに帰りは1時間かかる、と言ったような具合である。ふと目を上げれば、街の向こうには霧が広がり海の上の島のように感じることもあった。
セーターを買った、ショールも買った。でもまだ寒い。下痢も治らない。こんな原因さえなければわたしはダージリンに1週間いても飽きなかっただろうと思う。しかしとにかく暖かいところに行かないと、死ぬ。と思ったので意識が朦朧とする中、次の目的地ネパールのカトマンドゥに向かうことにした。
26日、朝8時ダージリンからシリグリ行きの乗合ジープに乗る。ダージリンからネパールを目指す人は朝出発した方が、夜行バスに乗ることができるので時間とお金の節約にもなるので都合が良いと思う。1台のジープに12人くらいがすし詰めになり、ものすごい勢いで山道を下っていく。後部座席はふきっさらし、そして揺れる。わたしのお腹は何度も限界に達していた。
シリグリはインドとネパールの国境近くにある比較的大きな都市。ここからジープを乗り換えてインド側の国境のまちラーニガンジへ。イミグレーションを済ませ国境を渡るのはリキシャーで。ここまでくると陽射しが暖かく感じられてきて、少し幸せ。
ようやく国境を越えネパール側のボーダーの町カカルビッタに着いたのは午後2時。午後5時発カトマンドゥ行きの夜行バスを待つ。いっきに英語表記がなくなり、ネパール語だけの表記になったのにはとまどった。ここでもたくさんの人と出会う。
夜行バスといっても日本の高速バスなどをイメージしてはいけなくて、本当に小さな古いバスだ。リクライニングが機能するのは2台に1台くらいではないだろうか。わたしは小さいから良いのだが長身の欧米人男性は座席の狭さにキレ、運転手に何か言っていたがたぶんどうしようもない。ちなみにわたしの座席は床にむかって斜めに傾いており、足でかなり踏ん張っていないとお尻がずり落ちた。
そんな修行のようなことをしつつカトマンドゥに向かう。隣にはネパール人のヨガのグル(師匠)が座っていた。耳に葉っぱを挟み、始終数珠を振り回している。訛りが強すぎてほとんどわたしには聞き取れない英語で「スピリチュアルなこと」についてずっと話してくれた。そのうち「religion」が「science」に取って代わること、またどんな神よりもまず精一杯自分の両親を尊敬すること、そんな事を言っていたことが心に残っている。
翌朝の27日9時、カトマンドゥ着。かつてカトマンドゥはヒッピーの聖地だったというが、現在は毛派のテロ行為などが危険視されているのか旅行者の数はめっきり少なかった。その分宿の値段は70%ディスカウントなどざらであった。そんな訳でバス、トイレ付きシングルが2ドルもせずに泊まれてしまった。
カトマンドゥの安宿街タメル地区はアジアでも有数のバックパッカー御用達の土地。安宿、みやげ物屋、食堂などが一所に集中している。中でも印象深いのは「ふるさと」「味のシルクロード」を始めとする日本食を出してくれる食堂が結構あること。そこでわたしは卵粥と味噌汁をつくってもらい、久々にお腹に易しい食事をとることができた。
カトマンドゥの街には至るところに神々を祭る祠がある。そこを「チョーク」と呼び、そこから路が様々な方向に向かって伸びている。木造の古い家屋が道に迫り出すように立ち並ぶ町並みは、他のどの様な国でも見たことの無い「異国」であることを強く感じさせるモノを持っている。しかしそこは同時に人々の生活の場でもある。
何十個ものレンガを頭に引っ掛けた麻布に入れて運ぶ男性、道端で野菜を売る女性たち、観光客を待ち構えるリキシャーの男。全てのネパール人がそのカトマンドゥという街に良く馴染んでいる。当然のことと言えばそうなのだが、わたしはそのことをとても羨ましく感じた。たとえ服をネパールの人々と同じようにし、カメラを宿に置き、地図を見ずに歩いてみたとして、わたしは完全にこの土地に違和感無しで存在することができないことが残念に思えた。
仏教の聖地スワヤンブナート、ネワール族の都パタン、ヒンドゥー教徒の聖地パシュパティナートなど見所はたくさんあるが、わたしにとってはカトマンドゥの街自体が完全に興奮の的であったし、インドとはまた違う穏やかな混乱状態のようなものが、とても気持ちがよかった。
3月1日はシヴァラトリというヒンドゥー教の祭の日であった。シヴァの誕生日らしい。その日パシュパティナートに出かけたのだが、その混雑ぶりは凄かった。女性はみな赤いサリーを身に着け、インド、ネパール各地から駆けつけたサドゥ―と呼ばれる遊行者たちは寺の奥の森の中で参拝者達にガンジャーを配っていた。
全身に灰を塗りたくり、木に括りつけたブランコの上でガンジャーを吸い恍惚状態となっているサドゥーを取り囲み、一般の人々も年に一度のこの「スモーキング・フェスティバル」を静かに楽しんでいた。森のあちこちから神を賛美しているような歌声とその伴奏を勤めるタブラーの音が聞こえてくる。特に皆で何かを執り行うと言うわけではなく、各々がその祭を楽しんでいる様子が、「他人」であるわたしにとっては居心地の良い場所にしていた。
カトマンドゥには3泊し、2日の朝カトマンドゥから西に200キロ程のところにあるポカラに向かう。一人旅の良いところは、朝目覚めてふと「移動しよう。」と思ったその日の内に、自分の行きたい次の目的地に向かうことができることが、一つ挙げられると思う。

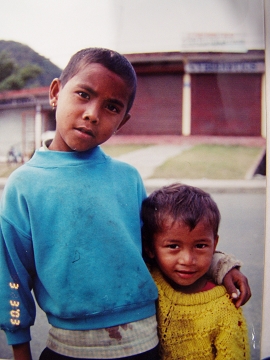
カトマンドゥからポカラまでの路はとにかく悪く、運悪くバスのタイヤの上の座席になってしまった時には座席とお尻をくっつけておこうとすることに必死にならざるを得ない。酔いはしないが、寝ることもできず、ただひたすら6時間窓の外を眺めていた。でもわたしは、居心地の良いお気に入りの都市で長く滞在することと同じくらい、移動している瞬間が好きだ。
ポカラは標高800〜900メートルでカトマンドゥよりも低い。しかし、そこから8000メートル級のヒマラヤ山脈が何も遮るもの無しに見ることができる場所だ。また湖が町の南北に広がっていてその上をボートがのんびりと行き来しているようなのどかな、小さな町である。
バス停で待ち構えていた大勢の客引きの一人についてゆき、ダムサイドと呼ばれる湖よりも若干南側に位置する安宿街へ行く。本当に観光客が少ないのか、バス・トイレ付きのシングルの部屋が、カルカッタのドミトリーと同じ値段で借りられてしまう。
次の日の早朝ドアを強くノックする音で目が覚める。ドキっとして急いでパスポートを体に巻きつけドアを細く開けてみると、宿の小父さんが「マウンテン!マウンテン!」と言って次の部屋をノックしに足早に去っていった。わたしは起きたままの姿であることも構わず、屋上への階段を駆け上っていった。
そして屋上からは登り始めた朝日に照らされているが、青と白のみのヒマラヤ山脈がすぐ手の届きそうなところに広がっていた。ここ数日曇っていて見られなかったヒマラヤが久し振りに顔をだしたので、小父さんが気遣ってみんなを起こしてくれたのだ。わたしはこんなにすぐ近くにあのような巨大で美しいものが今まで隠れていたのだと思うと、少し怖くさえ感じた。
CGの合成みたい・・・、そんな感想が出てきてしまう程、わたしが今まで見てきた光景には前例がないような大きさ、鮮明さ、美しさがあった。だれにも媚びない完全な自然のままの山々を、人々が「神の住む場所」というのも納得ができる。
ポカラは小さな町で1日あれば町を回ってしまうことができる。そして何処に居てもヒマラヤ山脈が見える。町の外れ、湖の途切れた所からは水牛が草を食む田園風景が広がっていく。トレッキングの拠点となる以外は特に何がある場所でもないが、のんびりすることができる静かな所だった。
3泊目の朝、山々とお別れするのはとても残念だったけれど、短い旅行故に次の目的地であるインドのバラナシに向かうためにポカラを後にした。バスに乗り、国境の町スノウリに行く。バスの助手であるような少年が「バイラワ!スノウリ!」と叫びながらあちこちで客を拾いながら向かう。
バスの乗客たちと必死のコミュニケーションを図っていると、8時間という時間はあっという間であった。完全に日本での8時間とこちらでの8時間は全く違う時間の長さで、わたしはこういう時間の経過の仕方が大好きだ。
スノウリに着くとすぐにリキシャに乗って双方のイミグレーション・オフィスに寄ってインドに入る。インド側の国境ナウタンワから18時半のナイトバスに乗り、バラナシに直行する。そのバスは特にひどく、隣の男と完全に体が密着してしまうほどの狭さ、そして混雑ぶり。揺れ方もひどく、眠ることができなかった。何も見えるはずがない暗闇の窓の外をずっと眺めてみる、そしてふと上を向くと満点の星空。フラットに受け入れてしまえるのは日本を出て驚きの連続だったからだろうか。
翌日のあさ8時頃バラナシに着く。バラナシと言えば、ガンジス河のほとりにあるヒンドゥー教の聖地であり、毎日のように死者の送り込まれる街。ここで火葬されその灰をガンジス河に流してもらうことで、この世の輪廻転生から解放されることを願うインド中の人々がここに運ばれてくる。
ここでは地図がほとんど役に立たないと言ってよい。なぜなら幅1mほどの路地が迷路のように入り組み街を形成しているからだ。ガンジス河の流れている方向だけをたよりに人に聞きながら安宿の集中している場所を探す。牛、羊、ヤギ、犬、猿、猫、人・・・、そして彼らののこす排泄物が路地をうめつくし、その匂いが強烈。でも不快ではない。
特に細い路地で牛とすれ違う時は本当にスリル万点と言える。インドでは牛は神聖な動物で邪険に扱う事はできない。実際はインド人も生活の場所で気ままにうろつく牛を邪魔に思っているようだったが、街から追い出すことは決してしない。ビーチサンダルで過ごしていたわたしは何度牛の糞を浴び、そのたびに宿に引き返し足を洗っていたことか。しかしそんな出来事も楽しくてしょうがなかった。
わたしは、ベンガリー・トラという小道から少し奥に入ったところにある「シヴァ・ゲストハウス」というところに2週間お世話になった。ベッドひとつがやっとはいるような狭いシングル・ルームで1泊50ルピー。そこがわたしにとってバラナシの城になった。全ての物に座っていても手が届く狭小性、4階まで吹き抜けになっている踊り場、窓が無いことを抜きにすればとても快適な宿だった。
ガンジス河はどちらが上流なのか一見では判断できないほどゆっくりと流れている。バラナシ市街のある岸にはガートという階段が河沿い続いており、その川辺は人々の生活の場、また死者が荼毘に臥す場所である。そしてその対岸は不浄の地であり、まったく何もない荒野。この対比がとても鮮明でいっそうこの特異な街を印象づけているように感じた。
不謹慎ではないかという思いを抑えながら、死体が一体焼かれていく状況を一部始終見た。近親者に見守られながら河の横で人は焼かれていく。まず皮が沸騰するように膨らみながら焦げていく。口からはキラキラとひかる血が流れ出ていた。次に白くなった筋肉が現われそれが焼けていくに従って体が解体していく。
腕や足などと違い燃え残りやすい胴体などは、人の手によって棒で叩かれ粉々にされていく。一番最後まで残るのは、頭部だ。一体が燃え尽きるのに焼く3時間ほどかかった。そんな作業が流れるように淡々とこなされていく。だからだろうか、わたしも感情的になることはなかった。こうした光景を見ていると「死」ということは必ずしも否定的なことではなくて、むしろ「生即ち、苦」ということが強調されて感じた。しかしあくまでもその場は、淡々としていた。
バラナシでわたしはタブラーというインドの伝統打楽器を習っていた。宿に借りてきたタブラーを置き、暇な時間に練習し、1日2時間のレッスンを受ける。先生とお金にまつわる静かな争いを繰り返し、毎日恒例となった停電時の暗闇と格闘し、また慣れない筋肉を使ったことによる筋肉痛に悩まされながらも、日本ではめったに感じることのできない充実感を感じていた。
タブラーは2つの太鼓がセットになっており、腹に響くような低音から空を突き抜けるような高音までが出るようになっている。それを様々なテクニック、リズムの決まりごとに従いながら組み合わせて演奏するのだが、それが凄く感動的なほどメロディー的というか、打楽器への固定観念を壊すほど流れるようなまとまりを作り出すことができる。
朝7時頃に起き、朝食を食べる。そしてタブラーの朝のレッスンを受け、宿での練習後に昼食。お昼休みをし、ガートに日陰ができる時間帯を見計らって散歩に出かける。入ったことの無い路地に入り込むと大抵道に迷う。それが楽しみでもあり、時間があっという間に過ぎていく。急いで夕方のレッスンに向かい、終わったら夕食。夜は屋上でボーっとしたり本を読む。そして10時には就寝。2週間の間にこの様な生活習慣が確立された。
宿で仲良くなった日本人の人とボートに乗ってろうそくをガンガーに流したり、またホーリーという年に一度シヴァの目が閉じるという祭を経験したり、夜な夜なインド音楽のコンサートに出かけたり、毎日飽きることは無かった。行き着けの食堂やチャイ屋、顔なじみもたくさんできた。
1日1回は必ずガンジス河を眺めた。インド有数の観光地であるバラナシ。もちろん観光客相手の商売も発達しているし、人々も抜け目がない。でも腹が立たず長く居たいと思わせた原因は何だろうと考えてみると、やっぱりガンガーがあったからとしか言いようがないような気がする。
インド人にとってもそこは、金の落ちる場所である以前にガンジス河のほとりの聖地であることが第一にされている。そして、神がとても近くにいるまぎれもない「生活の場所」。早朝にガンガ―に行くと、沐浴し祈る人の横で洗濯をする人が居たり、サドゥ―が瞑想をしている横でお土産屋の少年が大声をだしていたり、そんなバランスという気の利いた言葉では表せないが、経験したことの無い調和がある場所だった。
4日の滞在予定が1週間になり、2週間になってしまった。おかげで予定していた数都市を削る羽目になってしまったが後悔はしていない。一人旅の良い所のもう一点にこうして好きな場所に好きなだけ居られることも挙げられる。わたしがタージマハルを見る事を諦めたからと言ってそのことに文句を言う人など一人もいないのだ。
そんなバラナシも出なくてはいけない。残された日にちは気がついたら1週間になっていた。またたった2週間ではあるが半径500mほどに限定されてきたわたしの生活範囲の中で、気疲れというものが出てきたのだ!まさか一人で出かけた旅先で、とも思うが誰もわたしのことを知らない所へ行きたいという思いも出てきた頃だった。
19日、次の目的地カジュラホーへ。ここには1000年前に築かれたヒンドゥー教の寺院が残っており、天女像、ミトゥナ像(男女交合像)が有名で、その寺院群86年に世界遺産に登録されいる。
まずバラナシから鉄道にのりサトナーという中継の街へ。そこでやむなく1泊。そこで泊まった宿には考えられないほど蚊が居た。これは悔しいので書かずにはいられない。蚊から身をまもるため汗だくになりつつも持参した筒状のシーツを頭までかぶり顔に毛布をかけ窒息しそうになりつつうとうとするのだが、痒くて目が覚める。シーツの上から刺す!刺す!刺す!結局寝たら蚊に負けると思い、夜中蚊を殺し続けたが何箇所刺されただろうか。まぎれもなくインドに来て最悪の体験であった。
翌朝、カジュラホー行きのバスに乗る。ホテルよりバスの方が良く眠れるとは何事だ。ガイドブックには相当の悪路だから覚悟せよ、とあったがまったくそのような心当たりの無いまま、目が覚めたらそこはカジュラホーだった。
わたしは客引きがいれば、客引きについていってしまう。確かに当たり外れがあるけれど、メリットとしてはバス停や駅からホテルまでその客引きが車かリキシャーで連れて行ってくれる。重い荷物を持ってうろうろするのは疲れるし、好きではないのでバスを降りてからホテルのドアまで直通というのは、わたしにとってなかなか魅力的だ。
そこそこのホテルだった。田舎町であるせいか値段もすごく安い。カジュラホーは小さな町だ。寺院群が無ければただのしがない農村だっただろう。そんな小さな町がわたしは何故か好きになれなかった。バラナシの印象が強すぎた、というほかに何か原因があるはずだ、と思い考えてみた。
観光客に開かれすぎた町だった。すべてがツーリスト中心になっている印象を強く受けた。バラナシにとってのガンガーがそこには無かったように思う。小さな町故にしょうがないのかもしれない、それが生活していくため避けようの無い選択なのかもしれないけれど、絶えず監視されているような息苦しさを感じてしまった。
カジュラホーの寺院群自体はとてつもない迫力だった。壁の表面を彫り込んでいるという次元ではなく、彫り抜いて人間が完璧な立体で現われていた。そして曲線が石とは思えないくらい柔らかだった。そして何より数が、多い。やっぱりわたしは数の多さや、大きいものに弱い。圧倒的な迫力は律儀に寺院全面に彫り抜かれた無数の女神たちの数によるところが絶対大きい。
何故このようなエロティックな男女交合像が多く彫られているのか。後であった日本人に聞いた話だが、昔はヨガや瞑想、断食といったいわゆる苦行によって悟りを開こうとした人々と、一方完全に快楽に身を任せ切ることで悟りを開こうとする2つの潮流があったという。そしてこの地のチャンデ―ラ王は後者を選んだということだった。どっちを選びますか?
カジュラホーは1泊しかせず、21日の夕方デリーへの直行バスに乗る。閉めても手で押さえていないと開いてしまう窓を必死で押さえながら夜の道をバスはひたすら走っていった。やはり日中暑くても朝夜は冷える。
明るくなってきて外の風景が見えるようになると、明らかにそれは今までのインドとは違っていた。まず道路が広くて、きちんと舗装されていること、コンクリートで建てられたビルが建っていること、公園があること、そしてカルカッタでさえ見なかった外資系ファーストフード店が至るところにあること。デリーに着いた。
デリーはインドの首都。人口はムンバイ、カルカッタについで3番目だが完全に政治の中心地になっている。道が広く、建物も白かったり、並木が整っていたり、どこかのヨーロッパのような光景も見られる。さすが首都と言う感じ。まあイギリス人が創ったものだけど。
ニュー・デリー駅から伸びるパハ―ル・ガンジはデリーの言わずと知れた安宿街。カルカッタのサダル・ストリートに負けず劣らず混沌としている。世界中の旅行者がうろうろする場所だ。わたしの泊まった宿には中年元ヒッピーみたいなおじさんたちが1日中何をするでもなくハッパを吸い続け、夜にはギターを伴奏に歌を歌っていた。
結局デリーには22日から出国日の25日まで3日間居たが、ガイドブックに載っている名所にはどこにも行かなかった。いつもそうなのだが、最終都市はどうしても「心ここにあらず」状態になる。食事とネット以外は「小さな城」わたしの部屋でボーっとする。日本に帰った時のことを想像し始めると何も手がつけられなくなってしまう。旅行の終わりが見えてしまうこの時期ゆえの倦怠感がうっとうしい。
インターネット1時間の料金が、カルカッタ、バラナシでは20ルピー、カジュラホーでは40ルピーであったが、デリーでは10ルピー。しかも比べ物にならないほど速い!比較的涼しいし、恰好の暇つぶしの場所になった。日本に居ても開かないような大学のホームページを熟読してしまったりした。まあそんな1日も今考えるととても楽しい、贅沢な1日なのだが。
唯一したことと言えば、布屋で布を選んで買い、仕立て屋さんに持ち込んでパンジャビー・スーツを仕立ててもらったことだ。インド人が皆着ているような目の覚めるような鮮やかな色の布の中からわたし好みの物を見つけるのは至難の業だったがそれも楽しかった。布代、仕立て代合わせても400ルピー、即ち1000円と少しで服が仕立ててもらえる。良い国だ。
25日、インディラ・ガンディー国際空港から日本に帰国した。 約5週間の旅行だったけれど、今まで行った旅行の中で最も早く時間が過ぎていった旅行だったと思う。逆にインドに居る間は一日がゆったりしているように感じていたが。全てに合理的である必要がない、ということに気付いたあたりから楽に時間が過ごせるようになった気がする。
インドでは列車の3時間遅れとか平気でプラットフォームに座って待つことができたのに、日本に着いて、スカイライナーが時間通りに1分遅れただけなのにイライラするわたしとは、いった何?やっぱり旅行をして思うことは、今回も例外ではないけれど、異国の地(今回はインド)が必ずしもわたしにとって「他」ではなくて、もしかしたら日本が「他」と考えるのが自然なのかもしれない、と。
今回インド・ネパールを約1ヶ月旅行することができた。今思うことは「絶対もう1度行くな。」ということ。物理的にも、精神的にもインドは大きいし、濃いし、複雑だと思う。そこに居れば居るほど分かってくることが比例して増えていくんじゃないか。限界なしで。分からないけれど。
そしてインドは「強い」国だと感じた。いたるところに問題山積みだし、貧困問題だって差別問題だって根深いはず。でもわたしはインドに「弱さ」を感じなかった。どこかに人々は簡単に「フニャ。」とは決してならない芯を持っていたように思う。それが何なのか、その根拠は何なのか、まだ分からないけれど、日本で暮らすわたしたちには無い「強さ」を絶対に持っている。
安全な場所からこうして文字にするということは、完全に事を限定してしまう行為で、わたしの勝手な思い込みを文字にしてしまうのは無責任かもしれない。でもそんなことも意に介さず受け入れてくれそうな懐の深さというか、無頓着さというか・・・、そんなインドがわたしは大好きだ。