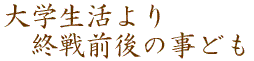
一.大 学 生 活
五年間の教員生活をやった後、再び学生生活に戻ったロートル学生、親のスネもかじらずアルバイトもせず、独立人として学生時代を過すことができたことを有難く思っている。
八ケ岳の修練農場で合宿訓練に参加して見たり、晩秋の猿ヶ京温泉で二週間程過したり、自由な生活を楽しんだ訳だが、主要なエネルギーは勉強に注がれた様である。それも無目的、無計画な知識の吸収であった。結局教えることより教わる方が楽だという訳で、東京商科大学にふさわしくない様な講義種目をあれこれと沢山聴講した。
一橋会の懸賞論文には、二年の時も三年の時も応募したが、三年の時、入選発表者名が食堂に張り出されているのを見たら野崎義之と出ている。しかし題名は正に自分の書いて出したものであったので一橋会執行部に尋ねたら書き誤りと分った。―つまらぬ事を覚えているものだ―「一橋評論」にもジェイムス・ミルの教育論について書いた。三年の夏休みは数日間帰省しただけで、図書館に通うのが日課、七時の閉館時間が近づくと、係員が「もう仕舞いますよ」 と言う。その声を聞いて帰り仕度をし外に出る。冷え冷えとした武蔵野の夕暮れの空気を吸う。満ち足りた爽快な気分。こんな気分はもう二度と味えない。
ささやかな楽しみは新宿のムーランルージュ通い。月に二度番組が替わるのだが、新番組が始まると、万障差繰り東方へ。今テレビタレントで活躍している者の中には、ムーラン出身者が可成りおる。テレビを見ていて「これもムーラン出身者だ。馳 け出しの者と違って芸が確かだ」というと女房は「又始まった。何度も聞きましたよ」とぬかす。ムーランのプログラムは粗末な紙に印刷された小さなものだったが、詩情溢るる散文詩で埋まっていた。丁寧に保存してあったのだが、何時か引越しの時、整理してしまったのは残念。
二、開戦・繰上卒業の頃
開戦の報せを聞いたのは中野の下宿(既に結婚していた妹の家)で卒論の仕上げにかかっていた時であつた。それから数日後、ふとした因縁で知遇を蒙むることになった大阪の貿易商岩谷昌雄氏(故人)から燈火管制下の浜町で卒業を祝って貰ったが河岸は真暗闇で、たまに会う人は警防団だった。
同門の伊奈重熙、橋本八十彦君と共に、妹の手料理、乏しい酒で卒業自祝の宴を張ったがその時大声で合唱したのが「なんにも言えず靖国の宮の階額づけば‥・」だった。橋本君の伯父さんが当時武名の高かった和地部隊長だったせいもあってか、 彼が良く覚えており、他の二人はこれに和すという恰好だった。ちなみに彼が中央信託富山支店開設の時、スポンサー銀行の代表者の一人として第一銀行の峰岸常務と共に富山にやって来た。その際この話をし、今度は僕が教えてやろうという訳で、雪の降る街を歩き乍ら歌ったのが、こまどり姉妹の「女の恋」。‥・死ぬも生きるも女の恋は、命かけます一筋に、可愛いお夏は恋故狂い、八百屋お七は身をこがす‥‥。呑み屋街から彼の宿迄相当の距離があったので、歩いているうちに彼はすっかりマスターしたのだった。
三、卒業・戦争・戦後
卒業後の行先は、大阪府堺市立堺商業学校ときまっていた。高瀬先生が勧められた東亜同文書院大学を断り、自ら選んだ途である。理由はあったにしろ、温厚な先生が「この際、僕のいうことを聞いておいた方が良いよ」と言われたのを断ったのだから、事実上の破門と覚悟していた。ところが先生は一年半後、大連高商の口を再度持って来てくださった。当時は戦局漸く我 に非なることが判って来た頃だったので、向うへ行けばどうなるかという事は略々見当がついていたが寛大な先生の態度に感激、行く決心をした。
大連へ赴任した年の夏、暑さの酷しい山県通りを歩いていたら、ムッソリーニの失脚、バドリオ政権の成立をラジオニュースで聞いた。愈々来るべきものが来たという実感と共に、その前の講義の時間に、特定の世界観に立脚した学問の不可なることを力説したことを思い出し、まんざら嘘を言った訳でもなかったと感じた次第であった。
敗戦迄の二年余りの間の出来事は全く目まぐるしいものであった。大連高商は大連経専と名称変更になり、経済科と工業経営科に分かれた。中等学校は五年制から四年制に変わり、若い入学生を迎えることになった。そして学徒出陣、勤労動員等想い出はいろいろあるが、余計なことをしゃべって他人様に迷惑をかけた事件がある。
昭和十九年夏のある日、丙種合格、第二国民兵の小生も在郷軍人として一日がかりの簡閲点呼を受けた。当日の査閲も終わり、兵事部長の講評となった。「本日某専門学校教授は休憩時間に”B29が来襲すればよい”という発言をしている。この男は自由主義者だ。自由主義は共産主義よりも有害な思想なのである。斯様な非国民から教わっている学生も多数本日の点呼に参加しているが当然不真面目な者ばかりである。よって本日の点呼の成績は不良なり」と結んだ。大連在郷軍人第五分会長は その後を受けて日く、「長年簡閲点呼に立会って来たが、かかる一人の不心得者のために不良なりとの講評を頂いたのは始めてである」と壇上で男泣き。今から考えれば一個の漫画であるが、満場粛然として声がなかった。当日は雲一つない晴天で暑 く、点呼参加者は皆上半身裸体を命ぜられていた。それで小生、昼休みの時、学校の同僚と一緒にしゃべっていたが「今日みたいに天気の良い日にはB29がやって来るかも知れない。みんな裸だから、こんな時に来たら怪俄人も多いだろう」ともらしたのであった。
翌日学校へ行くと、一緒に点呼を受けた一同僚日く「君、良く今日学校へ来られたね。昨日あれから君は憲兵隊に引張られ、 もう帰って来れないと思っていた。君の傍に見知らぬ男がおったが、あの男がスパイだったらしい。関東軍は無茶するからね。発言に気をつけた方がよい。」この話に小生全く肌に粟を生ずる思いだった。
昭和二十年七月二十日過ぎ、人並みに召集令状を貰い、馬糞の散らばっている貨物列車に積みこまれ、降された所は遼陽で あった。有名な白塔の周りをかけ足させられたり、楊柳の生えている遼河の岸にも連れて行かれ、帰りは軍歌をどなった。
シャバにいる時の考課状が悪いので、何のかんのと皮肉を言われ、撲られるやら蹴られるやらの毎日であった。
敗戦の日は、奉天郊外の東陵で迎えた。東陵は清時代のある有力な皇帝の墓であって、不毛の満洲には珍らしくウッソウたる樹木に囲まれていた。満洲は元来樹木の育たぬ所ではない。樹木はおろか草木一本も我れ勝に先取りして燃料にするという住民の掠奪様式が荒涼たる原野にしてしまったものと思う。参道には彩色された陶器のこま犬がずらりと並んでいて見事だっ た。八月末日漸く動き出した汽車に乗り、所持品はみんなソ連兵にとられ、大連の自宅にたどりついた。途中沿線の民家には戸毎に青天白日旗が翻っている。漢民族は何回も異民族の統治を経験しているので、少くとも五種類位の国旗を用意していると聞いていたが、なる程なあと思った。
帰宅した翌日、学校へ顔を出したが、勿論授業どころでない。各教室は住宅をソ連軍に接収された教職員の避難所にあてられていた。旅順大連地区はソ連軍の最高権力のもとに中国の保安隊が治安を維持する仕組みになっていた。大連市は総人口約六十万、うち日本人は約二十万と言われていたが、満洲の奥地から身一つで逃げて来た日本人が大勢いて、これらの人々は大抵学校に収容されていたが、発疹チブスが流行してバタバタ死んで行った。すべての日本人は、敗戦の日から自活して行かねばならなくなり、優勝劣敗、適者生存の生物界の法則が支配する世界の中におかれることになった。
小生は敗戦後暫くして満洲油脂(日本油脂の子会社)大連工場に勤めることになった。工場長の娘さんが戦争末期から学校の図書館に勤めていたが「先生、もう学校も事実上なくなった訳ですから、父の工場へ来て会計課の仕事をして頂けませんか」 という。そのうちに工場長と副長が拙宅にやって来て懇請され、結局内地に引揚げる迄ここで生活の糧を得ることになった訳である。
この工場は始め現地人労働組合の監視下、日本人の旧経営陣で、曲りなりにも生産を続けていた。そのうちソ連の軍管理となり、イリン中尉が最高責任者となった。その時従業員主人を審査して、必要な者は残し、他はやめさせた。小生は最低の給料で居残ることになった。理由は、外国語ができるから米軍がやって来た場合、通訳にでも使えるということだったらしい。席は相変らず会計係であった。会計主任が居たので特別仕事らしいことはせず、専ら本を読んだり、会計主任が尋ねることに答えたりしておれば良かった。ところが間もなく会計主任が工場に出て来なくなり、小生が会計主任ということになった。 事態が次第に平静を取戻すと、軍管理に代って、ユクスポート・フレイプ(支那語で糧穀貿易公団)の管理となり、経営専門家が乗込んで来て、小生はザメスティテイ・グラウニ・プッハルテリヤ(財務部長、経理部長、常任監査役を兼ねたような役職、ザメスティティというのは代理の意味である。代理といっても正式の部長がおらないので職務内容は正式部長と変りがない。給料も三倍位に飛躍した。外国語よりも会計能力を認めてくれた訳である。間もなくモスコーから監査官が来た時、当工場の会計帳簿が、大連所在の油脂工場五社の中で最も正確に記帳されておるというので、おほめに預り、「代理」の肩書が なくなり、日本人、支那人従業員の中で最高給を貰うことになった。ソ連本国から来た経営専門家のコロスコフ氏がディレクトル(最高経営者)小生がグラウニ・プッハルテリヤとして紙一枚の出庫、一円の支払でも必ず二人の署名がなければならない。会計の処理―原価計算も含めて。特に原価場所計算が労働生産性測定の尺度として重視された。―は極めて厳格であった。 ところがディレクトルは立派な家具を一セット買って来て彼の部屋に運び込んだ。インフレが相当に進行していたので、以前からあったものと比べたら百倍以上であった。金庫を預っている小生に支払いを命じたので証拠書類添付の上、出金伝票を切った。その後でディレクトルは以前からあった帳簿価格の低い同種の什器(例えばソファ或は机など)と一緒に記入し、平均単価を算出し、一率にこの単価で書き改める様命じた。小生はこれが会計慣行に反する旨説明したが、彼は命令だといって、分ってくれない。しかし小生は頑として聞かない。三日間ニ人ともロをきかなかった。ところがそのうち右に述べたモスコーからの監査があった。監査の成績は上々だったので、ディレタトルの気嫌はすっかり直っただけでなく、以前にも増して信用してくれるようになった。日本人通訳が二人いたから、読み書きは一切通訳がやってくれる。しかし二人とも管理、会計のことは分らないから、結局この方面の事になると通訳を通すより直接話した方が良く通じる。それでロと耳だけのロシヤ語( 勿論文法などには叶っていない)で押し通した。経済政策担当の同僚が生活費を稼ぐ手段として、ロシヤ人から彼等の配給物資を買いとり、日本人に売り渡す商売をやっていたが、日曜日には小生が彼の通訳としてロシヤ人将校夫人と交渉にあたったこともあった。
引揚げの日が近づいたある日、ディレクトルがエクスポート・フレイプ本社の幹部と日本人従業員の名簿を前にして話をしている。どうやら小生が問題になっているようだ。話しの内容は、野崎は財務に明るいから、引揚げを延ばさせる。そしてモスコーへ連れて行くというような事である。翌日ディレタトルが小生を呼んで一年引揚げを延期しろと切り出し、その様にしたら配給品はソ連人並み、砂糖、米、石炭も充分支給するという。敗戦の動乱期に漸く生き残ったのに、又米ソ戦(当時は米ソ関係は険悪であって、戦争の可能性大との噂が専らであった。)にでも巻込まれたら大変と思い、凡ゆる手段を尽して引揚げを懇請、辞職許可書を貰って佐世保に上陸したのが昭和二二年二月二八日であった。