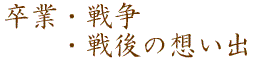
「十二月クラブ」という会の名の示すとおり、激動と動乱の時代の中できわめて異常な卒業を経験した。それだけに余計あの頃のことが想い出されるのもまことに当然だと言える。のんびり構えて、昭和十六年の夏、休暇が終って学校に出てみれば、
お前たちは十二月に卒業だ、卒論を早く書くようにとの指示、 まことにあわただしい。それだけに学生時代の最后の仕上げがゆっくりできないで、いわば未成熟児で卒業し、そのまま軍隊送りという始末である。
その未成熟児の烙印は、ずっと今まで私のどこかに押されているような気がしてならない。
人生の不可思議に解決を求めて、卒論に哲学をえらび、如何に生くべきかを考えて、出口のない、暗い時勢の中で模索していた頃の自分が何となく懐しく思い出される。
いくら絶望的な環境でも、若いだけに若さのエネルギーで苦しさに打ち克って行った生命力を思うと、自分なりに、その頃の若き自分に対して第三者としての立場から賞讃の言葉を送りたいと思う。
卒業と同時に入隊した軍隊生活も、敗戦で終止符を打ち、引揚船の甲板の上で、黒く沈む佐世保の港をながめ、海面に尾を引いて映える灯をみつめつつ、忽然として自分の生き方の根本にふれた感慨は今も忘れ得ない。人生に対する悔恨と、その中から過去を洗い流して生れ出てくる新しいものへの確固たる自覚、あんなものをインスピレーションというのかも知れない。今でもそのときの価値転換は、はっきりと想い出される。
末の男の子を外地でなくし、長男は引揚船のペットの中で発熱している。妻と三人で着のみ着のままでようやくたどりついた内地、卒業後五年間の人生とは何と儚いいものであったか、人間の歴史とは何であり、これから如何に生きるかを本当に真面目に考えた。この辺が未成熟児の未成熟児たるの所以であろうか。しかし今では、戦争に負けてよかったと考えている。あのまま日本が勝ち戦を続けていたらロクでもない人生を生きていたのではないかと思う。
敗戦を自分の肉体で感じ、同僚たちの尊い血の上に築かれた自分たちの人生の価値を改めてかみしめ続けたいと思う。
「きけわだつみの声」を読みながら涙を流した自分を思い、使命感に燃えていたあの頃がなつかしい。
「鋼鉄は如何にして鍛えられたか」の中の一文が格調高く思い出される。
「人間にあって最も大切なもの、それは生命だ。それは人間に一度だけしか与えられない。だからあてもなく過ぎ去った歳月に、いたましい思いで胸を痛めることのないように、卑しくくだらなかった過去に恥辱で身を焼くことのないように、また
死にのぞんで生涯を一貫して持てるすべてのカが世の中で最も美しいとの、人類解放のたたかいのために捧げられたといい切れるように、この生命を生き抜かなければならない。そして生きることを急がねばならない。」
齢五十三の現在、戦後激動の時代の中でかみしめつづけてきたこの言葉のように生きられたら俺の人生はベストだと思う。
過去を回想するとき、人間は自ら若々しくなるものらしい。