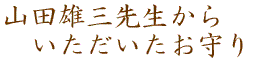
それは、私が駆逐艦乗組の時であったから、多分、昭和十七年から十八年にかけてのことではなかったかと思う。乗ってい た艦が、作戦の都合で、佐世保から横須賀に回航になり、ここにしばらく滞留することになった。そこで上京した機会に、久 しぶりに山田雄三先生の下落合のお宅を夜分訪問した。その頃は、ソロモン海域で、ガダルカナル島をめぐつて日本海軍が全兵力を投入しての激しい攻防戦が続けられ、しかも日本の敗色が次第に濃くなりつつある時であった。
私は、昭和十六年十二月に卒業と同時に、三菱商事に入社したが、僅か十日余りいただけで、一月二十日には、海軍二年現役主計科士官として築地の海軍経理学校に入校した。四ヶ月にわたって訓練をうけた後、五月末に重巡衣笠乗組を命ぜられ、内南洋のトラック島で衣笠に乗艦した。このときから以後、約二年にわたる私の艦隊勤務がここに始まったのである。
当時は、ミドウェイで初めて我が機動艦隊が惨敗をなめ、多くの犠牲を出した直後であった。そして艦隊勤務にようやくなれたと思ったとき、最初の試練が第一次ソロモン海戦である。それは、昭和十七年八月七日、当時海軍で飛行場を建設中であったガダルカナル島に突如として米軍が上陸し占領した。このときラバウルにあつた八艦隊は、八月八日の夜ガダルカナル沖ツラギ海峡に突入し圧倒的勝利を得た。このツラギ夜襲に衣笠も参加し、初めて砲火の洗礼をうけたのである。このガダルカ ナル島の攻防をめぐって、日米の主力が正面衝突をし、ソロモン海域が主戦場になった。この間に、私は衣笠から駆逐艦に転勤し、いくたびか死生の間を出入し、今日、はるかに往時を思いやるとき、私の人生にとって、はかり知れない貴重な経験と思い出を残してくれたと思う。私のもらった辞令は、第三十駆逐隊附というもので、当時三十駆逐隊は、睦月、望月、卯月の 三艦編成であった。ラバウルで衣笠を降り、折から入港していた睦月に着任した。望月、卯月は作戦行動中であり、睦月もま た、ニューギニヤ方面に作戦行動に出る寸前であった。そのため、ラバウルにあって待機、望月の入港するをまってこれに乗艦せよ、と指示をうけ、とりあえず荷物はそのままにして、身のまわり品だけもって即日下艦、ラバウルの司令部で待機して いた。ところが、睦月はそのときを最後に、ニューギニヤ沖で空襲にあい、沈没してついに帰らなかったのである。死と生と 紙一重なるをここでも体験した。当時は駆逐艦の快速力と機動力を買われて、全く息つぐひまもない程、作戦にかりたてられていたのである。それだけに多くの犠牲も出している。そして昭和十七年の末、残務整理と艦修理のため、佐世保に回航した。修理期間中に、戦死者、行方不明者等の残務整理も終り、次の作戦のため横須賀に向ったのである。
横須賀から上京して、家に帰ったあと山田先生のお宅にうかがったときは、夜になっていた。先生の書斉で久しぶりに先生と対座した。暗幕をかけて暗くした書斉は、あくまでも静かであった。煙草のお好きな先生のことだったから、多分そのときも静かに煙草をくゆらせながら、語っておられたのではないかと思う。自分はそのとき先生に何を語り、また先生からどんなお話をうかがったか、残念ながら今は記憶にないが、ただ、艦に乗ってからの異常な緊張に、自分ながら荒んだと思う神経が 不思議に安らいだことを思い出す。話しは多分、学校のこと、学問のこと、そして日本の敗色が決定的となった戦局のことであったろう。そして、このとき忘れようとしても決して忘れ得ない一つのことを今もありありと思い出す。そのとき、ふと先生が、かたわらの奥様の方をむかれながら、「船乗りには昔から金比羅さんの信仰がある。君さえよかったら、金比羅さんのお守りをおくってあげようか」と云われたのである。思いがけない先生のお言葉に、ちょっとどぎまぎして、「はい、いただきます」と答えた。そのときの約束どおり、先生から金比羅さんのお守り札がとどき、私は有り難く頂戴して間もなく横須賀 を出て再びソロモンの戦場に赴いた。
戦局はますますひどくなっていた。そして日本は完全に押されていた。私の乗っていた艦も傷つき、辛うじてラバウルまで僚艦に曳航されて帰った。この間に先生からいただいたお守り札も南太平洋に没した。ラバウルでも修理不能で、さらにトラ ックまで戻った。トラックに入って間もなく、連合艦隊の山本長官が前線視察のためトラックを出発されるのを見送った。山本長官の戦死が伝えられたのはこれから間もなくである。日本の敗北を痛いほど感じた。大和、武蔵を擁する連合艦隊の偉容を見ながらも、何か精気のないものを感じた。私はトラックにおいて、機雷施設艦へ転勤を命ぜられ、駆逐艦を降りてジャバのスラバヤに向った。
私は、山田ゼミでは第二回生だから、ゼミに入ったときの先生はまだ助教授で、ウィンの留学から帰られて余りたってない頃であった。当時の先生は新進の理論経済学者として、その頃横行した日本経済学という怪物にも、少しの妥協も許さず、理論の孤塁を守った数少い学者のお一人であった。当時の私共は、このような先生の態度に尊敬と共に、ひそかな誇りすら感じていた。合理性をあくまで追求される先生から、非合理の世界のお守り札をいただいたことを有難く思う。先生は合理を尚ばれたが、いわゆる合理主義者ではなかった。人間の心のひだまで感じとられる直感力も豊かにおもちであった。私はここに先生の人間味に触れた思いで、今も心暖かく思いおこすのである。山田ゼミ三年間の生活は、やはり懐しい思い出に満ちている。
この思い出の一端として、このことを記した次第である。