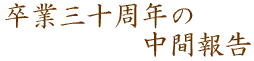
五組 和田 一雄
三十年前、卒業に際して是から出発する人生の旅を、一体どの様な考え方で処してゆくべきか、呑気坊主の私にしては、比較的真剣に考えた。其の結論としては、鈍才の私が此の厳しい世を生き抜いてゆく為に出来る事と云ったら、賢明な人達が厭がり逃げる様な仕事を進んで引受けるか、或は利口な人達には其の結論が見えて居て、そんな事をやってみても馬鹿々々しいと、取り上げ様ともしない事で、其の儘に放置しては世の中の為にはならぬ事を、馬鹿者の私は少しでも多く取り上げてやってみよう、と云う事であった。
勿論、意志の弱い、ぐうたらの私の事であるから、必ずしも万事此の精神でやり抜いて来たとは、決して云えない憾みが今も大きく残って居る。然し乍ら、方向丈は之から大きくは逸脱して居なかったし、やって見た結果は、私にとって全くの無駄であった事は一つもなかったと考える。その為に今の私には、「鈍才は鈍才なりの活路が必ずあるものだ」と云う信念が強く育って居て迷う事が余りない。
此の鈍才的信念が、次に私に植え付けたのは、「殆どの物事はやって見なくては判らない、真剣に取組む限り、やって見る事自体に果てしなく価値が内在して居る」と云う事であった。ついでに付言すれば、此の考え方は私に更に、貴重な教訓を与えて呉れて居る。それは後年になって気が付いた事ではあるが、世の賢人達は大概、きまった事の様に同じ、ミステークを犯して居る事がある。即ち、一つの課題なり、プロヂェクトなりを取上げる場合、其の計画が如何に実現される可き価値があるか其の計画は如何に完璧であるかどうかの、審議検討は充分に実施され、時間も掛けられるが、肝じんな誰にそれをやらせたら充分に期待通りの成果を挙げて呉れるか、と云う人選に就いては洵にいゝ加減な御座なりの措置で決定して、何等の懸念も不安も感じないケースが実に多い、と云うことである。先見性に富み、予見能力の高い賢明なる人達も、事業そのものに目が眩み、事業は人なりと云う、人の世の基礎的原理をお忘れなさる事が多い、という事を指摘したい許りの、横道入りを許して頂き度い。
扨而本論に戻って、世の賢人諸士の取上げ様ともしない、予見された結果は否定的である事どもの中にも、全く放置する事を許されぬ事柄も亦多く存在する。例えば瀕死の病人に対する医者の処置や、倒産必至のボロ会社の整理などは、そう云った仕事の部類に入るものと云える。処が結果は予見された通りである場合もあるし、万に一つは取組んだ人間関係から、予期せぬ好結果が出て来る場合もあって、神様丈が御存知的要素を全く否定する事は、人間社会では未だ許されぬものと考え度い。又死地に入ってもがく事自体が、経験的に、教育的に重大な価値を持っている場合も多々ある事は、世の賢人諸士も強く否定は出来ない筈である。
此処にこそ、人の世の奥深い面白さがあるものと私は信じて居る。斯う云った考え方が、此の三〇年間の私を支配して来た訳だが、鈍才がそれなりに生きる道を求めてもがく過程は、更に賢人諸士の不得手とする着想なり、考え方の存在する事も教えて呉れた。即ち世の中の事は一度は私心を離れて考察して見る事が大切であるとの考え方である。斯うした考え方は世俗的には、案外と通用して居ないのに実は私自身が驚いて居る。どちらかと云えば利口な人達程この考え方をせぬ場合が多いのも不思議な位である。だが私は今迄身を置いて来た大組織の中で、所謂出世主義第一で要領良く立廻り、危険の予測される仕事は仮令その仕事が其の大組織の為に必要事であり、誰かがやらねばならぬ種類の仕事であっても、それが脚光を浴びる種類の仕事でない場合は、極力その仕事は他の馬鹿者にやらせ自分は出来る限り歩の良い見て呉れの良い仕事を汲々として求める人達の多い事に慄然とした事が多々あったのは、私の属する大組織の為に洵に遺憾に堪えぬ思いで一杯である。
要するに便所掃除的仕事はエリートのやる仕事ではないと云う思想が、私の身を置く大組織でも或は又この世の中全般的にも余りにも強く通用し過ぎて居る事に対して、卒業以来私は強く反発して来た。この思想は軍隊での幹部候補生時代の予備士官学校で、私をして専ら便所掃除とタン壺磨きに坐禅を組むが如き努力をせしめた。斯うした考え方で世の中を見れば、他人の放置した仕事で 鈍才の私でも社会の為に貢献出来る仕事を探すには事をかゝない。又この私心を離れた見方で物事を判断すると、賢明なる人々でも見落したり、ミスヂャッジしたりする問題点を、鈍才の私の方が的確に正しく把捉出来る場合も多くあり、鈍才も又捨て難い点があると自負して居る次第である。
以上の処世観に加えてサラリーマンとしてスタートした私に今一つの信条がある。それは一生サラリーマンで終るつもりがないならば、一瞬たりとも所謂サラリーマン根性にはなり下がるまいと云う決心である。従って今日迄私の名刺の肩書は最初から、「社長心持ち」と云うものであると考えて来た。此の心構えは後年、即ち今から二年前の昭和四五年に只今の会社の再建の為に、自ら志願して傭われマダムの社長になって出向した際にも、社長たる自分は如何に在るべきか、或は社長は何をなすべきかと云った様な問題でと惑う事は一切なかった事は有難い事であつた。
此の脱サラリーマン、否超サラリーマンとして若輩の時から自分の職務を、いつも自分が社長であっても斯く判断し、斯く業務遂行をやるかどうかの反省をし乍らやろうと心掛けて見ると、上司の俗サラリーマン的判断や出世主義的便宜主義的態度が、往々にして我慢出来ぬものとして私を刺戟して、反抗精神の持ち主として睨まれ、随分と同僚と差のついた待遇に永年甘んじなくてはならなかった。だが此の事に私は決して損をしたと云う後悔もして居ない。寧しろ損をしたのはもっと早く私に大きな任務を与えなかった会社の方であろうと自惚れて居る。そして苦難に満ちた下積みサラリーマン時代に、私は得難い人づかいの勉強をさせて貰った事を今日つくづくと感謝して居る。即ち将来部下を持った場合には、どんな事があっても部下を不幸にしたり、部下の仕事の邪魔をしたりする様な上役に丈は決してなるまいと誓って今日に及んだ事である。今日私にさゝやか乍ら自慢出来る僅かの事の中で、正しく努力する部下を只の一人も今迄に不幸にしたり、進路を間違えさした事がないと云えるのは何より幸福であり、有難い自慢の一つである。今迄よく昔の御得意先から和田学校の卒業生は皆、優秀であり信頼出来ると云われて来た事は、私にとっては会社に対する私の貢献の中で最も大きなものであると考えて居る。又不思議な事に曽って私が必死に反抗した上司は皆、晩節を必ずしも全うせずに中途で会社を去って行かれて仕舞った。サラリーマンとして幸福の最大のものは良き上司に恵まれると云う事である、と云うのが此の手記の最后の結びの私の感想である。
