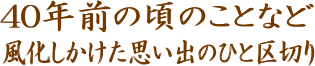
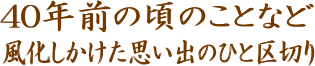 |
5組 井手口一夫 |
|
何が切っ掛けで、そうなったのか、今はすっかり忘れてしまったが、倉垣と二人、太宰治(当時三十三才)に会いに行こうということになった。中央線三鷹駅南側の近くの飲み屋だったか、そのガランとした広い土間の右むこうの片隅に、カウンターに片肘を付いて、人げない静かな雰囲気を楽しむかのように、太宰治は、真昼のコップ酒を独りゆっくり傾けている。 かれがじーっと眼を光らせているように思えたのだろう、少しばかり硬くなって、初対面の挨拶もそこそこに、徐々に近付いて、来訪の意を告げる。「まずいものではありますが、折角書いたものですから、読んで見て下さいませんか」と拙詩の原稿を差し出して、丁寧に訴える。 私たちは、太宰に連れられて、かれの住いを訪ねることになるのだが、途中、道ばたの、のれんに「うどん」とある屋台をのぞき、急いでうどんをすする。 やがて、かれの家の前まで辿り着く。玄関を開けると、小さな上り口の向うに、赤ちゃんをおんぶした奥さんが、優しく迎えて呉れる。隣りの部屋に案内され、早速、私は、同人雑誌「白鳥」(同人は、倉垣・横山・木島・高木と小生の五名。昭和十六年八月二十日発行)に載せる予定の「合掌」という題名の原稿を、こわごわ差し出す。それは、私の「青春」が残照に影る頃、梅雨空の欝情を拒んで、裸身で闇に向う自我像の断片に過ぎない。太宰は、ちらちら見ていたが、最後の三行を指さし、「ここだけはいいよ」と素っ気なく云う。 嫋嫋として忘れられた美しい双生の敵が 今にして思えば、それは、錯倒した没落意識と、そのいびつな暗さを吹き払おうと焦るあがきの痕跡だったような気もする。 花あれば花を愛し 奥さんが横で、「主人はお客が来ると直ぐ、こうして書きたがるんですよ」とたしなめるように、少しばかり不満そうに私に眩く。 さて、こうして書き綴っていると、高木勇兄との交わりが自然、滲んで来る。頑張って、幾分憂いにやつれ、茶色がかったその顔色。当時から、おのずと身についていたおおような大人の風格。 「ヴァレリーを一天才の悲劇として観ることは確かに文学的な見方には相違ないが、然しそうした観照の態度はヴァレリーが最も嫌悪する所である。もとより我々がヴァレリーの作品を読み暗い所を模索して彼の面貌に思い到る場合、我々はヴァレリーを作品から書斎に移しているのであってこゝに文学の不思議さがあり救いがあると云える」と。 ここには、「作品と作者」をめぐる古くて新らしい問題を、弱年の力をふり絞って精一杯、穿岩せんとする高木のきびしいヴァレリー観・文学観が躍動していないか。 どんなに気を配っても、栄養のバランス配合を自ら整えたとしても、胃の脇が受けつけなければ、正常な血液循環が阻外され、引き締った肉体を養うことが出来ないように、頭脳の働き=知性が少しでも麻痺すれば、自ら発見した生の素材から、何ものかを新たに創り出して行く可能性は、それだけ閉されてしまうだろう。だから、身体上の「血肉化」は、頭脳の生き生きとした働きまで貫徹しなければならないし、「創造」という人間的・個性的な自己実現は、徒らに発見そのものに安住することなく、知性の可能性に向っての無限追求の営みに外なるまい。ひとり、ひとりの「営為」のかたさと厳しさを、高木は、ヴァレリーの湿気を絞り切った硬い英知の結晶にのめり込みながら、必死に自ら追い求めて行く。私は、高木の聡明な知性と鋭敏な感性からの啓発を通じて、青春の終えんの日々を、詩作を介して、「生」について、あれこれ学び得たことを、今でも心から有難いことと思っている。しかし、身体の余り丈夫でなかったかれにも、召集令状が遂に舞い込み、その貴重な生命は、満州の原野の片隅で、虚しく散り果ててしまった。今はもう、かれのたまの声を聞くことは出来ない。西荻の浩々居ーーそれは、先入者の川崎文治の推薦で入居を許され、同人の先輩。同輩後輩たちと文字通り寝食を共にしていた、広田弘毅大先輩がわたくしたち、在京する同郷の学生たちの為めに建てて呉れた学生寮ーーから、近くのかれのアパートを、よく訪れては、かれから受けた詩の手ほどきにまつわる思い出の数々が今もって懐かしい。 茜色の空の下にある たしかに見失われた面影の後姿をかれは、虚しく「花冠」に託したけれど、未来は哀しくねむり、戦争・軍隊・入隊という、あわただしい過酷な現実は、寒冷な満州の原野で、か細い、その肉体を無惨にも眠らしてしまったのだ。 戦後も余り遠くない日、偶々、鹿児島えの所用かたがた、西鹿児島駅から汽車に乗り、「隼人」という小さな駅で降り立ち、広々と田園風景の開けた田ん圃道を、トボトボと歩き、たしか、かれの伯父さんの住いと誰れからか聞いていた家に漸く辿り着いた。 さて、昨年一一月一一日付け日経新聞の「本との出合い」欄で、私は、はしなくも木島利夫の文に接し、一入、昔を忍ぶよすがに浸ったことだ。いうまでもなく、木島は、われわれの同人の一人であったし、通巻第二号ーーそれは、「白鳥」を改め、「真昼」と銘打っていたーーでの「まひるに」という題名のかれの詩は、白日に、ひっそりとさらされた、「石」の弧独で、静いつな情感に溢れ、「白い石の上で花びらが果てる」虚しさを一入いとおしんでいる。かれが、その文の中で、「…青春の一時期、文学を一生の仕事にしたいと大まじめに考えた…」と語っているのも、まことにむべなるかなと思ったことだ。 出 帆 ……頃未知なるもの、大らかな宴げ遥かに (昭和十六年八月四日作。五十六年五月二十六日若干修正。) |
 卒業25周年記念アルバムより |