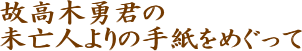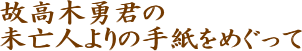|
私は古い一通の手紙を大切に保存している。長年の歳月を経て封筒も用箋も変色して、インクの筆跡も色腿せて薄くなり、もう読みにくくなっている。それは戦後の或る日、高木勇夫人から貰った手紙だった。若し今度の文集に物故会員に関する欄でもあるなら、その一隅にでも載せて頂けたらと、その紹介を兼ねて一文を草してみた。
高木君は予科在学中に胸を病み、休学して一年おくれ、私達と同期となって五組に編入された人だ。そんな事情から、此の人が忘れさられることを倶れる点も有るのである。フランス語には一年の長があり、何処か孤独な影もあるが、既に人生の悲喜を識ってしまっているという様な静かな眼差しで大人びた風ぼうを具へ、皆から一目を置かれていた人だ。私や一部の文学好きの者は敬愛して兄事し、親しく交際していた。今でも覚えているが、西荻窪の愛の里会館という下宿に、病気上りの故か郷里鹿児島から上京された母堂と一緒に暮して居た。同じ西荻窪の宿町にいた私はよく訪ねた。高木君は煙草が好きで、その頃まだあったあの「朝日」という煙草を愛用し、着物のたもとからおもむろにその袋をとり出すと、角を破いた穴から白い紙巻を振り出し、ちょっと吸口に凸みをつげて指にはさみ、唇に運んでいた。余り吸い過ぎては胸によくないのではと、いちど注意をしたら、いや、脂で病菌を殺してしまうんだよ、とまことしやかに応え、これは余計な注意となった。
母堂は小柄な人で部屋の二隅にちょこんと坐り、これまた長い煙管できざみ煙草を喫っては煙草盆の竹筒をぼんぼんと叩いておられた風景が今も眼の前に浮ぶ。高木君はその頃難解とされていたボオル・ヴァレリーの純粋詩に傾倒し、当時でも既に入手困難なヴァレリー詩集の初版限定本を何冊か愛蔵していた。活字の大きい大型のぼってりしたフランス綴のそれらを大切そうに見せてくれた。ほかにも、かの総皮装袖珍本のプレイアド版ボードレール著作集(当時は二冊本であった)も所蔵していた。彼にはそんな一種のぜいたくがあった。趣味は釣りで、しかも鮎釣りである。机の脇に立てかけた紺の竿袋に飴色の太い見事な継ぎ竿が段々に細いものとセットで容れてあった。全部継いだら数間になるという代物でいづれなにがしかの竿師の作った銘品であるらしかった。下宿の部屋の窓から継いだ竿を突き出して振って見せてくれた。体力の要る渓流釣りを、母堂は危倶し乍らも病弱な高木君に眼をつぶって許容した様子であった。文士滝井孝作にも釣りの趣味のあることは彼から聞いて私も知っていたが、それに倣ったかどうか。何か高木君には若くして既に老成した大人の一面があった。
その高木君が卒業後には郷里鹿児島の伯父の経営する無尽会社に就職するという。早く父を失った高木君は伯父から学費一切を出して貰っていた事情もあり、本人は東京に留って就職したい希望だったが、義理上も断り切れず鹿児島へ帰ったのである。その後、会社の社内報の様なものを作っているということを噂に聞いた。
扨て、手紙のことだが、戦争が終って、あの激変の混乱時代を各自それぞれが生きることに追われるうちにもいくらかそれなりに身辺が落着いて来て、学生時代の友人達は皆どうなったろうかと周囲を見廻してみて、お互に安否を尋ね合い度くなった頃、在京の連中はどうやら消息が判ったのに、どうしても不明な級友の中には例えば深山厳君とか中村富士男君とかがあったが、高木君のことが私は気になり、どうしているだろうかと住所も判らぬままに、勤先の鹿児島無尽会社気付で高木君宛に手紙を書いた。処が返事が来ない。何時迄経っても返事が来ない。やはり消息不明者の一人となった。半ばあきらめ、自らの日常生活に追われつつ、すっかり忘れ果てていて、一年近くも経った或る日、一通の封書が届いた。裏を見ると高木初子とある。返信用にと私が同封して置いたその頃の記念切手、月に雁の図の紫色の長い切手が表面に貼ってある。いま見ると日付スタンプはかすれて明瞭でなく年が判然としないが、どうもその年も押し詰った十二月末日である。
ともかく次に高木夫人からのその手紙の全文を原文のまま掲げることにしよう。
「御手紙拝見致しました。うけ承りますれば高木の御親友でいらっしゃいました由誠に恐縮に存じて居ります。
私高木の妻で御坐います鹿児島無尽よりお手紙御届け下さいましてより心のむきませぬままに何時何時迄も失礼申上げました事何卒何卒お許し下さいませ。
高木は昭和廿年三月一日佐賀通信兵として入隊直後渡満致し新京にて軍務にたずさわって居りましたものの同年八月終戦と共にシベリヤヘ捕虜の身として、抱引、元来強健ならざりし高木には如何に心苦しき旅路で御坐いました事かついに十月廿七日骨身をけづる風雪の中にアルタイスカヤの収容所にてかえらぬ旅につきましたとは、高木の一大事業の発足を二、三日後にひかえての出征は誠に誠に心苦しきもので御坐いました。
必ずや生きて還ります事を約しながらも誠に誠に申分なき主人で御坐いました後や先なる無情の風は人力ノ如何程にも致しがたき事は知りつつも此の世の無情をのろえる丈のろいたい私で御坐います。
僅か一年三ヶ月の結婚生活では御坐いましたものの共に楽しく過してやれました事を何よりの慰みと思って居ります高木の忘れ形身勁(百ヶ日の時に出征)も明けて七ッの春を迎えます。
父親そっくりの勁、楽しみにつけ苦しみにつけ如何ばかりに心の奥をかきみだす事で御坐いましょう。それにもまして母の歎きは一入如何に話してよろしきものやら全く言の葉も御坐いませぬしかし勁の成長を楽しみにけなげな母は農事に精励致して居ります
孤独に等しい高木の母後生を楽しく過さして差上げたく心かけては居りますけれども中々に意も叶えませず実家の農地が少々御坐いますれば折柄事うるさき農地問題のため母に面倒を見ていただいて居りますので田舎と街をかけての忙がしい生活をいたして居ります。
母も呉々もよろしく伝えて呉れとの事で御坐いました
酒井嚢様は如何御過しで御坐いましょうか当地にて度々御目にかかり御なつかしく案じ申上げて居ります
又東北病院にいつぞや入院なさっていらっしゃいました小武山敬之様とかおっしゃいます方御健在でいらっしゃいますでしょうか御伺い申上げます
倉垣様は?
色々家庭の都合にて来年二、三月私親子上京致し度く心のままに明るい明日の道を歩いて行き度く考えて居りますでは皆々様へもよろしく皆様の御繁栄を御祈り致して居ります。 かしこ 高木初子
横山健之輔様
以上である。
之を読んだ時の驚きと衝撃。はっきり憶えがないが、折返し出した私の手紙に対してだったか、高木未亡人からのまたの便りだったかで、返事の遅くなったのは、高木の追憶と戦後の生活に触れると思いが千々に乱れて、とうてい、筆を執る気にはなれなかったので長い間無沙汰のまま過ぎた事と、シベリヤの荒野で他界した高木は自分の忘れ形身を夫人が懐妊していたのに遂にその顔を見ることが無かったという事を私に知らせて来た様に記憶する。
さて、之には後日談がある。その後、蒼茫裡歳月は迅く、二十余年を経たのちに、偶々私は公用ではからずも鹿児島へ出張する事があり、約一週間滞在した。
私としては九州の南端迄の旅は初めてのことで、之を良い機会に長年気になっていた高木未亡人をお訪ねしようと現地に着くと、先づ鹿児島無尽会社に問合せたが、社名もたしか旭相互銀行と変り、当時の幹部の人々は全部更迭して高木一族のことを知っている人は居らず、僅かに未亡人が田舎の実家に引退されていると聞いたとか、鹿児島市内の百貨店の階上で洋裁教室を開き教えて居られたことがあるとかの程度でさっぱり見当がつかなかった処、私の出張先の渉外係の人が根気よくトレースしてくれて、番地と各戸名入りの詳しい地図により遂にどうもそれらしき家を図面の上で見つけてくれたのが滞在期間最後の帰京するその日であった。若しやと訪ねて見た。
玄関の前に立ち、思い切って戸をがらりと開けると奥から出て来て、上り枢に坐った中年の婦人に「突然失礼でございますが、高木勇さんのお宅では?」と言葉をかけると、とっさに婦人は身をかがめ、ていねいに両手を突いて、私の顔をじっと見上げ「はい左様でございます。どちら様でございましょうか」と云った。
私はほっとして、救われた様に名乗った訳だが、何と二十余年の間隔を置いたこれが高木夫人との初対面であった。一ぺんに感懐がこみあげて何から話してよいやら戸まどった次第だが、高木君の遺児勁君は昨日迄此の家に帰省していたが、一日違いで昨日東京の大学へ戻る為鹿児島をあとに出発したことが判った。その日は私も残る時間も少なく、その後のあらましを語られるのをお聞きしたり、私も高木君の憶い出を語ったりして、一旦出張先に戻り、西鹿児島駅からの上り列車に向ったが、その駅頭に高木夫人は見送りに来て下った。東京で勁君に会ってやってくれと繰返された。
帰京後早速教えられた勁君の宿へ連絡したが間もなく或る日、休日だったか私が家に居た日に勁君が訪ねて来た。家内が「高木さんとおっしゃる学生さんが見えました」と私に告げ、既に通してあるという部屋に入ってゆくなり、私は愕然とした。なんと其処にあの学生服を着た高木勇君が坐っているではないか。そして慄然とした。
思わず「君は」と、あとは声にならなかったが「高木です。勁と申します。母からもお伺いしております」と明るい声が返って来た。余りにも似ているのである。往年の学生時代の高木勇君に生き写しなのであった。
勁君は青年らしく暗い日本の過去にはこだわらず、自分の将来のことに就いて語ったが、さすが母の労苦を思ってか、鹿児島には母も居ることですから、近く学校を卒えたらやはり鹿児島に帰って就職するつもりですと云った。
つぎに高木君にまつわる、我等の青春の一駒とも云うべきもう一つのことを紹介して置こう。
それは此の一文のはじめに、高木君を敬愛し、兄事した文学好きの者達といったその仲間、五組では高木勇、井手口和夫、横山健之輔、一組の木島利夫、倉垣修の五人が詩を主体とした純文学雑誌『白鳥』という同人誌を発行したことだ。尤も此の『白鳥』は第一号を出したのみで終っている。いま私の手許に遺っている一冊を見ると「詩」を同人各自が二篇乃至一篇づつ、「論文」が一篇(高木・ヴァレリーに就いて)、「創作」が一篇(倉垣・季節)の内容で、奥附の発行日は昭和十六年八月二十日となっているから、既に本科に入って三年の卒業近くの夏に出したものと見える。此の『白鳥』の他に私達は『真昼』というやはり文芸誌を一号出しているが、いつか家の中の何処かで見かけたことがあるのだが、いま見付からず手許にない。これにたしか旅を主題にした創作を倉垣と私が夫々「金弥」、「湯ケ島の宿」と題し一篇づつ書いた覚えがあるが、発行年など定かでない。兎に角、予科から引続き本科卒業の頃迄、学業をおろそかにして、かような事に取りつかれて青春を生きていた仲間があったということだ。
しかし、『白鳥』発行時の昭和十六年の夏と云えば、いまから丁度四十年前、あの十二月八日開戦、翌くる一月には殆んどの同期生が入営してしまう、半年前に当るのに、何も識らずに、青春のみが賦与するはじける様な感覚と溢れる情熱と静かな知性とに支えられて、精一杯、いかに稚き歌をうたっていたか、四十年の歳月に洗われたいまとなってみると、その是非を超えて、之は戦前期に存在した、或る種の精神風土の記録《エクリチュール》とも云えようから、同誌冒頭の高木勇君の「拝情詩」「ポプラ」と題する二篇を茲に紹介する傍ら、同人各自作の詩一篇づつをも併せ掲載して故人の霊を慰めるよすがとすると共に、私達にとっての一時代の墓碑銘といたしたい。
おわりに、謹しんで高木勇君の冥福を祈る。
昭和五十六年八月十五日
東伊豆北川にて誌す。
抒情詩 高木 勇
茜色の空の下にある
市場へと人は夥しく溢れ
夕暮の風は彼等の帰りを知らない
母よ 母もかへるな
石段の明るみに影を残し
花園の輝ける饗宴は鎮まつた
失はれし面影の後姿のみが
思念の如く訪れてくる所在なさに
窓に揺れる青い階調に指を染むれば
花冠の中に哀しく未来はねむる
ポプラ 高木 勇
絶えずまつはる
白い亡霊に悩まされ
かすかにそびえるポプラ
生きることの幻そのまゝに
日はゆらめいて空にあらはれる
夕陽は甍にあまねく
街は祈念に燃えあがり
みなし児の思もそこはかと燃えるとき
ポプラは己を支へる存在を知り
大いなる思想の片鱗をさへ見る
散文詩 横山健之輔
夏の宵。小路小路に木の葉が鳴り、未完の音楽の如く不動に復る。西空のピンクが硝子戸に冷く燃えるとき、倦怠の肉体にかすかなリズムがよみがえる。
高台に日輪は何を忘れたか。
生桓のほの暗い谷間に白シャツ、青シャツの子供等が灯す線香花火。いま、青葉と煙硝の匂にかれら酔ひ痴れるのだ。
小溝のふちに咲いた黄色の花花。おまへたちにも物語があるのか。紫陽花よ。おまへの冷い水色は? かって一緒に住んだ混血少女ローラの疑ひ深い瞳だな。
よし、またあの頓狂な甲高い笑声を虚空にあげよ。美しき痴呆。
家々に灯がつく。遠くかすかに聞える嬰児の泣声。突如、あゝ、この明星の蒼空に幼い日々が立ちかへる。母の唱った子守唄が。乳母車の車輪のひどき。
そヾろ歩きの俺のからだに日没喝を誦する僧侶が住んでゐる。
昼さがり 倉垣 修
どこかで松カサの落ちる音がした
はげしい松脂の香の中で
私は青い海を眺めてゐた
ねむつたような白雲
真昼の、眼に滲む海の青さを恐れて
潮の梢になる風に一心に
心をひそめてゐた、
あゝ、嘘のやうに平和な、
遠くに忘れ果てた私の風景画
旅に出た星・・ノヅーリスの詞のために 木島 利夫
山なみは 指さしてゐる
星々が かつて通つた 道の跡を
その星たちは もう帰らない
野の果に 荒れた砂浜が続き
それを 越え
こゝの海 あそこの海
合 掌 井手口和夫
梅雨嫌う贅楽が淀み熟したる光沢
の辺(ほと)りではタベが崩れた。
それ故にゆらめいて青白い蛇足は激
しい舞踏を病んで杳かなる廃嘘へと
流れた。
焦躁は渦いたにはびの肉(ししむら)に帰り……
髑髏が純粋を思念する
嫋嫋(じょうじょう)として忘れられた美しい双生の
敵が半顔を見開いて更に明るみへの
索引を強いた。
|