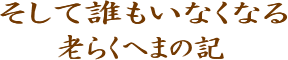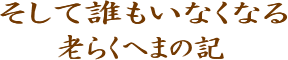| 月の石
もう十年以上も前のことである。僕は図らずも「月の石」を三回見た。最初は、上野の科学技術博物館。昭和四十四年の十二月クラプ総会前に集った仲間と共に、杉江館長の案内で裏口から入った。表は長い行列だった。次は、大阪万博のアメリカ館。そこも長蛇の列だったが、張漢郷君のお蔭でVIP扱いの裏口入館、家内が「悪いわ」を繰返して恐縮していた。三回目は、同年秋、翌年ドルショック後の「合意」で有名になったワシントンのスミソニアン博物館、というわけである。
何の変哲もない石なのだが、上野で見た際「月の石の年齢は約五十億年」という説明を聴いて、ちょっとしたショックを受けた。
気の遠くなるような五十億年に比べれば一瞬に過ぎない我が人生は、あと何年で終るのかというような一抹の無常感におそわれたのであろう。その夜の総会では、幹事が物故者の報告や三十周年の準備の話などをしているのを聞きながら、四十周年までに何人の仲間が亡くなるだろうか、七十周年には何人残るだろうか、などと考えていた。その頃、高橋勝君の影響もあって、アガサ・クリスティの「テン・リットル・インデイアンズ」その他の推理小説を、ぺーパー・バック本で読んでいたので、SFまがいのとりとめもない空想に引き込まれる始末であった。その空想をショート・ショートに脚色してみることにしよう。
Short Short : And Then There Were None.
二〇一二年十一月下旬のある午後、Zは如水会館のロビーの彼の常席である肘掛け椅子に身を沈めていた。館内の調度は程よく時代がつき、以前は窓から望むことのできた宮城の森も、立ち並ぶ高層ビルに遮られてしまっていた。
昨年の春、十二月クラブの七十周年記年東西懇談会に生き残り会員十人全部が参加、スペースシャトルで月旅行をした。もう余り珍しくなくなった月の石をみやげに、皆元気で帰って来たのだが、その年末の総会には半数しか残らなかった。今年になっても次々と会員が世を去って、会館の常連であったYも今月の始め亡くなった。その訃報の原稿を今会報編集部に届けたところであった。Zは取り残された寂寥感に身を震わせて、「一人では総会も例会もできやしない、いよいよクラブの後始末をしなくては、」とつぶやいて立ち上つた。
数日後の十二月初め、Zは会館の食堂に現れた。これも彼の常席であるテーブルに着いた。ここでは、人間的サーピスを建前にして注文キーボードやロボットコックなどの機器を導入していない昔ながらのレストランでZのお気に入りだった。顔なじみのウェーターに、「今日は一人総会でね」と言って最上等のワインとコースを選んで命じた。約三百人の亡友の冥福を祈って乾杯した。枯野を駆け回る思いでゆっくり食事をとった。「オールドブラックジョー」のBGMが流れると、「もう直ぐ俺も行くよ」とつぶやいた。最後のコーヒーを飲み終ると、ウェーターを眼で呼んだ。クラブ基金の「ワリソー」を処分し後始末をした後の残金の百万円札を渡し、「つりは取ってくれ」と言って、静かに立ち去った。近くのテーブルで食事をしていた中年グループの一人がZの後姿を見送りながら、「老人は哀れだな」と誰に言うともなくささやいた。
その後、Zは食堂にもロビーにも姿を見せない。そして、十二月クラブは誰もいなくなった。
ただ一度 ーー NICHT WIEDER
一昨年の九月、如水会館「サヨナラの集い」に出席した。中村達夫君の勧めで「歌声酒場」に席をとった。ところが、なんとなんと「ただ一度」を歌手が唄うではないか。僕はいささか興奮して、まわりの老人仲間とともに大合唱。中には眼に涙を浮かべて唄う者さえいる。僕はかねてこのレコードを探していたので、歌手に尋ねてみたが知らないと言う。それはともかく、この歌にめぐり会ったことは予期せざる収穫であった。
その翌月、NHKで、映画音楽大全集というのが放映された。これまたなんと、「会議は踊る」がリクエスト第二位を占めたのである。そこでNHKに問い合わせて、大全集のレコードを買った。更に渡辺公徳君に教えられて、昔懐しいドイツ映画のサウンドトラック版を入手した。リリアンハーベイ、ウィリーフリッチ、ディートリッヒ、スアルバース達の歌声を聞きながら読書をすれば、実にいい気分である。そのような場面が伊藤整の小説にあったことを思い出す。
この四月末、金原君宅での花見の宴に招かれた。その前の岡部君宅の観桜会には、残念ながら「ギックリ腰」で参加できなかったが、その腰もほとんどよくなった処だったので、喜んで出かけた。集る者は十二月クラブ員を含む一橋OB六名。庭に咲き乱れるリラを観ながら、飲み且つ食い且つ論じた。兼子君がドイツから入手したという「会議は踊る」「狂乱のモンテカルロ」などの録音カセットをかけたので、更に気分は盛り上った。果ては、興極まって庭に降り、寮歌などを唄い踊った。まさにオールドボーイの意気を示したのである。しかし、そのような宴の中でも、おのおの名句迷句を毛筆でしたためるという粋人ぶりを見せた。僕も対抗上いささか無理をして、「ライラック青春というはかなきもの」という拙句をものしたが、青春は、ただ一度、二度とない、げにはかなくもまたいとおしきものである。
行き当りばったり
この歳になって振り返ってみると、行き当りばったり、成り行き任せ、しかもどじとへまの常習で、今までよくもやって来られたものだと思う。「明日のことを思い煩うな」と達観していたわけではない。今度こそは行き詰ったかと観念すると、何となく道が開けて来た。観念するとまで行かない場面でも、十二月クラブの諸兄、一橋の先輩後輩を含めて多くの人に世話になった。有難いことだ。しかし、大企業に永く勤めている人にはぴんと来ないであろうが、中小企業を渡り歩く過程で一橋出身という経歴が、却ってマイナスに作用する場合も多かったのである。
ついでながら一橋とわが家族との関係について書き留めて置く。懇親旅行などでクラブ諸兄にお世話になった亡母の父は一橋家の臣下で、大政奉還後引き続き一橋に住んでいた際に、母が生まれた。亡義父も神田鍛冶町染料商の息子で、東京高商(大正九年)と専攻部出身だから一橋で学んだわけだ。家内も高商跡の共立専門学校出身で一橋に多少関係がある。因みに亡実父は、明石松平の藩士が先祖だが、芝白金の生まれだから準江戸っ子と言えるだろう。我が家族が、小心の癖に行き当たりばったりの楽天家でそそっかしくて駄酒落好きのお人好し、という性格を多かれ少なかれ共有しているのは、どうも江戸っ子気質に関係があるらしい。
それはともかく、高度経済成長のお蔭もあって「何処でも飯は食える」と糞度胸がつき「明日は明日の風が吹く」と、生来の無計画性を正当化して居直ってしまったきらいがある。辛うじて第二の人生に辿り着いたが、もとより老後の生活設計というような気の利いたことをやっていないので、これからも大変だ。今から心配しても時既に遅し、何とかなるさと、行き当たりばったり式を続けるしか手がない。
行き当りばったりと言えば、若い頃、一人で無計画に歩いて、ハップニングを楽しんだものだ。国立時代には、日曜日の朝リュックをかついでともかくも新宿発の列車に乗り、その日その時の出来心で立川から上野原の間で降り、奥多摩や高尾・景信・陣馬などを気ままに歩き廻った。ここ数年前まで、家族連れ交替運転のドライブ旅行も殆んど行き当りばったり方式だった。一応大ざっばな旅程は立てるが、それに拘束されない。楽しいところだと思えばそこでゆっくり遊ぶ。日没前差し掛ったところに宿を求める。駅があればそこで聞く。田舎の駅員は親切だ。宿まで車を誘導してくれる者もいる。時と場所によっては、ねらった宿が満室で断わられることもあるが、その宿で方々電話をかけてほかの宿を世話してくれる。紹介された民宿まがいの宿で、思わざる家庭的なサービスを受けて、もうけたような思いをしたこともあった。
五、六年前のことだった。家族四人で伊勢、志摩、紀州と回り、その間例の通り行き当りばったりの二泊、白浜で泳いだ後、東京に帰る長女を和歌山駅に送ってから、大阪方面に走ろうと思ったが気が変った。フェリーで徳島に渡って鳴門に向ったが、交通渋滞、途中で日が暮れかかった。次女が選定した沿道の宿屋は、玄関にトラックの運ちゃんらしき連中がたむろしていて恐れをなしたが、夕食に女中がつきっきりで大サービス、案外気分のよいところである。そこで約二十年前の阿波踊りを思い出して二木君に電話をかけた。
旅先で近くに知り合いがいれば電話で敬意を表するのがわが年来のしきたりである。東京近辺で特別の用もないのに電話をすれば迷惑がられるのがおちだが、地方では多くの場合喜んでくれるようだ。双方の都合がよい場合には会おうやということにもなる。
そのような突然の電話ではからずも、恒成・森・田辺・佐田などの諸君にお世話になってしまった。下関の坂本君からの年賀状に「東京忘じ難し」とあったが、東京で学生時代を過ごして地方に定住する者にとっては「友あり東京より来たる」ということで、特に歓迎してくれるのではないかと思う。二木君も電話を喜んでくれたのであろう。翌日オーシャン・フェリーの事務所で会うことになった。運転も飽きたのでフェリーで帰ることにしたのだ。
翌朝、鳴門の渦潮を見た後、二木君を訪ねた。彼は親切にも料金を安くしてくれた上に一等だか特等だかの個室を提供してくれたので、ちょっとした豪華な気分で安楽に帰京することができた。このような友人がいるということで、家内にも娘にもおやじの株が上ったものだ。これも行き当りばったりの功徳だと言うべきだろう。
落 差
最近おやじ(前述の亡実父)のことを頻りに思い出す。定年後も植民地(台湾)勤務時代の放漫な生活の惰性が脱けず、あせったおやじは投機株を買ったり泡沫事業に出資したりして、没落を早めた。昭和の初期に生活費が約三分の一に縮少するまで五、六年かかったようだ。オルガン、ミシン、たんすなど次々と家財道具が売り払われるのを見送ったり、広い家から次第に狭い家に転居したりすることは、十代の僕にとって悲しいことであった。落ちるだけ落ちての三分の一の生活費による暮らしは、その時代の中の下という位のものであったと考えられる。利息で優に中流生活ができる程度の退職金をもらっていたはずだから、始めから暮らしをそこまで落としておればなんのことはなかったわけだ。
そのような過程で、我が運命も大いに狂ってしまった。商業学校の受験組から商大予科を受けるつもりだったが、それを断念、ひどい不況期に辛うじて就職した。縮少均衡の気易さにうかうかと三、四年過してしまったが或る日思い立って、夜学、夜勤、月謝免除制などを利用して私大専門部経由商大学部の最短距離最低費用の進路を取ったというわけだ。いわば「苦学」だが、その頃は身の回りに貧乏人が多かったし、若かった故もあって、苦痛を感じなかったようだ。それどころか、貧しさの制約の中で、受験や成績に囚われず、「怠け者怠けてあればコーヒーの湯気の緩きに堪え難きかな」と適当に怠けながら、のんびり学生生活を楽しむことができた。「落あれば楽あり」である。
定年後の落差は経済的なものばかりではない。ステータスの下落は穏やかならざるショックである。再就職をしても、「玉座」から「窓際」へ、個室から大部屋へ、ぴかぴかの大きな机と椅子から薄汚い小さなものへ、というステータス・シンボルの落差は情けない感じのするものだ。たとえ系列子会社の社長になっても、名刺の会社名を一々説明しなくてはならないとなると、落差を感ぜざるを得ないだろう。ましてや、名刺に記すべき肩書きが無くなった時の頼りなさは、当分の間身にしみるものである。近所で毎日大型車で送り迎えを受けていた元会社役員が、引退後しばらくして再就職、通勤する姿を見かけるようになった。かばんを掛けているその肩に「落差」のさびしさが滲み出ていた。
幸か不幸か、僕はあまり上に昇らなかったので大きな落差がなかった。それにしても、家内はまず第一に中元歳暮のもらいが少なくなったのを嘆いていたようだ。
生き方死に方
十代の頃、ジョージ・ギッシングの『ヘンリー・ライクロフトの私記』を読んだ。彼は経済的にも家庭的にも恵まれない生涯を送ったそうだから、実際は悠々自適どころではなかったかも知れないが、その田園生活の記述は僕に相当の影響を与えたらしい。その故か、定年後の計画も準備もない行き当りばったりにもかかわらず、ただ老後は生計のための仕事にあまり時間を取られたくないという、比較的確乎たる考えをなんとなく持ち続けて来たようだ。先が短いのだから金よりひまが大事で、多少働くにしても今までとは変った仕事を持ちたいということだ。芦田君や本田君にたまに会うと「まだ働いているの」と冗談まじりに言うのは負け惜しみばかりではない。
現在、専門学校と短大でパートタイムの教師をやっているが、それが上述の条件にぴったりの仕事である。数年前の十二月クラブ総会の席上で、鵜沢君と教職は老後に適した仕事だというようなことを話し合ったことがあるが、その後はからずもその端くれに就いて、その通りだと思っている。無論鵜沢君や木村増三君などの大学教授とは同日の談ではないが、適当に体と頭を使い、若い人と接し、そして夏休みや春休みがあるのがよろしい。
パートタイマーだから組織とのかかわりが少いこともよい。教師冥利のようなものも漸く少し分って来た。教職の末端とは言え、あいつによく先生が勤まるなと思われるのであろう。何を教えているのかと訊かれることがあるので、課目名を記して置く。商業英語、実務概論、国際教養。家内と娘は僕が国際教養という柄ではないと笑う。専門は何かと訊かれると、太田ゼミ出身であり、また兼子君の勧めでNAA(米国会計人協会)東京支部の理事になっているという手前もあって、国際管理会計と答えることにしているが、これは多分にハッタリである。
現在週二日間に研究日というもっともらしい名称をつけて、毎週拘束されるパートタイムの切り売りにしないことにしている。従って週四日制、いや正味週二・五日制を採っていることになる。或る出版社の依頼で、ビジネス英語の本を書くことを気易く引受けたが、締切りがとうに過ぎたのに、未だに脱稿できない。しろうとの浅はかさである。しかし、売れる売れないは別問題にして、死ぬまでにスローモーションで何か特徴ある著述を一冊でも遺したいと思っている。
一昨年、三十八年ぶりの夏休みを利用して海外に住む娘夫婦と孫を訪ねた。予て小宮山君に住みよい所と聞いていたヨハネスプルグで、その生活を楽しむ様子を見て嬉しかった。何よりも感じたことは孫とはたんと可愛い者かということである。僕は孫に我が生命の延長継続を見た。その孫が二人になって、この夏家族が一時帰国でやって来る。家内は昨年ヨハネに行って来たのだが、今から「ばば馬鹿」まる出しでソワソワニヤニヤして帰りを待ち受けている。その前に次女を含めた三人で、台湾に行き、生まれ故郷を訪ねる予定、これで死ぬまでにやろうと思っていた事の一つを果せるわけだ。仲人をしていただいた上原専録先生御夫婦のお墓参りもまだ果してないことの一つである。
ともあれ、否応なく死に一歩一歩近づきあることは確実だ。終りよければ総てよし。今までの人生がお粗末であっただけに、せめてこれからよい生き方死に方をしたいものだ。最近「生きざま」ということばがよく使われる。僕の語感からすれば、「ざま」とは「ていたらく」で、「生きざま」とは望ましくない生活態様だ。「恍惚」や「瘋癩老人」や「植物人間」というような「生きざま」をしたくない。航空機事故で死ぬのが、死との対決時間も短いし、航空会社からの賠償金もあるから一番よい、と家内に冗談を言うが、そういう「死にざま」もしたくない。二、三週間畳の上で寝た後、二、三時間意識不明になって死ぬというのが理想的である。亡兄は臨終直前まで意識明瞭で従容として死んだ。僕には到底そんなことはできない。
もう一つ大事なことは死に順である。社長夫人が順序を違えて死亡した際の方が、社長本人の葬儀の時よりも、香典や花環が多いという、宮坂斗南房のビジネス川柳の材料になりそうな話を聞いたことがある。当方には花環など関係ないが、順序が狂っては都合が悪い。
僕が一時間探しても見つからない物を、家内は五分で探し出すという有様で、ばあさんが先に行ってしまうと不便でちと困るのである。
余生を送る条件として、経済的には甚だ心細いが、健康はまあまあ、家庭にも交友にも恵まれている方だろう。次女もそろそろよい相手にめぐり逢えることを期待する。安身立命とは行かなくても、心穏やかな日々を過ごして、無事に終着駅に辿り着きたいものだ。
追 記
文集委員としての事務が、前述の故郷訪問と行き当りばったり方式と組み合わされて、全く思いがけない仲間との邂逅を齋した。七月の委員会で台湾高雄在住の殷銘春君からの原稿未着と聞いて、台北あて通信のついでに同君に執筆を勧める葉書を出した処、思いがけなく折返し是非高雄に来いとの返事を受取った。台北にホテルを予約したが、主目的の生地(虎尾)と娘の希望による日月潭のほかは行き当りばったり、僅か四泊の不案内な旅なので、高雄まではとても行けそうもない旨書き送った。ところが、知人の紹介で訪ねた現地駐在の人の助言と手配で自動車を借り切ることによって、故郷でゆっくり幼少時代を偲んで宿願を達した上に、主な所を観光して夕方高雄に着くことができた。そこで事実上初対面の殷君に御家族を交えての思わざる歓待を受けて実に嬉しかった。いわば文集の取り持つ縁を記録に留めて謝意を表する次第。
|