| 7組 片柳梁太郎 |
| 学窓を出てから四十年、この間わたしはどんな精神面の生活を送ってきたのであろうかと省みてみると、われながらつくづくと頼りなく思われるこの頃である。戦争に行っても生き残って戻ってきて、始めてといってもよい職生活に入り、結婚をして、子供を育て今日にいたりはしたが、その間学生生活から軍隊時代を通じて味ったような精神的な昂ぶりを覚えたことがあったであろうか。その頃からの精神的な成長が果してあったのであろうかと反省して見ると、淋しい限りのように思われることばかりである。 省みれば、わたし達の大学生活最後の夏は、わが陸軍の仏印進駐、日米交渉の難航等戦争の前夜そのものであり、わたし達の明日は戦火の中を避けては通れないようなムードに包まれていた。われわれ当時の青年が、死生を超えた精神の安定を希う気持は、極めて自然のことであったと思う。 わたしは以前から湯島の麟昌院という禅寺が家の近くにあったので、毎月何日間か早朝坐禅に参禅していたが、学生生活最後の夏はじめて如意団の募集に応じて円覚寺の大接心に参加し、居士林で十日間を過した。当時のひたむきの気持と若さのためか、毎日三、四時間ほどしか眠る暇のないような生活も格別の苦痛とも覚えなかったが、今一枚破れそうで破れない壁は厚く、結局十日間の接心を終えて元の木阿弥のような気持で戻ってきたものだった。 当時の老師のお名前も、どんな提唱や講議を受けたかも、さっばり忘れてしまったが、中日頃に雲水頭に呼びだされ、老師の元に相見を受ける作法を教えられたうえ、真夜の三時頃、老杉の道を星を仰ぎながら、老師の庵室に参じ、三拝九拝の上「父母未生以前」の公案を授けられた。それから二、三回老師の下に相見を受けに参じたが、何時も「お前の言うことは頭で考えたことだ」と一喝されて引きさがってきた。わたしは漱石の「門」の主人公さながらに迷い多き心のまま、山門をくぐって横須賀線に乗って帰京したのであった。 心は満されないまま数日を送ったが、ある日街を歩いているとき、ふっと「悟りなどと遠くに求めても詮ないことではないか。朝起きて顔を洗い、飯を食べて、排泄もし、一日を過ごし、夜は眠り、これを生きている限り繰り返せばよいのだ」と思うと急に心が軽くなったような気持になった。 今にして思えば、日常の常識や知覚を通してしか見えない心の深層に到達することが、悟りであり、そうなって始めて生も死も超越することができるのだろうと一応理解のうえでは考えられるが、なかなかわれわれ凡人はすぐに垢がたまって、よりが戻り、そうそう澄み切った状態になれるものではないのだが、当時は本当に何か一つの境地に到達したような気持になって、足も軽くなったように覚えたものであった。 今ひとたび精神の昂揚を覚えたのは軍隊生活の末期にあった。わたし達の部隊は北スマトラで殆ど戦うこともなく終戦を迎えたが、その後約一年半この地に足止めを余儀なくされた。この間にいわゆるインドネシア独立戦争が勃発したが、進駐軍である英蘭軍はメダン周辺の一部を占領するにとどまり、われわれが戦時中の配備とほぼ同じ状態で北辺の地の警備に当っていた。 独立運動は日増しに狂躁の度合を高め、ついにわれわれは小さな港町に雲霞のような多勢に包囲されて二ヶ月余り籠城生活を送っていた。局地的な暴発はだんだんエスカレートし、ついに彼等と勝味のない戦いを交えるか、彼等の要求どおり「日本が育てた独立運動のために」兵器を引き渡すかの選択を迫られる局面に追込まれた。この期に及んでも「菊のご紋章のある兵器を渡すより玉砕しても頑張るべきだ。」という意見を変えない将校も何人かいたが、戦争が終った以上一人でも多く、一日も早く部下を内地に送り還すことこそが指揮官の最大の任務だというわれわれ予備将校の主張が通って、無血武装解除という日を迎えるにいたったのであった。 ところが、兵器引渡直後、進駐軍ならびに日本軍司令部からはわれわれを叛乱軍とみなして攻撃してくるという無電が送られてきた。その結果なかには部下を率いて集団逃亡をする指揮官も出たり、いろいろ曲折はあったが、こうなった以上われわれ将校は攻撃軍が攻めてきたら、それぞれ自決して恭順の実を示し、下士官・兵を何とか無事に引渡して帰還させようということに決った。ところがさて自決しようにも拳銃はじめ武器はすべて現地人に奪われてしまったので、最後にそういうことのために秘かに残した手投弾を一発ずつ分配して、自決用として毎晩枕元に置いて寝ることになった。この結末は幸いにも、ある夜半海上から五十余隻の上陸用舟艇の一斉到着によって救出され幕がおろされたが、自決の決意を固めてからの数日は不思議に心が安らかになり、、何の迷いも感じない静かな日日を送ったのを覚えている。 戦後の焼跡生活の時期食うだけの生活に追われても何も考える余裕のなかった時代もあったが、今日のような豊かな生活に馴れてしまうと、このような極限状態の中の心の緊張と安らぎは遠い遠いものに思えてくる。あるいは低い精神的な次元の生活に馴れ切って、次第に汚れやゴミが集積してしまっているのだろうか。 今静かに省みると、まことに懐しい人生の一駒であった。 亡友のこと この頃自分が年老いてきたという思いとともに、しきりに想いだされるのは亡友のことである。今彼が生きていてくれたらどんなに楽しいことだろう。これからの老境を一緒に生きて語り合うことができたらどんなに嬉しいことだろうと、しみじみ思われることである。 出合資文君のこと 彼は自分の情熱と理想を追い続け、波瀾と曲折に富んだ半生を送った後、最後に東海大学の教授に迎えられ、漸く静かな学究の道(もっとも彼にとっての学究は静かではなかったかも知れないが)を選ぶとともに、極く普通の家庭の安らぎを見出して、第二の人生を歩みだした途端、突如として、老いた母君をはじめ最愛の家庭を残したまま、五十代半ばにも達しない人生を終えてしまった。 彼の人生はその生い立ちから多彩な変化に富んだ道であった。彼の生家は鳥取県東伯郡の山村にある大地主であったが、父君が彼に劣らぬ情熱家であったようで、いわゆる大正デモクラシーの渦中、小作人に農地開放を行ない、一家を挙げて裸一貫のまま横浜に移り住むこととなった。詳しいことは聞き洩らしたが、父君はいろいろな事業を始めたり、失敗したり、時には廃品回収のようなこともやられて、親子で大八車を押したこともあった由、彼は新聞やら牛乳配達やらもやって、小学校から神奈川県立商工実習学校を卒えた。 幼時から彼は社会に対する情熱と貧しい人々に対する骨肉のような愛情を自然と身につけて生長したのである。商工実習学校卒業後、土地柄一時外国人の会社に職を得たが、昭和初期の在日外国人の横柄な態度に我慢ができず、外人専用のトイレに小便をばら撒いた挙句、そこから飛び出し、横浜高商に入学してきた。 わたしとの出合いはここで始まった訳であるが、わたしから見れば年齢も数歳上で、変化に富んだ人生体験も経てきた上、当時すでにマルクスやフロイトにも心を傾け、わたしのようなボンボン育ちの新入生とは違って、すでに一パシの大人の風格を具えていた。彼が情熱をもって説く理論や主張に、わたしは到底ついて行けないと思ったこともしばしばであった。 しかし彼が当時の社会主義者ないし運動家と本質的に異なったところは、彼の根底は深い人間愛に発していたことであった。当時でも今日でもそうかも知れないが、この種の人々の出発点が、社会的不公正に対する憤りや、権力に対する憎悪である場合が少くないが、彼の場合その根底にあるものは、社会と人間に対する深い愛情であった。彼は自分自身が経済的には恵まれない学生生活を送ったにもかかわらず、夜学の教師をしていたある日、寒空に震えている生徒に自分の一着しかないオーバーを快く与えてやったことも忘れられない想い出であった。 彼は自分の社会に対する情熱を弁護士となって展開する望みを持っていたが、彼の情熱は司法試験という一つのことに結集するには余りにも広く、不幸にしてこの望みを達成することはできなかった。戦後もさまざまな道を歩いたが、最後に当時としてはまだ数少なかった中小企業診断士として、零細企業の人々に親身の手を差しのべることによって若い頃の望みを達成することになったが、同時に自分自身にとっても現実を視る眼を堀り下げて行ったように思う。 彼はこよなく酒を愛したが、その飲み方も人を愛し、人生を愛する心から発したような飲み方であった。わたしは学生時代彼に誘われて伊勢崎町裏の安酒屋で焼酎をはじめて飲まされたこと、戦地へ赴任の途次シンガポールで彼と再会し、屋台店をハシゴしたうえ、安ホテルで彼と一夜を共にしたことを、昨日の事のように想いだす。 晩年彼は自動車の運転を習い、母上を鳥取の墓参にお乗せして、親孝行をしたが、あとから考えるとこの鳥取行は死の何日か前であっただけに、長距離の強行軍が彼の死期を早めた一原因であったかも知れない。 東海大学教授に就任して約半年、平穏な家庭生活の安らぎを漸く得て、これからという矢先、彼は逝ってしまった。月並みな人生を送ってきたわたしには、彼の生き方は余りにも羨しく、また異質な友の一人として絶えず何か教えられるものを持っていた。彼の死後十数年を経た今日でも、ポッカリ穴があいたような思いがしてならない。 太田一雄君のこと 十二月クラブの会員で彼についての想い出を持っている人は少いかも知れない。それもその筈で彼は学窓を出たまま二十六歳の若さで南方で散華してしまったのだから。 彼との出会いもまた横浜高商であった。彼は名古屋の在の出身で愛知一中を卒業して入学してきた。その頃のわたし達は東京組といって、東京の中学、商業を卒業して入学し、東京から横須賀線で横浜まで通学していた仲間が殆どで、地方から出てきて寮生活をしていた連中とも、また地元、神奈川県の出身で自宅通学をしていた神奈川組とも、一風変ったグループを形成していた。しかも彼は三年間柔道に打込み、横浜での三年間は余り深い交際をすることもなく過したのであったが、一緒に一橋に進学するということから、次第に親しくなり、国立での三年間はゼミも一緒ではなかったのだが、何時の間にか忘れ難い友人の一人となっていた。 彼の外貌は柔道部員らしく、大きな上背とガッシリした骨格で、都会育ちのわたし達とは異って一見剛直な風格を具えていたが、彼は元来母一人、子一人の家庭で育ち、心の優しい淋しがり屋であった。熱血漢でありながら、一面静かな性格で、詩を好みロマンチックな小説を愛した。彼とはしばしば誘い合って、当時流行のドイツ映画やフランス映画を見に通ったり、またしばしば小平から村山方面にあるいは多摩川まで且つ歩き且つ語った。 彼と最後に会ったのは昭和十七年の一月末、わたしが入営のため九州の任地から帰京の途次名古屋で途中下車をして、短い時間同地の料理屋で飲み合った時であった。彼は一人息子のため、気が進まないままに、母君や親類の強い希望で入営前に結婚することになった些細を淋しそうに語った。その折の奥さんと一緒に生活したのは僅か一週間、名古屋の部隊に入営、予備士官学校卒業後、ニューギニアからガダルカナルに転進した由であった。わたしは終戦後南方から復員して、彼の死を知ったが、ご遺族との音信は絶えてない。 数年前十二月クラブの第一回慰霊祭実施にあたり、彼の本籍地の役場に問い合せたが、詳しいことは何も知ることができなかった。こうして三十年も経っても、何処かその辺りに彼がいて微笑んでいるような、温もりのようなものが感じられてならない。 栖原俊蔵君のこと 栖原俊蔵君は十二月クラブの会員ではない。彼はわたし達より一年遅れて昭和十七年九月に一橋を卒業したが、彼は府立一商、横浜商高、一橋とずうっとわたしより一年後のクラスで、全くわたしと同じ道を歩き、卒業後わたしは三井鉱山に入社、彼は三井化学に職を得た。今日まで彼が生きていたら、戦後の三十年を再びお互いに身近かな道を歩み、更に親しい交りができたことと思うのに、惜しいことに彼は卒業後間もなく陸軍に入隊し、二十数歳の若さで戦死してしまった。 彼も母一人、子一人の家庭で育ったが、都会育ちらしい明るさと人懐つこさをもっていた。それでいて何時でも落着いた、静かなたたずまいを感じさせるような人柄であった。わたしの家は本郷の湯島、彼の家は上富士前で近かったため、しばしばお互いに往き来した。わたしとは性格的にはずい分違うのだが、妙にうまが合って、お互いの部屋でよく人生のこと、宗教やら哲学のことを語り合い、赤電車に乗って帰ることもしばしばであった。 わたしが謡曲を習ったのも、何でも物好きのオッチョコチョイからであったが、彼もわたしの後を追って横浜高商の謡曲部に入部してきた。彼には人柄からいって謡曲の雰囲気が身についたようなところがあり、地味な謡いぶりだったが、間もなく一つの風格のようなものを感じさせた。 また毎月月初めの五日間、湯島の麟昌院の暁天坐禅会に一緒に参加した。久留米絣にセルの袴といういでたちで朴歯の下駄を鳴らして、末だ星が残る暁天を寺に通ってくる彼の姿が、今でもありありと目に浮んでくる。 わたしが軍隊に行く直前、彼はわたしの家にきて、蔵書の整理を手伝ってくれた。わたしの家にはコンクリートの倉庫があったが、湿気るというので、わざわざ近所に住む姉夫婦の家にリヤカーで運び、いくつかのリンゴ箱に整理して、目録まで作ってくれた。この家が後に戦災で焼けてしまったので、せっかく彼が苦労して整理してくれた書物や、若い頃書きためた日記等も一切焼失してしまったが、丹精こめて整理してくれた彼もついに戦争から戻って来なかった。 復員後わたしは直ちに再び九州に赴任し、八年間の焼跡時代を彼の地で過したため、彼の母上のことを気にしながらも、ついにお訪ねして、彼の戦死までの動静を伺ったり、お慰さめする機会を逸したまま今日にいたってしまった。彼と過した楽しかった日日の想い出は今も活き活きとわたしの中に生き続けている。 |
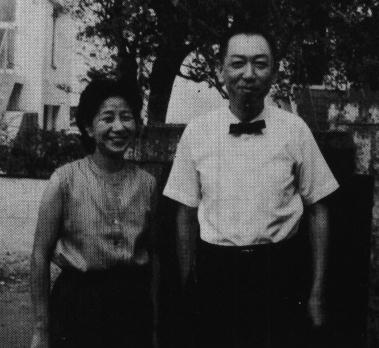 |
|
卒業25周年記念アルバムより |