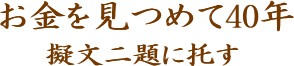
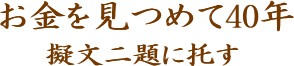 |
7組 西川 元彦 |
お金を見詰めて、といっても金縁・金運は全くありません。しかし、お金の本山の日本銀行で貨幣にまつわる現実と人生を凝視し続けてきたのです。顧問としてまだ続いていますから、日銀創立以来の長期在勤記録を樹立しないとも限りません。
それから、最近数年は大学でもお金の講議をし続けています。ゼミの恩師中山伊知郎先生が原論を講じたあの二十一番教室においてなのです。今は大講座制ですので、私も何と原論担当教官のわけです。中山先生の一周忌も過ぎましたが、晩年の先生から「お金原論」の遺言を直かに承けたまわったつもりでをります。自惚れでも何んでも、そういう心意気を持ち続けたいのです。
しかし、お金という代物は難物です。純粋理論で快刀乱麻を断っても、なお妖怪を切り払ったとはいえません。一方では左右田さんやジンメルの貨幣哲学に思いを馳せたくなりますし、他方で現実の貨幣体験は雲の如く多彩かつ異様を極めます。だからまだ道半ばにすぎません。
中山先生は「学問は一生の事」といわれましたが、私の旅路は、若し先生の年まで生きれば、「お金を見つめて六十年」ということになるわけです。そんな心境と今の境涯を託したものが次の「擬文二題」です。
一つはバイブルの「初めに言葉ありき」を、二つは陶淵明の「悠然見南山」をなぞった替え歌なのです。戯文でないよう念じ、在天の霊にひざまずくものであります。(第一題) ヨハネ伝福音喜に擬す○ はじめに貨幣ありき。
○ 貨幣は神と共にあった。目に見えない理念であった。そして神の世界に止まっていた。
○ しかし、貨幣は人と人との関係に、次第に姿を現わすようになっていく。
○ 市場経済の営みとして出来てきたものはみな、貨幣の力と業によらないものはなかった。
○ そして、この貨幣には命と心があった。この命は、経済を営む人々を導く光なのであった。
○ この光は、闇のような経済世界に輝きつづげている。そして闇も闇のままではなくなっていく。
以 上右を読んで本当に替え歌かなと思う方は、同福音書の冒頭と比べてみて頂きたい。貨幣的な用語とゲーテのファウストによる「ことば」の解釈とを嵌め込むと、右のようになるのであります。
読み替えの心はジンメルの哲理です。こういう擬訳を思いついた動機は高橋泰蔵先生の「経済学巡礼記」でした。中山先生は、自分のしのこした仕事、つまり「お金原論」の完成に高橋君だけが取組んでいると述べられたことがあります。両先生に比べれば、私などまだまだ巡礼を続けねばなりません。扨て次です。
(第二題) 陶淵明の酒詩に擬す
○ 書室を結びて尚金座の境に在り。 (結廬在人境)
而も僚人の喧騒に没すること無し。 (而無車馬喧)
○ 人、君に問う。何ぞよく然るかと。 (問君何能爾)
応う。現し世の阿堵を離れ仏性に偏す。 (心遠地自偏)
○ 書を采る。明治なる灯火の下。 (采菊東籬下)
悠然として金銀の根底を見つむ。 (悠然見南山)
○ 酒気、日夕に到りて漸く佳し。 (山気日夕佳)
飛鳥、飛銭相共に天然に還る。 (飛鳥相共還)
○ 斯くの如き中に真相ありと信ず。 (此中有真意)
弁ぜまんと欲し、己に機縁に托す。 (欲弁己忘言)
以 上右は漢学に素養のない私の替え歌に過ぎませんが、心底から湧き出てきたものです。そして、これも泰蔵先生に刺激されての擬作でした。私の今の境地を読み込んでおります。
少し言葉の注釈をしますと、「金座」とは江戸時代の貨幣どころです。そしてその跡に現在の日本銀行が建っております。「阿堵」はお金の旧称で軽侮を含んだ用法であり、「金銀」には敵意が込められます。「仏性」とは悉有仏性のそれであり、私はお金と東西の宗教の関係を探っています。
「飛銭」は昔の飛脚による為替送金のことですが、如何に乱れ飛ぶ阿堵といえども最後は仏性という天然に還るはずと思っているのです。
「明治なる燈火」は、今の私の書室が明治二十九年に建った文化財指定(永久保存)の日銀旧館にあるためです。ドームの真下に位置し、古いマントル・ピースも残っています。また日夕に備え、つまり想を巡らしたあとのために「酒気」も用意されているのです。
「機縁」にはさい啄の意を込めたつもりであり、弁ずるを欲しつつ、時に語り、時に黙すという心境です。中央銀行は鎮守の森の如しという表現がありますが、それが今の私の座している「場」なのです。
誰にも見せない日記のような擬作をふと皆様の目にさらしたくなったのは、編集者の檄文のためでした。活字にする以上はと、少々説明をつけました。
学問は本よりも現実に直面することの中にある、という中山先生のお言葉があります。その学問を皆様と共に「一生の事」としたいと考える此の頃であります。 近況・心境如件。
 |
|
卒業25周年記念アルバムより |