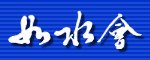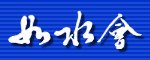|
私の中にすっかり住み着いてしまった四文字「く・に・た・ち」。それは単なる地図上の一地名であるにとどまらず、私にとっては忘れがたいあらゆる心象の原風景と言って憚らぬものである。其処には四季を問わずいつも眩いばかりの光が溢れていた。思うに、あの頃目一杯粋がりながら生きていた私の青春の全てはわずか四星霜と言う束の間の時流の中にあって、いつもあの「く・に・た・ち」とともに息づいていたような気がしてならない。
ただただ一直線に伸びる大学通りの街路樹の緑はどうしてこんなにも輝いているのだろうと何時もいつも目眩めいていた。こぼれるような光をひたすら体一杯に浴びながら、許される限りの歳月を半永久的にここで過ごし通せないものだろうかと謂れのない想いにとりつかれては、本気で万年学生を夢見ていた他愛無い憧憬が今となってはひどく懐かしい。
「おい、お前卒業出来そうか?」友人の卒爾で不躾なそんな言葉に一体どんな意味があるのだろうなどと考え込んでは、むしろそれは一種の邪念に近い思い込みに過ぎなかったのだが、そもそも訳などあるはずもないと納得しては、とにかく「く・に・た・ち」の空気を思いっきり呼吸することだけで体中が至福に満たされていく日々であった。
思えば大学などどうでもよかったのだと思っている。ふと気が付けば18歳の春まだ浅い季節にさしたる気持ちの拠り所もなく「く・に・た・ち」の地にまるで天から舞い降ちるようにして降り立ったのは決して偶然でも必然でもなかった。それは他ならず単なる受験のための所作に過ぎなかった。中学から6年間も学び舎をともにして来た多くの学友達は皆、聊かの逡巡もなく屯して駒場へ向かった。
幸いなことに言わばハイブレーン軍団とも言える彼ら集団と行動をともにするには私は聊か力量が十分ではなかった。そのことは別にどうと言うこともないありきたりの現実であり、受け容れられないと言うより私の気持ちの中ではむしろ望むところとも言える人生展開であるとの強い思いの方が勝っていた。
加えて、「く・に・た・ち」の空気は恐ろしいほどに柔らかく、夥しい光を含みながら私をいきなり包み込んだ。一体この空間は何なのだろうと図らずもたじろいだ。最早逃げられないと観念するのに然程の時間はかからないだろうと予想することはいとも易しいことであった。それからと言うもの、私はまるであの三島由紀夫の「金閣寺」の世界の爛れるような美文に耽溺するかの如き日々の中でその流れにひたすら身を任すことの他に術を知らなかった。「く・に・た・ち」は間違いなく文学に相応しい佇まいをもって私に迎合した。
そして故もなくもケインジアンへと傾かなければならない必然性への肯定の思いを確実に萎えさせて行ったのだが、Sゼミは名うての厳しさであった。ただ只管、義務感に駆られて提出したレポートが返って来る度に、その末尾にはいつも決まり切って、判で押したように「君には知的反応と言うものはないのか・・・」と朱色のペンで書かれていた。ポエティカルなリテラシィには人知れず聊か尊大な自負心があったが、私の本来の学業であらねばならないエコノミックスの学域においては、およそ踏み込みがたい世界観への程遠い距離感と度し難い力量不足を判然とした思いで実感していた。
そして、まるでたゆたうような不思議な量感に満ち満ちた「く・に・た・ち」と言う空間の中でひたすら押し流されて行く日々に無類の快感すら覚えていた。そもそもこの世のあだ花的生業(なりわい)としか思えない「作家」などと言うもっともらしい世過ぎ身過ぎの手法が当然のごとく所在し得ることの現し世の不思議さに闇雲に抗い、その一方では毎年着実に文壇に登壇する芥川賞や直木賞の受賞作家の作品を読み耽っては、彼らの底知れぬ文才の凄まじさにただひたすら圧倒されては羨望を感じつつ、身じろぎすら出来ない日々を重ねることで自虐的な快さを無抵抗に受け容れていた様な気がする。
「シラスの台地に白雨であった。それは幾つもの筋となって地を這い、ひとかけらになっても生き長らえていた荒地野菊らの儚い一生は押し流されてしまった。物憂い午後。決まって襲われる僕のアンニュイの感。今日も一人、キャンバスに向かって無造作に黄色い花を描いていたが、人と光が交錯する夏の盛りは余りにも眩しすぎる・・・」
このくだりは13歳の夏に思い切り背伸びしながら、気取った言い回しで記した稚拙なエッセィの書き出し部分である。信じられないことだが、その情景描写を繰り返し、そしてまた繰り返し読み返していると、不思議な自己陶酔がとめどもなく襲って来る感覚をどうしても抑えることが出来なかった愚かな自分がこの上もなく恥ずかしい・・・と言うよりもむしろ青く幼いと気づかせてくれたのもその後の「く・に・た・ち」に他ならなかったことを忘れない。
そして、折に触れては読み学ぶことを強いられたマックスウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」などと言う難解極まりない思想書に傾倒するよりも、むしろ文壇をはるかに飛翔した天才・三島由紀夫の圧倒的な「豊饒の海」に逆らうことなく飲み込まれてしまう方がどれほど望ましいことか・・・などと言う不埒な思い上がりを何の躊躇も無く正当化して止まない自己を冷ややかに自視し続けていたのであった。
要するに、私にとって「く・に・た・ち」は経済学の世界に程遠く、文学の世界に限りなく親近感のある空間をなしていたように思えてならないのだ。
そして、ともかくも4年の歳月は確実に流れ、私は「く・に・た・ち」を去りがたいと言う思いを踏み捨てにしながら、約束のない将来における「く・に・た・ち」再訪の機会などおよそ覚束ないことだと諦観しつつ其処を後にしたのだ。
あれから40年足らず、今、私から「く・に・た・ち」はとても遠い。遥か遠景の中の「く・に・た・ち」。それはまるでセゴビアの「アランブラ宮殿の想い出」におけるトレモロの寂しさのようでもあり、あのモーツアルトの「魔笛の主題による変奏曲」における何か哀しげな曲想をおびてやまないギターの名曲の揺さぶるような切なさが私の心底に居座って動こうとしない。いずれ遠からぬ日に何の束縛もない全くの自己世界の中で、「く・に・た・ち」を思いっきり彷徨してみたい衝動をいかんとも抑えがたく思っている今日この頃である。
|