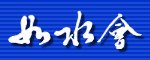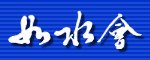先回の國武兄の格調高いエッセーからかなり落ちる話で恥じ入るが、看過しえないもう1つの格差にふれてみたい。
コンピューターやワープロなるものが登場した1980年頃から、勤め先の会社では英文、和文のタイプや計算は自分でやるという建前になった。省力化、機械化の号令が鳴った。1990年代に入り、事務はラップトップパソコンでやるのが当たり前になった。ところが筆者はその頃、花の次長になっており、必要な書類、資料はすべてまわりの女子社員がこぼれんばかりの笑顔で作ってくれた。その笑顔は「次長にこんな仕事をやらせるわけにいきません」という癒しと、「貴方にパソコンの使い方を教えるよりも自分でやる方が速い」という皮肉を含んでいるように、ひがみっぽい次長には映った。
筆者は56才のときに何を勘違いしたのか、会社をやめて国立大学の教員に転職した。 入学して与えられた研究室の鍵をあけると、事務方が手配してくれた新品のデスクトップパソコンが机の上に鎮座していた。恐る恐るカタログをのぞくと、初期設定とかいう手続きをしないと動かないらしいことに気づいた。額に脂汗がにじんだ。パソコンを動かしてくれる会社の女子社員の笑顔がつぎつぎと走馬灯のように浮かんでは消えた。 あとで知ったことだが、大学というところではどんなに偉い教授でも書類作りやコピーとりなどをすべて自分でやるルールがあって(門下生の大学院生をうまく使うのがコツにせよ)、わが研究室は笑顔の女子社員とは無縁のパソコンアレルギー独房と化した。
人類史上特筆すべきデジタル進化の時代はちょうどわれわれが中高年にさしかかる頃に来た。蒸気機関や電気の発明を上回る、デジタルによるグローバルな産業・生活革命が起きたと言えよう。身近なところでは携帯電話は人々の生活様式を劇的に変化させた。 われわれの存命中に、世界中の人々と携帯テレビ電話できる日が来るのだろう。
ところでそもそも平均的オジサン(あるいはオバサン)にとりパソコン、携帯電話、デジカメなどの設定は容易だろうか?その機能の何%を利用できているのであろうか? パソコンが一度いうことをきかなくなるとほとんどの人がお手上げではないだろうか? テレビでは、地上アナログ放送と前からあるケーブルテレビ、スカパーなどに加え、地上、BS、CSの各デジタル放送が普及して、テレビとデッキのリモコン操作がややこしくなった。地上放送とBS、CS電波の違いをどれだけのオジサンがご存知であろうか? リモコンを操作して自分の見たい番組を選べる老人が何%おられるだろうか?
レコードやウォークマンはテープ、CD、MD、メモリー、HDDと変化してきた。まもなくDVD映像はブルーレイとHD-DVDになるらしいが、またもやメーカーは規格主導権争いをしている。いまのDVDソフトを使えるという確証をえない限り、ソフトを貯める気や次世代DVD録画器を買う気にはならない。
筆者の知人では携帯電話やE-メイルを使ってない方がおられる。固定電話以外では接触されたくないという理由かと思われるが、果たして「邪魔」という理由の裏には、「使い勝手が悪い」という意味も込められているのではなかろうか?
メーカーはあらゆる電気機器にこれでもかこれでもかと機能をてんこ盛りにして新機種を売り出してくる。パソコンやデジカメは半年ごとのモデルチェンジだ。デジタルビジネスは使い手の利便性から遠く離れた空間で動いているかのようだ。家庭内の電気器具がLANでつながる時代が来ると宣伝される一方、「買いたくない人は買わなくてよい、使えない人は使わなくてよい」と消費者疎外をされているかのようだ。
さらにもっと驚くことにはデジタル機器についている分厚い取扱い説明書(以下取説と略す)はオジサンには理解できない部分が多いということだ。どうやら日本語文法が怪しい部分すらある。最初の「これだけは知っておこう」ページや最後の「困ったときは」のページを読むが、それでも断片的にしか分からない。取説とは業界人による業界人のためのテキストなのだろうか?
どこのメーカーにもインフォメーション電話サービスがあり、分からないときや動かないとき、電話するが、ほとんど回線が混んでおり、つながらない。デジタル用語辞書なども買ってみたが、その辞書の記述がまた分からない。挙句の果て教えを乞うた知人の彼(または彼女)はにこやかに説明してくださるが、「これだけ説明したのにまだ分からないの」と無言で言われているように思えて、自分は適当に引けてしまう。
以上のような現象は消費財ハードに関する話だが、ソフトの内容やITインフラとなるとさらに知識がない。分からないということは機器の便利さを越えてストレスにすらなる。こんな愚痴を言うと「分かってないのは君だけだよ、パソコン教室に行くといいよ」「神経質になるな、君にとってのデジタル機器はそれでよいのだ」「デジタル商品はあらゆる人のあらゆる使用法に対応しているので、分からなければ専門家に聞くしかないよ」などとお叱りを受けるだろうが、小生なりの論点をまとめると;
1)たしかにデジタル機器はある程度使えた方が便利である。より多くの人々がデジタルに親しめば社会の効率は上がる。一方、デジタルの知識量、習熟度は一般的に育った時代によると思われ、老齢な方ほど激しいデジタルデバイド(格差)を自己解決項目として放置するのは好ましいことではない。
2)平均的な人に分かりやすい、ストレスの少ないデジタル機器であるべきだ。製造・販売市場が競争のあまり多機能・高機能の製品のみに特化しつつモデルチェンジを繰り返し、なおかつ消費者との大きな接点である取説の日本語すら不明瞭であったり、電話サービスが応答しないのは、片手落ちだ。
3)小中高校で情報通信の教育が叫ばれてからかなりの年月がたつ。わが国のデジタル利用による競争力はOECD諸国などに比べ優位と言えるのであろうか? 携帯電話は手品のように使えるのに、インターネットの検索すら下手な若者、またはその根気のない若者がかなりいるのだ。2−3万円する携帯電話やゲーム機を買う財力はあっても教科書を買わない学生がいるのだ。
4)人類が20世紀末から浴したデジタルの恩恵は計り知れない。わが国の技術開発者に深い敬意を払うものである。優れた技術はより広範な人々に利用されてこそ報われる。デジタルリテラシーを高めるにはハード・ソフト両面にわたり、人々の「知」と「経験」の裾野を広げる必要がある。そういった努力を供給サイドでもしていただきたいというささやかな願いを本文にこめてみた。 |