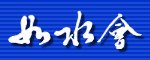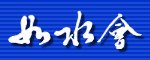今年は、大学卒業40周年である。振り返ると、世の情況は大きく変わったものだ。
私は、大学では法学部、行政法のゼミだった。当時我々が習った行政法は、国や地方公共団体が国民より優位に立っていて、権力遂行の道具を提供する「官僚のための法学」のようなものであったと思う。しかし、その後の外圧や不況の中で民営化や規制緩和などの路線が打ち出され、90年代には、行政手続法や情報公開法が制定され、そして現在では、小さな政府だ、地方分権だ、そして教育改革だとか、行革の嵐、行政システムやお役人の姿勢も変化を促されざるを得ず、また、お堅い裁判官が新判例を出すなど、行政法は様変わりとなったのである。
刑事法にいたっては、もっと激しい。戦後の刑法理論は、「戦前の国家主義的・権威主義的刑法理論への反省」から始まっているのだが、したがって、学説はすべからく判例と対立していたかのごとくである。判例を批判するのが学生の本分だったのである。それが今はどうか。刑事システムへの要請は、単に刑事法の不当な運用から国民を守ることだけにあるのではなく、処罰すべき行為を速やかに処罰し犯罪を防止することにより国民の利益を守る点にあるとされるようになっている。私は、仕事柄ずっとそのように考えてきたが。今では、刑法学者の仕事は、判例をいかにうまく説明するかというようなことになってきているようにも思われる。
そして平成13年には司法制度改革審議会から意見書が提出された。憲法の権威、京都大学名誉教授佐藤幸治先生が中心となってまとめられ、かなりの力作となっている。そこでは、民法等の編纂から100年、日本が辿ってきた近代化の歴史を省察しつつ、21世紀のわが国で、「法の精神が血肉と化し、個人の尊重(憲法13条)と国民主権(前文、1条)が真の意味で実現されるために何が必要とされているか。」を根本的課題として設定するとしている。この意見書が日本の近代化や社会構造論まで射程に入れている点は、興味深い。この根本課題は、明治以降、法律制度も含めて激しい勢いで先進文明を取り入れ、とりあえずは近代化してきた日本の悩みにつながっている。
民法のヨーロッパからのわが国への導入は、この点について、一つの具体的素材を提供する。詳細は省くが、当時もっとも優れた民法典とされていたフランス民法典を日本に伝えるため、日本政府から招聘されてはるばるやってきたパリ大学教授ボワソナードが財産法部分を起草し、日本人委員が起草した身分法部分(この部分については、旧慣があるためボワソナードには委託されなかった)とあわせて公布された「旧民法」に対する当時の日本社会の反発である。これが、「民法出でて忠孝滅ぶ」などで有名な法典論争である。
「旧民法」によって日本古来の家制度をはじめとするよき伝統が滅んでしまうというのが「延期派」の主張であり、いわばヨーロッパ的な個人主義に対する日本固有の集団主義、またボワソナードの権利主義に対する道徳的な徳義主義、そしてボワソナードが拠り所とする経済自由主義を前提とする契約自由の原則を、「新法典は、社会の経済を攪乱す」と非難した。この論戦は、4年間にわたって続いたが、結局、ボワソナードの努力は報いられなかったのである。明治25年である。
元学長阿部謹也氏によれば、わが国では、「個人」という言葉がインディヴィデュアルの訳語として生まれ、広まって行ったのが明治17年である。丁度この論争の直前ぐらいである。しかし、わが国の個人は、西欧のインディヴィデュアルとは決定的に異なっていたのである。そのような当時の日本社会にヨーロッパでも最も徹底した個人主義の法律を植えつけようとしても木に竹を継ぐようなもの、たとえ草案が法理的には優れたものであっても、反発は、自然な流れであったといえる。そして、改めて日本人委員だけで起草された明治民法が制定され、改正を経つつ現在まで続いている。
このころ、明治初年には、古くから中国の法律制度が輸入されていたが、どこまで事実上施行されたか疑問、むしろ条理により裁判をするようにとの布告がある。そして、明治憲法も施行されたばかり、財産権の保障といっても今と違って法律の範囲内でのもの、当時の延期派の人々には、契約自由の保障など迷惑、それよりも国家に守ってもらったほうがよいというような節も窺える。したがって、家と家族、あるいは人間関係などに関する部分は、旧来のまま置かれ、この論争は、第2次大戦後の新憲法の制定による民法の大改正までお預けとなったのである。その間、日本人は、西欧から輸入された近代的諸制度と旧来のままの家族や地域などの人間関係のはざまでダブルスタンダードを演じてきている。これは日本にとっては、かなり大きな時間のロスであったような気がする。
しかし、戦後は、新憲法の理念に基づき、封建遺制を取り除くということで、旧来の親族、相続編の全面改正が急激になされた。ここでは、アメリカ的な法制度が法典論争(文明論争かもしれないが)もなく導入され、現行制度となっているのである。戦後の社会運動の高揚の中でイデオロギー的議論はあったにしても、このあたりに何か、大きな議論が欠落しており、それが昨今の教育論争などにも反映していると思う。日本人は、戦後封建遺制を取り除いたかもしれないが、それ以上に大切なものを破壊したとも思われる。今後、逆戻りすることなく、文化伝統のよきものを選択して後に引き継ぎ、また新しい価値を付け加えることが大切である。
そこで先ず、(1)現代は、都合の良い理論など待っていてもなにもない。問題状況を具体的に捉え、議論すること。具体的に把握するには、現場に出て行くしかない。体を動かすことである。広く情報を取り、分析、価値判断、選択、実行、確認をする。
それから、(2)社会との関わり合いを持つこと。換言すれば、常に「公共心」を持ち続けたい。すなわち、昨今、人口は都市に集中するとともに個人がバラバラになっている。これでは、日本社会は、活性化しない。少子化が進む今日、一層そう言える。個人は、世間に帰属するのではなく、「社会」と向き合わなければならない。日本社会が、「世間」を脱却した後には、「新しいネットワーク」が人を結ぶ社会でなければならない。それは、生涯学習の会か、環境保護運動か、仕事か、趣味か、社会に向かって打ち込めるものを持ちたい。
そして、(3)情報を共有し、徹底して話し合い、共通する意識を持つそんな組織が沢山できて、相互に自由である、そんな社会が望まれるし、それは法律が作るのでは
なく、みんなの意識が盛り上がったときに出来るのだろう。
|