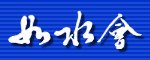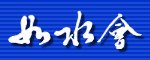振り返ってみると、一橋大学での4年間のバドミントン部に所属していた時期を中心として、バドミントンとのかかわりが私の人生のなかでとりわけ大きな比重を占めています。
今回、リレーエッセイを書かせていただくことになったのを機会に、このテーマで私の思いを綴ってみたいと思います。
私とバドミントンの最初の出会いは愛知・豊橋の時習館高校1年のときにさかのぼります。その前年に赴任していた新任の体育の先生が、大学でバドミントンを本格的にやってきたことから、高校でもバドミントン部を立ち上げて部活動を始めようと生徒を集めていました。私も高校では何かスポーツをやってみたいと思っていましたので、体育館を覗いてみた時にシャトル(羽根)を打たせてもらったのがきっかけでした。1年のときは同好会でしたが、翌年4月に部員10名くらいで正式な運動部として発足しました。当時、愛知県下では運動部として部活動していた高校はわずか数校に過ぎず、試合といえばいつも開催地は名古屋で、早朝の名鉄電車で遠征していました。試合には出ると負けの状態で先生の意気込みだけが先走っていた時代でした。今思うと、先生は、体育教師は副業で、部活動の指導が本業と思うほどに打ち込んでくれましたし、生徒にとっては年齢も近く兄貴のような存在でした。バドミントン以外にもスキーやキャンプにも連れて行ってくれるなど楽しい高校生活に恵まれました。卒業後はこんな部がいつまでも続くのは難しいと思っていましたが、案に相違して順調に発展して今はOB・OGの人数は600名に達しました。奇しくも今年が創部50周年に当たる記念の年になるので、秋には盛大な祝賀会をやろうと、時々帰省しては老若OBが集まって知恵を絞っています。
高校を卒業して首尾よく一橋に入学できたので、クラブ活動には引き続いてバドミントンを選びました。バドミントン部は一橋の運動部のなかでは比較的歴史の新しい部で、そのせいか、雰囲気も上級生・下級生の分け隔てもなく、新入生にとっては馴染みやすかったことは幸いでした。練習は小平の体育館でしたので、当時一橋寮住まいだった私には歩いてすぐの距離であり最高の環境でした。寮の同室の先輩も偶然バドミントン部員でしたので、よく一緒に通いましたが、時にはサボりたいと思っても望みどおりにはゆかず仮病を使ったりしたことを思い出すと赤面の感がします。1日の練習のメニューのスタートは最初が柔軟体操(体の硬い私にはこれがきつかった)、それから玉川上水に沿って短い時は津田塾まで、長い時には朝鮮大学までのランニングでした(これは得意のほうでした)。その後に、シャトルを打っての練習に入ります。ご存じのように、バドミントンのシャトルは傘のような形をしていますので、思い切り打たないとなかなかエンドラインまで届きませんし、飛行スピードは遅いと思うと初速は時速200km以上というスピードがあり敏捷性も要求されます。したがって、コートに入っている時の運動量は予想外に大きく、技術とスタミナの両方が要求されると言えます。通常の練習のほかには春・夏の合宿を富浦や小平で経験しましたが、今も覚えていることは苦しかった練習のことよりも汗臭い異臭のなかで寝起きしたこと、起きているのかと錯覚する大声でカツを入れる寝言、食事は質より量だったこと、ラケットは左利きだったが箸は右手使いと使い分けできて助かったこと、打ち上げコンパの日を指折り数えて過ごしたことなどです。
自分なりに部活動に励んだ成果も徐々に出てきて、3年になった頃から運よくレギュラーの一員に入ることができるようになり、対外試合にも出場の機会に恵まれました。春秋の関東大学リーグ戦、国公立大会、商東戦、三商大戦、三多摩大会などが主な試合でしたが、なかでもリーグ戦で毎期のように東大と、二部の6位と三部の1位で入れ替え戦を戦ったことが印象に残っています。また、新名君と組んだダブルスで三多摩大会を優勝できたことがうれしい思い出です。3年の夏になって、S42年組が部の運営に当たる時期となり、私がキャプテンの役を担うことになりました。30名余の部員をまとめながら、活気ある部の運営と対外試合の成績アップに全力で挑みましたが、そういう時に同期の部員と一緒に活動できたことが何よりの心の支えでした。同期生は、斎藤君(C)、新名君(C)、立石君(D)、椿原君(E)、渋谷君(I)、羽山君(I)、鈴木(彦)君(K)、中村君(K)、鈴木(秋)君(L)、私の10人ですが、今でも同じ釜の飯を食べた仲間として私の大きな財産となっています。斎藤君が社長に就任した時には久しぶりに10人全員が集合して祝宴したのも思い出です。また今年3月には、この中の5人が夫人同伴で雪の五能線と津軽鉄道ストーブ列車の旅を楽しみました。これはクラブを38年卒部の先輩が故郷五所ケ原から請われてUターンし、津軽鉄道の存続に社長として尽力されているのを後輩として応援の気持ちもありました(添付の写真は参加の9人と先輩の澤田夫妻(前列中央)です)。
バドミントン部は昭和27年に9名の先輩が創部して、平成14年には50周年を迎えました。OBの人数も400名に近づく大所帯となり、OB会は「みずとり会」の名称で活発な活動を展開しています。一方、現役では女子部員もリーグ戦に出場するなど私たちの学生の当時とは一変しています。
一橋を卒業して就職した会社にもバドミントン部があったので、入社早々加入しました。部のボス格に元全日本チャンピオンの先輩社員がいたご利益で東京都の予選を突破して、ヨネックスや電電東京などの強豪と一緒に全日本実業団大会に出場できた年もあって、幸運にも恵まれました。会社内の練習も巣鴨で月1回くらいでしたが継続して楽しむことができ、小平にもOB総会など年に1〜2度は訪ねてプレーも楽しむことができました。
会社をリタイアした後は自宅近くでバドミントンが気軽にできるフィットネスクラブを探し当てたので会員となって、ママさんバドミントンの楽しさを味わっています。しかし、1年ほど前から、家裁の調停委員の仕事のウエイトが大きくなってきて練習に通える日が少なくなってきたのが悩みの種になっています。
最近になって嬉しいことの一つが、商東戦や三商大戦がOBのみで開催できるようになり、試合と懇親会が年々賑やかになってきたことです。これは各校のOB会が充実してきたことや団塊の世代が出席しやすい年齢になってきたことが背景にありますが、先行きが楽しみになっています。
バドミントンのメリットとして近年感じていることは、年齢を取っても楽しめるスポーツであるということです。シングルスは無理でも、ダブルスなら70歳まではやれそうですので、これを当面の目標にしています。今の年齢になると正直なところ、プレーの楽しみが半分、仲間との懇親が半分といったところですが、今後は後者の比重が次第に増えてくるでしょう。人間やはり親しい仲間に多く恵まれているほうが楽しく生きて行けると思うし、それが叶うとしたらバドミントンのおかげが大きいと感じています。
今年は北京オリンピックの年、バドミントンも競技種目に加えられています。日本からは人気の女子ダブルス「オグシオ」こと小椋・潮田組を始め、男女とも出場権を得ていますので、世界チャンピオンの中国に一矢を報いてほしいと期待しています。
高校時代のバドミントンとの出会いから始まってちょうど今年が50年、一橋のバドミントン部は5年前に50年を通過しました。S42年会の卒業50周年は9年後ですが、まずは来年3月の卒業42周年大会を元気に迎えたいと願っています。
|