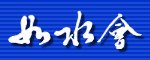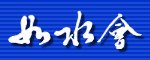齢65歳に至るまで随分旅を重ねたものだと思う。
旅には陸路、空路を、海路を物理的に移動する旅もあれば、読書を通じて過去に歴史を辿る旅、SFで近未来への空想を膨らます旅と数限りないがいずれも推理を、空想を或いは思索を促す極めて楽しいものである。人間には様々な欲があるが、その内の一つ、好奇心から来る知識欲が萎えたら自分も終わりに近いのではないかとさえ思っている。
自分は商社に身を投じたお陰で現役時代は仕事で随分出張の機会にも恵まれた。中には有難くない出張先も無くは無かったが、仕事上の要請である限り忌避は出来ない。イラン・イラク戦争中は両方の国にも訪れた。バグダッドへ、イランからのミサイルが着弾したとの新聞報道が出る最中にも駐在員が頑張って留まっている以上忌避は出来なかった。テヘランの街中を銃を持って闊歩する少年達の姿に見たことも無い中国の嘗ての紅衛兵のイメージを思い浮かべ、背筋が寒くなったこともある。
国民の大部分が極貧だったインド、フィリピン等アジアの経済的に恵まれぬ国では無数の親子の物乞い、或いは花売りに遭遇した。幼子が通行人の哀れを誘い、物乞いで生きて行けるようにと親が敢えて我が子の両脚を切断したとの話を聞かせられたのもボンベイ(現在のムンバイ)長期出張中のことである。このような所では、「憐憫の情」或いは「博愛精神」で個人的に幾ばくかを与えてもより沢山の人間に追い掛けられるだけで何の解決にもならぬと悟ったのは少なからぬショックであった。幸か不幸か更に苛烈な状況のアフリカ大陸には足を踏み入れずに終わったが、国外へ出て見聞したことの重みと、一方外から日本を観る、日本人を観ることの重要さも併せて実感した思いであった。
そんな中の一つの見聞が本エッセーの主題に繋がる。
1995年9月、会社から長期休暇をとって妻を初めてスイスへの旅に連れ出した時のことである。バグダッドへの行き帰りの束の間の過去2回の滞在以来だったが、永世中立で知られる彼の国は、平和憲法を誇りにする我が国と似たようなものと思い込んでいた自分にショックを与えたのは、旅行中に1、国民皆兵制の重武装国家、2、家を新築する時は核シェルター設置が義務付けられる、の2点を知った時のことである。時移り、昨年STCの仲間とスイスを旅した時には、この核シェルター設置義務は緩和されたと聞き、「何故?」の思いが頭を過ぎったが、米ソの冷戦終結が産んだ産物であったのだろうか?
真相は知らぬが、自分の母国を彼の国と同列と思い込んでいただけに、余りの両国の意識の格差に愕然とすると同時に日本のあるべき姿に初めて疑念を抱き、以来「安全保障問題」、「日米同盟」というテーマへの関心が急速に高まって行くことになった。自分に問い掛けた疑問を列記すれば立ち所に五指に余るだろうが、最も基本的なポイントは下記の3項である。
1、 自衛隊単独の戦闘能力はどの程度あるのだろうか?
2、 日米安保条約は国家の安全保障上有効な担保として恒久的に存続し得るのだろうか?
3、 日本人は武力で侵略される可能性を排除して掛かってはないだろうか?
残念ながら、1、の項目に付いては全く定かでない。僅かに認識している日米の間には役割分担があるらしいとの概念からすれば、自衛隊は自己完結的な装備をもって防衛に当たるのではなさそうであり、其処には2、の日米安保条約が恒久的な担保として絶対に必要との論理的帰結になる。個人的には「自国の利益最優先」の米国が永遠に日本を庇護して呉れるというのは妄想だと考えているし、この仮説に立てば、「自らを助ける為の能力のある装備を持つ自衛隊にupgradeせねばならない」との方向が見えて来る。
米国は世界各地に軍事拠点を有し、常時戦闘体制に身を晒して居り、各地で米兵の生命が失われている現実があるが、彼等を駆り立てる動機は、決して高邁な「同盟関係のパートナー」を守る為のものでは無かろう。 湾岸戦争でブッシュ・シニアが巨大な戦力を中東に送り込んだのは、1、石油供給源の地域に安定を齎すことであり、2、サダム・フセインから最大の石油産出・輸出国サウジ・アラビアを守る為にあったのは間違いない。経済の血である石油の流れに支障があってはならない、それこそ命綱との思いであったろう。アフガニスタンは言わずと知れた「テロとの戦い」の最前線ということであろう。このように、自国の利害に深刻な影響があると思えば敢然と立ち上がり、戦う事を厭わぬ国、それが米国と自分なりに定義している。
然れば、日本という国は米国にとって是が非でも守り抜かねばならぬ対象足り得るのだろうか? 未だ、自信の持てる回答を導き出せぬが、感じとしては悲観的である。米国は膨張を続ける中国の軍事力、そしてその野心への警戒を隠さぬ一方で、経済面では余りに深く関わっている現実があり、両国の関係がどう動いて行くのか我国としては目の離せぬ所。 米国が足場を日本から中国に移したとの見方があるのも承知であるが、事はそれ程単純でないかも知れぬ。然りとて、米国にとっての日本の存在感が大きく薄れているのも現実でなかろうか。いずれにしても、米ソ冷戦時代、日韓を中・ソに対峙する拠点とした時代から様変わりしてしまったのは紛れも無い事実であり、この間に中国は核兵器を持ち、戦略ミサイルも配備する軍事大国にのし上がり、今では北朝鮮ですら核兵器を保有するに至るというまでに我国を取巻く環境が劇的に変わった現実を目にして尚、我国の政府、政党、マス・メディア、国民の意識に際立った変化が見受けられぬのは奇怪なことだと思っている。
3、 で挙げたポイントは正に其処にある。
「不戦の誓い」とは他国に侵略され武力鎮圧されてもよしとまで徹底した戦争忌避に堕しているのだろうか? 私見では、太平の時代が長く続いたお陰で「平和憲法維持」の故に平和が維持できたと妄信している人も居るように見えるし、理屈抜きで戦争は嫌いとの思いより不安な未来を直視しようとしない人も居るだろう。又、今まで何とかなって来たからこれからも何とかなるだろうとの超楽観主義の人も居るだろう。
只、2人の子供の親であり、1人の孫の祖父である自分としては、彼等が生き続けて行く日本という生活基盤の独立と平和が守られる状態に置いておきたいと切に願うし、その為には何が出来るのだろうかと考える日々である。 年金問題以外にも大小問題発生し、「民意」とか言う動きが先の参院選で民主党に地滑り的な勝利を齎した結果は、「二大政党制のメリット」が出る処か、江戸時代の倒幕運動さながらの民主党の「政局本位」の動きに繋がり国政は停滞、国益喪失に繋がっていると憂慮するのは自分のみでは無かろう。政策面で国民の生活に直結する、医療、年金も重要なテーマなら、「安心して住める国」を維持し続ける為の安全保障のテーマも負けずに最重要テーマの筈である。政治家には高い志と見識で国を牽引して欲しいし、マス・メディアにはポピュリズムに堕することなく、社会の木鐸としての機能を今こそ十二分に発揮して欲しいと願うものである。
「風が吹けば桶屋が儲かる」的な展開となったが、徒然なるままに思いつく処を書き連ねた。至らぬ点に注意、助言を頂ければ幸いである。
|