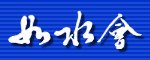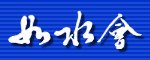大学院修士卒業、毎日新聞記者を経て、28年勤めた野村総研を60歳で定年になった。2005年4月に立教大学経済学部教授になった。それ以降4年、教授生活を楽しんでいる。ものを調べて、分かったことを書いたり、しゃべったりすることが好きな人間には、教授暮らしはよいものである。これまでに9冊本を出した。2009年になって出したのは『環境問題を経済から見る』(亜紀書房)という題にした。野村総研で定年間近になってから、本書き中毒のような状態になり、いまは『オバマが変えるアメリカ経済』という本の原稿を八割方書き終えた。いつも「次はこういう本を書こう」という妄想に耽っているので、これはもはや一種の病気だろうと思っている。
大学で与えられた研究室の快適な静寂、両側の壁いっぱいに取り付けた移動式の書庫。完備したインターネット基盤とサポート。卓上には(カラーコピー、ファックス、電話、プリンター、スキャナーと五役をこなす)小さな複合機。電子ファイル・ソフトを買い、新聞記事や雑誌論文は紙を残さず、メモリー上の仮想書庫に保存するようになった。場所を取っていた新聞スクラップ帳が物理的な形状としてはなくなったので、室内はゆったり使える。
通信販売を利用し、わずか一万円で買ったインドネシア製の藤製ソファーで、ほぼ毎日本当に昼寝をしている。昼寝がこんなに健康によいとは知らなかった。恵まれた環境下で仕事がはかどる。60歳までの36年のサラリーマン生活で6冊本を出したが、教授になってからの4年間で3冊出した。生産性は教授になってからの方が高い計算になる。池袋の校舎は便利なので、記者の方やお役人、企業の方も私のところに足を運んでくださる。
で、教育の方はどうかというと、私学なのでマスプロなのは仕方ないが、出席はアルバイトの大学院生が取ってくれる。近頃は全学生が(教員も)、カラー写真付きで学生番号をバーコードで表示したプラスチック・カードの身分証明書を持たされている。机上に学生カードを置かせ、バイト学生がバーコード・リーダーを持ち、それでスーパーのレジでやるみたいにバーコードに赤外線を当て、ピイピイッと音を立てて読み込んでゆくこれならわれわれの学生時代みたいに声色を変えて代返なんてできないと思って最近まで安心していた。
ところがハイテク時代にも代返はあったのだ。その手口はこうである。友人から学生カードを預かってきた学生が三人掛け机の真ん中に座り、隣の席に友人の学生カードを置く。出席を取りに来たバイト生がカードだけあって本人がいない理由を聞くと、学生は「隣の人はいまトイレに行くといって席を外しました。」と答える。バイト生は「そのうち戻ってくるのだから」とカードのバーコードを読み込む。こうしてカードを友人に託した学生は「出席」扱いになる。
数百人が履修している大教室では、そうでもしなければ出席を取る作業が先に進まない。誰もトイレの中まで行って名前を呼んで出席を確認しないから、代返はバレないはずだ。 それがバレたのは忘れ物である。その学生が出席確認後、自分のと友人のと二枚の学生証を財布にしまい、財布を鞄に入れ、その鞄を机の下の小物入れに置き忘れた。次の授業に来た学生が机の下に鞄があるので、事務局に届けた。事務局で開けてみたら学生証が二枚あった。「忘れ物をしました」といいに来た学生に「なぜ学生証を二枚持っている?」と問いただしたところ、「福島先生の授業で代返しました」と白状したのである。蛇の道はヘビ。サボリ学生と大学事務局の虚々実々の駆け引きは21世紀にも続く。
教授生活を始めて以降、毎年ゼミの学生を連れてヨーロッパへ調査旅行に行くようになった。大教室で私語する学生も、小集団の中では素直で屈託のない若者で、話していると楽しい。零下5度。冬のベルリンで朝6時からホテルの周りをジョッギングするほど、元気溢れる少年少女たちだ。私には早朝ジョッギングにつきあう元気はないが、夕食時はワインの味わいや歴史の話をして20歳前後の若者たちとの会話を楽しんでいる。外国経済の講義でも、12年間の海外生活で見聞したエピソードを入れると、それが好評なようだ。
ロンドン勤務時代に始めた、趣味としての海外旅行で訪問国数はいま87。100になるまで旅行し、その時点で世界史の見方について、もう一冊書こうと思う。楽しい、立教での教授暮らしもあと1年で定年。その後も旅行と執筆、講演を楽しもうともくろんでいるのが、いまの生活である。2009-3-23 記す。
|