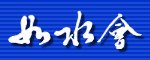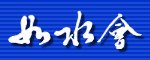|
|
| ■リレーエッセイ |
「農的生活をめざして」 |
| 後藤 守孝(Iクラス) |
誰しも還暦・定年を迎えれば、以降の老齢期をどう過ごそうか考えざるをえない。 自営業に従事していた私に定年はなかったが、そのまま続ける気はなく、新しい道に入ることにした。 選んだのは農的生活だ。
自営業時代から、趣味の園芸としては桁違いな400坪もの畑を耕し、小型管理機や刈払機を使っていたので、技術的な不安はそれほど感じなかった。 私の作る野菜が消費者の求めに適うのか、市場で売れるものが作れるのか、との不安と期待が大きかった。
幸い女房の賛同も得られたが、私の母や義母などは、「なにを、大学を出て百姓に」 と否定的な意見を言っていた。 根底には農業蔑視の考えがあったのだろう。
お世話になった不動産屋には、「奥さんの了解は得られてるんでしょうね!」 と二度も念を押される。 だいたい男は夢を持って田舎に入るが、奥さんは都会との差や環境・人間関係で幻滅を感じ、悪ければ離婚に至るケースもあると言う。無住になった別荘もこの鴨川では目立つ。 ここは一つ、フンドシを締め直さなくっちゃあ!
移住先として安房鴨川を選んだのも、住んでいた我孫子から移った先輩のいたことと、多分お世話になる直売所があるからだった。 その東京近郊で移住先として人気の高い鴨川も、高齢化の進む過疎地であった。 私が鴨川に移住し、別荘族ではないことがわかると、荒れた農地や水田を借りることは簡単にできた。 住んでいた我孫子の市民農園は10坪ほどで年9000円かかる。 農地を借りることは一番の問題だと思っていた。 しかしここでは 「草を刈ってくれるだけでもありがたい」 とか 「耕してくれるならただでいいよ」 という土地がたくさんある。 東北地方や山間地ならこういうこともあろうと考えていたが、東京から百キロ圏でも農村の荒廃は予想以上に進んでいた。 まさか出来ないだろうと予想していた稲作も、移住早々挑戦することができた。 喜んでいいのか、将来のためには悲しむべきことか。
最初に借りた農地は加茂川べりの600坪の放棄地。 この畑にはさんざん苦労させられた。 移住した初めの二年間に三度も水害に見舞われた。 しかも三回とも耕したあとの軟らかい土をもっていかれ、代わりに石や竹、樹木を置いていく。 後片付けをし、粘土土だったのでその都度、川岸や土手に溜まった砂を運び、土壌の改良につとめた。 移住早々の高揚期でもあったので、土木作業もなんとか乗り切れた。 以後水は出ていないが気候のことは予測できず、今は水の害の出ない場所の畑が中心になっている。
我孫子時代も無農薬・無化学肥料で作っていたので、鴨川に来てからも同じスタイルを貫いている。 美味しい野菜はできるのだが、また別の課題も出てきた。 その一つはハタネズミの増加だ。 ケイフンと牛フン中心の肥料は土を肥やす。 と、ミミズが増える。 畑にはいいことじゃん! がミミズがモグラを招き、その穴を伝ってネズミが入り込む。 根物中心にその害は多いときは収穫を半分に減らす。
サツマイモ、ジャガイモ、ニンジン、ダイコン、ラッカセイなど土中の作物はもちろん、辛味のあるネギ、エシャロットや白菜、ソラマメの株元も冬季には食害して枯らす。 かわいい小型ネズミなんだが、今の私には天敵。 ネットで 「不耕起畑はネズミに入られたら致命傷」 との文を読み、作付け前の一度だった耕運を3回にしよく耕し、また友人に勧められてハーブを株間に植えてその臭いでネズミを寄せ付けなくするなど、農薬に頼らない対策に着手したところだ。
もう一つの困ったことは葉物野菜の虫害だ。 私の技術の未熟さや対策の不備から虫類の被害を減らせない。 「虫に食べられるのはうまくて安全な証拠」 と言うけど、そんな野菜は誰も手に取ってくれない。 消費者が野菜を選ぶ基準は、まず見た目。 面食いなのだ。 私の葉物野菜は第一印象で外され、かくて今は自家用のみにしか作っていない。 結果あまり熱も入らず、どうもスキルは低下したようで、満足な葉物を口にしていない。
私はもともと自給自足生活は夢見ていない。 「田舎暮らし」 も目標ではなく、現住所も県道に面したにぎやかな場所だ。 何か所かにある畑へ行くのに便利だし、この車社会の田舎町・鴨川で運転できなくなる今後のことを考えると、「バス停20メートル」 は重要だ。 通りの反対の我が家の南には竹林がせまり、その向こうには水田と嶺岡の山並みを望み、町と田舎が混在している。 こんな現在地での農業中心の生活に入っての楽しみの一つに、庭先でヤマウド、タラノ芽、蕗、セリ、ミツバ、竹の子などが季節の山菜が食卓を飾ることだろう。 しかも友人たちが 「こんなにたくさん!」 と驚くほど多くたんのうできるのが醍醐味だ。 また孫たちも竹林での焼きイモ、畔での花摘みやザリガニ取りなどに興ずるし、初めのうちは畑仕事にも熱心だ。 ありがた迷惑なニンジンなどの洗いや袋詰め、直売所でのシール貼りも手伝ってもらう。 食に対するなんらかの経験となり将来生きてくることを期待して、鴨ジイの頬もゆるむ。
個人としての生活では、生育する野菜に、どういう仕事を今日しようか、来春の作付け計画は? と朝のふとんの中で考えるのは無上の楽しみだ。 植物は生育を止めてくれないから、仕事は無限に出てくる。 生育に遅れないように追いつくのも大変だ。 だから雨の日以外は畑にたつ。
もちろんいのちを播き、育て、収穫し、頂くことも農的生活の最大の楽しみだ。
原発に代表される、無機的な死の世界と真逆な世界がある。 雑草も抜いても油断すれば思わぬところから根を出し、生命をつなごうととする。 道端のあのタンポポも花を摘めば、すぐ綿毛の種子を作ろうとする。 環境の変化への適応が生物の特徴なんだろう。 おかげでこちらはいくつもの農作業に汗を流すことになるが、こんな生命のダイナミズムを畑の一角で見ていられるのも幸せなことだと思う。
少額ながらの年金、女房のパート勤めに支えられての農的生活だが、早く自立=独立自営農民になることが、今の課題だと思う。 これからの日本を考えると自助・自立した生活が大切になりそうな気がする。 財政破綻による戦後の混乱期のような社会が来ないとも限らない。 基本的な生活部分はできるだけ自分でまかなえるようにしておきたい。 設置した太陽光発電も資金回収はむりだが将来的な支えになるかもしれない。 こうしてみると30年は無理だろうが、近い将来となると健康維持が大きな課題になってこようか。
移住して7年。 無理してやってきた農作業で、また加齢により体の節々に痛みを覚える今日この頃だ。 特に私のような多品種・少量生産の畑中心の仕事は、スコップや鍬などを使う肉体労働が多い。 この齢だ、無理はすぐに体に帰ってくる。
実は昨秋ショッキングなことがあった。 サラリーマン時代からの山仲間との菅平・四阿山での下り、私一人膝の痛みで遅れたのだ。 スコップを使う農作業が日ごろ多く、ちょっと痛みを感じていたのが、下りの体重の荷重に耐え切れなかったものらしい。 加齢や運動不足もあろうが、日々の労働での無理がこんな時に出てくるのだろう。 周りのお百姓さんたちは、12時と夕方の時報には必ずさっと仕事を切り上げる。 キリのいい所まで、と私のようには考えない。 農業は長い仕事だ。 翌日やればいい。 先輩農家からも 「疲れたから休むのではなく、疲れないために休め」 と言われた。 ここがまだ農的ライフスタイルになりきれていない私の現況なんだろう。 あと十数年、加齢とのせめぎ合いのなかで、私なりの農的生活をきわめていくことになるのだろう。
|
| 以上 |
クリックすると拡大します |
 |
 |
| 自走式脱穀機ハーベスタを使って |
サトイモ冬囲い |
|
|
|
|
|