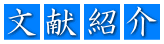
刑事手続法上の「捜査」をめぐる重要テーマを取り上げた論文集。もっとも、取り上げられた論文の多くは初出時のものに補筆されているし(補筆された部分はわかるようになっている)、新たに書き下ろされた論文も含まれている。 Ⅰ.捜索・差押え 第一章では、筆者は、処分を受ける者が現場にいる限りにおいて、令状の呈示が「憲法35条の要求」であるとした上で、呈示の目的を達成するために一定の場合には被処分者による令状の筆写を認めるべきだとする。また令状執行の際の住居主や弁護人の立会いについても検討している。第二章では、捜索差押えの際に為す捜査官の写真撮影について検討されている。撮影態様(権利侵害の態様)に応じて検証令状の要否や違法性を論じる。また救済手段として準抗告の活用を法解釈上認めるべきだとする(他、判例解説)。第三章は憲法35条との関係で生じる盗聴の問題点を論じたうえで、通信盗聴立法の問題点についても立法事実論、濫用防止策、裁判所の要件解釈の弛緩防止策、捜査法全体の均衡という点から検討している。 Ⅱ.逮捕・勾留 第一章では、法198条1項にもとづく出頭の求めに応じない被疑者を逮捕する必要性の問題(とりわけ速度違反などの交通事犯)を検討する。ここで筆者は、不出頭自体は必ずしも逃亡のおそれや証拠隠滅を徴表するものではないとし、逮捕には他の積極的な理由が必要とされるべきだと結論付ける。そして、むしろ不出頭の場合は逮捕せずに公判請求して、裁判所から被告人へ召喚状を発するべきだとする。第二章では、別件逮捕勾留について、判例を三つの類型に整理し、また別件基準説、本件基準説の内容を整理されている。なお本件基準説について、その内実は「捜査官が本件(=余罪)取調べの意図を持っていたことが、別件(=本罪)での逮捕・勾留の適否に影響すると考えること」だとしている。第三章では川出敏裕『別件逮捕・勾留の研究』(東大出版会、1998年)への論評が展開されている。ここでは川出理論の特徴が、別件逮捕勾留の違法性根拠を捜査官の意図や目的ではなく実際に生じた結果に求めるところにあると評する。しかし、取調べを主目的とする拘束を否定する論理が欠如している点を問題として指摘している。第四章では、留置施設法案が、現行法の理解として妥当性のある「本来的留置場所説」の建前を変更するものであり、ひいては憲法34条の趣旨に逆行するものだと評している。その上で、「仮の拘束」としての逮捕の性質に鑑み、被逮捕者の地位の法定し、訴訟手続のための権利の保障の必要性を主張する。第五章では、訴訟法と施設法の関係を「二元主義」的にとらえることへの疑問を示し、「一元主義的な考え方」でとらえることを主張する。その上で、具体例として接見交通権や被疑者取調べについて検討し、憲法に基づく価値判断に合致した未決拘禁の具体的内容を考える必要性を論じている(他、判例解説)。 Ⅲ.被疑者取調べ 第一章では、取調べ受忍義務否定論の具体的な論理的帰結が手続の中でどのようになるかを提示している。例えば、自白の任意性評価の厳格化、弁護人立会い権の一定範囲における保障、接見指定の要件の厳格化など。また取調べの任意処分性ゆえに事件単位説による余罪取調べの規制は論理的に困難であるとし、むしろ別件逮捕勾留の違法性の問題で対処している。ほか、未決拘禁の執行などについても論じられている。第二章では、余罪取調べに関する裁判例を時系列的に分析し、学説を四つに整理・紹介している。そして判例の現況を示し、余罪取調べと別件逮捕等諸問題との関係について分析する。筆者は結論として、本罪についての逮捕勾留自体で余罪取調べが禁止されることは無いものの、そのためには身体拘束の適法性と取調べの非強制性が要求されると主張している。 *Ⅳ.被疑者の弁護人依頼権、Ⅴ.捜査構造論をめぐっての内容は建設中です。 なお本書の書評として、小坂井久「後藤昭著『捜査法の論理』」季刊刑事弁護28号156頁(2001年)参照。 |
 後藤昭
後藤昭