[友視の視は正しくはネへんでなく、示へんです。なお以下の文では敬称を略させていただきます。]
はじめに
今、日経2013年9月8日の「読書」ぺ−ジで福音館書店の松居直による追想を読んでいる。1953年に児童文学者の与田準一と絵本「ビップとちょうちょう」を作った画家の堀文子が、執筆を依頼され「これは個展をやるぐらい、大変なことですね」と語ったというのだ。それで僕は二つの講演を思い出した。昨日9月7日の神奈川近代文学館における画家の司修によるものと、一昨日9月6日の八重洲ブックセンターにおける村松友視によるものである。
司修はこう言っている。「絵本画家希望者は今でこそ多いが、昔は画家のアルバイトとして低く見られており、自分でも食べるために絵本の絵を描いていたから、とくにアンドリュー・ワイエスが30年以上もクリスチーナを描き続けたことに比べ、負い目を感じていた。でも、今振り返ってみると、大切な仕事ということを別として、好きなものを描いてきた、そして一所懸命に画いてきたということに最近気づき、救われる思いがした。」 司の話を聞いて、「同じように絵本画家でもあった日本画家の堀文子は、どのような心境だったろうか?」と思ったのである。そのあとに上記の日経記事を読み、「やはり、本気でやっていたのだな。」と確認できたわけだ。
村松友視の講演は 「『極上の流転 堀文子への旅』刊行記念トークショー」で、僕がこれを聴きに行ったのは二つの期待があったからだ。ひとつは2013年8月25日発行の本書に書かれていないことが聞かれるだろうということ。もうひとつは、本書に図版として含まれていない堀文子の絵をスクリーンに映しての話があるだろうということ。というわけで、この感想文は読後感と講演会で得た情報が混ざったものになっている。
1. 本書の特徴
村松友視による、堀文子というエラン・ヴィタル élan vital(生命の躍動、または躍動する生命)追跡の記録である。これが僕の要約。
序章 + 16章 + 終章から成るが、各章は平均10頁ほど。章の終わり方が「その次は、どうなったのだろう?」と読者の興味をそそるような書き方になっている。これは著者の力量によるところで、一気に読ませる。もちろん、堀文子の人生そのものが、起伏に富んだ「流転」に満ちているからでもある。いや、起伏の伏はないと言ってよい、彼女には「逆境」というものがない。あるいは、「『逆境』が贅沢にお色直しする。」ということだ。いかなる転換点も「極上」のものにしてしまう。旺盛な好奇心のためだろう。堀文子の生き方を、表面上謙虚で内面的に熱い好奇心をもつ著者が追跡する。これ即ち「堀文子への旅」なのだ。
「極上の流転」の「流転」とは、何か? 関東大震災、二・二六事件、第2次大戦を経験したにとどまらない。麹町の良家に生まれ、自然科学者になりたかった少女は女子美日本画科に進み、その因習的な雰囲気になじめず洋画家に友達をみつけ、後に夭折する柴田安子と影響しあい、偶然、徳川義親と知り合い、これも偶然 芸者「露木」と終生の友となり、自立のために家出をする。病弱な学者と結婚し、絵本の絵を描いたりして生計を立てる。夫は結婚後14年で亡くなる。その後、彼女の画業を評価してくれた米人富豪の援助を得てエジプト・ギリシャから欧米をまわる。さらにメキシコに渡り、欧州とは異なる美を見出す。東京を嫌って大磯に移るが、そこにも満足せず、軽井沢にアトリエをもつ。バブル景気の日本に愛想をつかし1987年、単身イタリアにむかう。1995年には、アマゾンとイタリア (再訪) へ、1996年ポルトガル、1998年ヒマラヤとペルー、1999年「ブルーポピー」を求めてヒマラヤへ。動脈瘤が一夜にして治癒。それが微小な細胞のおかげというので、微生物に興味をもち高価な顕微鏡をのぞく。
あまり細かく書くと、本書が売れなくなり営業妨害になるので、以上にとどめる。
本書には、絵の図版はない。わずかに「幻の花 ブルーポピーズ」が表紙に用いられているのみである。作品論・画論もない。第10章までのエラン・ヴィタル追跡の旅の最後に「堀文子作品の鑑定などは思い及ぶべくもない。(中略)しかしこのあたりで、堀文子が手放すことのない美術の肌ざわりについての、何らかの手がかりをまさぐってみなければならなるまいと覚悟して、私はいま大きく息を吸い込んでいるところのである。」と書いているため、読者は画論が出てくるのかな?と思ってしまう。 第11章「作品と人生との連鎖」のはじめでは、たしかに画論に近いことに踏み込んでいるのだが、この章は短く、読者は肩透かしを食うことになる。第12章から再び「生き方」に焦点があてられる。
だが、本書は堀文子という人を扱っているのであり、表題も「極上の流転」であって、「堀文子百科事典」ではないから、図版、作品論が無いことで著者を責めるのは筋違いである。著者は、「絵画を見る目がない」と言っているが、テレビの仕事でオランダの画家ボッシュを取材したり、「最後の晩餐」の取材でミラノへ行ったりしており、絵画が分からないはずはない。ただ、役者、俳優、歌手、スポーツ選手のパフォーマンスを論じるときのように絵画を雄弁に語ることはないと想像できる。これは、謙遜とか含羞とからでなく、誠実さから来てのことだろう。堀文子自身、自分の過去の作品についてあれこれ話すのが好きでない、ということを配慮し、「絵は各々の目で」という画家の考えも尊重しているのだろう。ただ、講演会では、期待通り絵画の一部をスクリ−ンに映して話してもらった。これについては後述する。
2. 村松友視による伝記
松岡正剛は、「村松友視は変なものばかり書く人だ。(中略) 小説のほうではない。(中略)。『私、プロレスの味方です』や『トニー谷、ざんす』や『力道山がいた』、『そして、海老蔵』、『百合子さんは何色』、『雷蔵好み』のほうだ。こういう仕事は、きっと誰かがそのうち書くだろうと思っているのに誰も着手しない人物伝というもので、村松にしかできないものなのである。」と村松による水原弘評伝の読後感で書いている。「村松にしかできない」という点はまさに同感だ。
9月6日の講演会の村松自身の説明によると、「幸田文、武田百合子を書いたのは、彼女たちの没後。堀さんは生きている人です。その意味で書きにくかった。」そうである。
村松友視に画家の評伝が他にあったか僕の記憶にはない。彼の祖父 村松梢風の代表作「本朝画人傳」に触れた松岡正剛は、「大衆文学にはなじまず、あえて考証的趣向文芸ともいうべき領分を拓いた梢風」と言っている。「大衆文学にはなじまず」はともかくとして、「考証的趣向文芸」とは村松友視にも当てはまる。彼も、執拗な文献調査にとどまらず、ジャーナリスト的に「足で」情報・記録を集め、インタヴューをする。 本書でもそうだが、彼の書く評伝には、必ず政治・経済・社会史年表が、必要に応じて挿入される。
東に「本朝画人傳」あれば、西にラスキンの「近代画家論」がある。「近代画家論」が、様式と思想と技術と主題と社会問題をごちゃごちゃ書いているとしたら、「本朝画人傳」は、その点すっきりしており、本書は、絵画そのものの詳説がない分更にすっきりしている。日本に再三愛想をつきることが、堀文子の流転の契機となることに、著者が尊敬と同意の目を注いでいることは、間接的に、著者としては珍しく社会批判をしていると言える。著者も(僕と同じように)資本主義国日本にどっぷりつかっているから、ラスキンのように社会正義を全面的に表出するのは難しいだろうが。
3. 堀文子の絵画について
はずかしいことに、僕は堀文子の絵画を、これまでよく観たことはなかった。今回、InternetのImageで得られるものに目を通してみた。驚くことは、作風が一定していないことだ。画家ピカソが「ooの時代」とよばれるように作風を変えていったことや、作曲家ストラビンスキーが前衛的な作風のあと古典に回帰していったことが想起される。同じ女子美出身の日本画家 片岡球子の役者絵と富士山は一目見れば「あ、片岡球子だ」と分かる。「何を演じても勝新」の勝新太郎みたいだ。堀文子は、その持論「一所不住」「慣れない」を、彼女の描く絵画でも実践している。演じる役で千変万化する市川雷蔵のようだ。
すべての作品について話したらきりがないので、まずは著者が講演会で紹介してくれたものに触れる。柴田安子と影響し合っていた時代の「落下傘を造る少女」は、村松によれば、「これ日本画ですかね?ゴーガンの影響があるそうですが」ということ。

|

|
| (クリックすると拡大写真になります) |
上の「蜘蛛」は「堀文子のリアリズム」を代表する。
堀文子は西洋に行ってから西洋コンプレックスがとれて日本への回帰ができたということだ。これは土田麦僊においてもあてはまるものだったことが「本朝画人傳」で分かる。下の花札「日本の意匠 2012」は堀文子の最近の日本回帰を示す。

|

|
| (クリックすると拡大写真になります) |
堀文子は1965年から3年間「オール読物」の表紙絵を画いており、講演会当日、その36枚から24枚をスクリ−ンで見せていただいた。すべて外国の女性である。いや、魅了されてしまった。村松は「これ、アルバイトの作品じゃないですよね」と言う。格調が高い。僕は、その当時海外の仕事はしていたが、欧州・中近東は行ったことはまだなかった。それを経験した後の今、これらの表紙に描かれた女性たちを鑑賞すると、うなってしまうのだ。上に掲げたのは、そのうちの一枚。
さて、僕は作品論・画論はできないが、堀文子の絵を観て「僕の目で連想」した画家のことを次に書く。「堀文子に影響を与えた画家」かどうかは、僕には判断できない。
「極上の流転」の表紙に使われた「幻の花 ブルーポピー 」伊藤若冲。
以下は講演会では映されなかったものである。
「極微の世界に生きるものたち 2002」ミロ、「八丈島 1950」ルネ・マグリット、「山の思い出 1955」アンリ・ルソー。
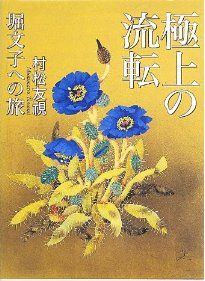
幻の花ブルーポピー |

極微の世界に生きるものたち |

八丈島 |
| (クリックすると拡大写真になります) |

山の思い出 |
最後に、僕が好きな絵を2点、下に示す。
なお2013年11月7日〜27日に 「堀文子展 2013…現在(いま)」が画廊 ナカジマアート( 東京都中央区銀座5-5-9 アベビル3階)で計画されている。ぜひ、鑑賞に行きたいと思う。この拙文で興味を持たれた方々も憶えておいてください。もちろん「極上の流転」を読むこともお忘れなく。
堀文子自身の書いた本もあるが、その中から彼女の言葉を抽出した「堀文子 言葉の花びら」が「極上の流転」終章に集められている。
以上

|

|
| (クリックすると拡大写真になります) |