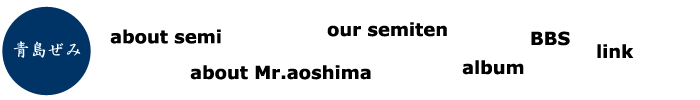
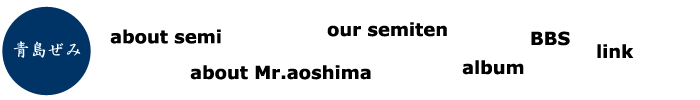
![]()
ここでは私たち青島ゼミがどんなことを勉強して、どんな活動をしているのかについて
紹介していきたいと思います。
新3年生が近いうちに手にすることになる、後期ゼミナール協議会発行のゼミ紹介冊子
に載せるために書いた記事は、こちらです。
どんなゼミ紹介冊子を見ても、名前の順から必ずいちばん最初に登場してくる「青島ゼミ」
そんな青島ゼミで、僕たちが実際にどんなことを勉強しているのか、紹介していきたいと思います。
![]()
青島先生の専門分野はイノベーション・マネージメントですが、僕らが3年で勉強してきたことは
前半が「社会調査法」、後半が「組織論」です。どちらも網羅的な英語文献を輪読し、レジュメ担当の
2〜3名が週1回、発表しています。実際に僕らの読んだ文献は、
□ 「Reserch Methods in Social Relations」(社会科学調査法)
著者:Charles M. Judd, Eliot R. Smith and Louise H. Kidder
□ 「FRIENDLY FIRE -THE ACCIDENTAL SHOOTDOWN OF U.S. BLACKHAWKS OVER NORTHERN IRAQ-」
著者:Scott A. Snook
前者は、2期生のサイトに端的な説明があるので、引用させていただきました。
|
社会科学というのは抽象的な概念で、実際に現実社会において証明するのが本当に難しい。自然科学は合理的な解答が実験から導き出されるのとは対照的。 なので社会科学の組織論・戦略論を学ぶ上で、きちんとした学問として証明するためには何が必要なのか?という方法論をこの本によって学びました。 |
青島ゼミではゼミの導入でいままで読んできた文献で、先生によると新3年生にも使うそうです。
後者は、湾岸戦争時に発生した、米軍による味方機の誤爆を組織論の観点から分析した文献です。
組織論の基礎となる、個人レベル・集団レベル・組織レベルから誤爆を分析しています。
軍隊という組織の話なので、初めの頃は英語で出てくるマニアックな軍事用語と事実確認の部分には
てこずらされましたが、そこを過ぎて分析の段階に入ってしまったら非常におもしろい内容です。
ちなみに、2期生はバーナードの「経営者の役割」(邦訳)という組織論のバイブルを読んでいましたが、
2期生いわく日本語で書かれたもののほうが理解しにくい、とのことでした。必ずしも日本語の文献が
わかりやすいとは限らないです。英語のほうがわかりやすいということは多いです。
![]()
3期生の場合、レジュメ担当者が、自分が担当することになった範囲全体を網羅したレジュメを作ります。
一方で、それ以外の人間はゼミの前日までにゼミのメーリングリストへ簡単なレジュメを提出するという方法を
とりました。この「簡易レジュメ」という方法は正直、しんどい面もありますが、レジュメ担当でなくてもしっかり
範囲を読み、なんとなく自分のひっかかった部分をあらかじめ掴んでおくことができるので、
今にして思うとやってよかったです。4期生がどういう方針でやっていくかは、最初のゼミで青島先生と
ゼミテンとで話して決めることになると思うので、いろいろ意見をだして、ちょうどいい方法を見つけてください。
![]()
夏に勉強した「社会科学調査法」を実践して、自分たちでたてた仮説についてその因果関係を証明してみよう
というプロジェクトが夏休みからはじまります。そして、10月の4年生も含めたゼミ全体での中間発表を通して、
11月末の三商ゼミでの最終発表につっぱしっていく、というなかなか長い作業です。
3期生の場合は、10月の中間発表までは2チームに分かれ、まったく違うテーマで作業を続け、その後より深く
掘り下げられそうなほうに合流するという方法でやりました。
テーマの決定、仮説の決定、実際に街中などで行うアンケートの作成、アンケート取り、統計ソフトの分析など
やるべき課題は多いです。ぼくらが特に苦しんだのは仮説の決定でした。
おもしろく、意外性があって、かつ世の中で因果関係が成り立っていそうな仮説を創ることに、
かなり多くの時間をさかれました。
僕らの場合、多くの人にご迷惑をおかけしながら(本当に申し訳ありませんでした)もんどりうって
最後なんとかゴールをしたという形でした。もちろん2期生はそのようなことはありませんでしたし、
チームの性質によるものですが、ゼミとは別に自分たちで時間を調整して、ミーティングを重ねていく作業は
非常に時間を取られるものです。ゼミへのコミットができる人でないと持たないということは言えます。
能力や知識も大事だけど、それ以上にゼミを大学生活のうえで大きな位置に置けるかどうかが青島ゼミで
勉強をしていううえでは重要だと思います。
三商の話に戻ると、ぼくらのテーマは「TVショッピングの購買行動」でした。
最終発表で使ったパワーポイントのシートがこちらにあるので、興味のあるひとは見てみてください。
![]()
普段のゼミではテキストを輪読し、夏からは平行して三商プロジェクトをやっていくという基本的な形は
それほど変わらないと思います。時間的にきついこともありますが、みんなでチームを作ってかたちに
していくという作業は、一生忘れることない貴重な経験でした。ゼミテン同士の結びつきも急速に強く
なっていき、達成感もひとしおです。
そういうコミットのできるゼミに入りたいなというひとに青島ゼミはおすすめです。
ぜひ、青島ゼミの扉を叩いてみてください!