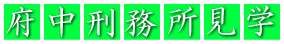
(3)質疑応答
庁舎に戻ってから、冷房の効いた3階で40分ほど質疑応答がなされた。すでにここまでのところで、質疑応答の内容についてもある程度触れてきたが、まだ触れていないこともあるので、私の記憶にある範囲で補足する。
①女性の刑務官はいるのか
受刑者を直接担当する女性刑務官は現在はいない。主に事務の方で女性が若干名働いている。
②受刑者への懲罰にどのようなものがあるのか
生活態度などに問題がある場合、受刑者には懲罰を課す。その種類としては、叱責・運動禁止(5日間)・減食・文書閲読禁止・閉居(最大60日・作業禁止・閲読禁止)がある。懲罰房は普通房と同じつくりである。なお、「保護房」というものもあるが、これは受刑者の自殺防止のための房であり、この房には一切道具は置かれていない。保護房は懲罰としては用いず、自殺防止のためでも収容期限は3日間である。
③受刑者の運動の扱いはどのようなものか
受刑者は、1日40分以内で運動をすることができる。刑務所内にはグラウンドが2面あり、そこでサッカーやテニス、ソフトボールなどをやっている。なお、年1回刑務所内で運動会を行なうほか、サッカー・テニス・ソフトボールなど各種目で大会を開いたりもしている。
④受刑者の意見を汲むような制度はあるのか
年数回の受刑者へのアンケートや、受刑者による刑務官への個人的な申し出から意見を聞き、担当部署の者のところへ意見をまわして話し合いの上、採用の可否を決定している。
⑤職業訓練を認める「適格者」(刑務所発行パンフレットで用いられている語)の基準は何か
健康であり、通常人並みの行為ができる者なら、生活態度の善し悪しを勘案した上で原則として認めている。しかしながら、実際に資格を取れるまで訓練を受けるものは少なく、自動車整備(3級)は年に10名程度、2級ボイラー技士は刑務所内にボイラーが少ないこともあり、年に3~4名にとどまる。資格取得以外の訓練には革工芸・窯業・木工(家具一般)・木材工芸(鎌倉彫り)・木工塗装などを行なっている。
⑥受刑者にみせる新聞・雑誌の内容に規制は加わるのか
刑務所ごとに異なるが、警備・教化との関係を考慮しつつ、新聞・雑誌の内容を規制して記事を削除することはある。わいせつな記事については、一般雑誌程度なら容認している。また、暴力団の抗争など、受刑者の対立・闘争につながり得ると判断されるような記事は、収監されているものに応じて判断する。
主に、以上のような質疑応答があった。
質疑応答の終了を以て、3時間にわたる今回の府中刑務所見学は終了した。もちろん、外に出るときに人数をもう一度確認されたが。外に出たとき、何かホッとした感じがした。以上


|