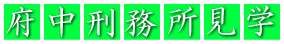
続いて、作業場に向かう。府中刑務所には作業場が実に29もあり、その内容も多彩である。私たちは、その中で金属加工・木工(たんす)・皮製品(靴・鞄)・部品(何の部品かは分からなかった)の作業場をまわる。これらの作業場は各々隣接している。
まず金属加工の作業場に入る。受刑者が黙々と作業をしている。二人の刑務官が監視に当たっていた。受刑者の人達は、我々が入ってきても何の反応もない。我々の存在に気が付かないかのようである。目を合わせることはまずない。むしろ、こちらの方が、ジロジロと作業を見るのが申し訳ないような気持ちがして、落ち着いて見ていられなかった。あっと言う間に通り過ぎた感じがして、何を作っているのか分からなかったというのが、正直なところである。
次に木工製品をつくる作業場である。私もやや落ち着きを取り戻して見ることができた。髪を短くされた受刑者それぞれに持ち場が与えられ、そこには名札が貼られている。概ね単純作業である。部品を機械に置き、部品ができたら機械から外してカゴにいれる。作業場には大体20人ほどいるであろうか。ひたすら沈黙が支配し、説明する刑務官の声と機械の音が響く。
木工製品作業場の中ほどに、優秀作品が法務大臣からの賞状と共に展示されていた。府中刑務所が、優秀な製品を多数製作したことを称える旨が書かれていた。実際、素人目ながら素晴らしい出来であるように見える。刑務所で作られた家具・製品は、メーカーから請け負ってつくっているものが多く、実際に市場に出ていると言う。何気なく購入した家具が、あるいは受刑者が制作したものかもしれないと思うと、説明しがたい複雑な心境になった。
次は皮革製品の作業場に入る。ここでは、靴や鞄を製作している。ここも木工製品作業場と同じくらいの規模のようである。靴・鞄は手作業で作られており、受刑者の机の上には木製の型が置かれていた。ここにもガラスケースの中に製品の展示がされており、値札までついていた。値段は失念したが、市価よりもかなり安い値であったと記憶している。受刑者の人達が忙しく針を持つ手を動かし、皮を縫い合わせていく。
最後に、部品製作(おそらく自動車)の作業場へ入る。先述したが、メーカーから請け負って製作している。ここは大きな機械が作動しており、非常にうるさい。何を作っているかも分からず、説明も聞こえない状態であった。時間がないのか、ここは足早に進んだ。
以上、作業場の一部を見たわけであるが、この作業について受刑者に一応、手当は出る。毎月作業成績などを考慮して平均で約3000円、高ければ 20000円支給される。支給されたお金については、出所前でもある程度は使うことはできるが、刑務所の方で使い過ぎないように指導しているという。というのも、刑務所ですべて使い切ってしまうと、出所時に無一文で外に出ることになるからである。大体、3年間の刑務所生活で約 50000円を貯めて出所する者が多いと言う。
なお、受刑者への手当以外の利益は国庫に帰属することになっている。この刑務作業による歳入額は平成7年度で 128億円に上る。刑務作業の材料を提供している財団法人矯正協会刑務作業協力事業部の製品は、CAPICというブランドで販売され、「毎年6月下旬に東京で開催される全国矯正展をはじめ、各地の矯正展等で展示・即売され、好評を博している」(法務省法務総合研究所編『犯罪白書・平成8年版』 p.150)。歳入額に比べ、受刑者への手当てが僅少である点が気になった。
さて、作業場を出た後、受刑者の食堂の前を通った。昼食のメニューがガラスケースの中に入っていた。大学の学生食堂よりもボリュームがあるように見えた。だが、それでも一人一食 150円程度であると言う。受刑者への給与熱量は、作業中の立位時間などに応じて3段階に量などが定められ、標準栄養量の確保が図られているという。150円でこれだけの栄養量を確保するのに頭が痛い、と説明する刑務官の方は苦笑していた。国民の税金から代金を捻出しているゆえ、これ以上のお金は使えないと言う。メニューについては、年に数回、受刑者にアンケートを行ない、その嗜好傾向を尊重して給食委員会で検討して決定するそうである。
食堂では数人の受刑者が配膳の準備をしていた。
その外では、トラックに製品を積み込む受刑者もいる。黙々と作業をする。
食堂を通り過ぎ、今度は受刑者用の風呂場である。共同浴場だが、結構狭い。脱衣所は人が3列に並べば一杯だろう。浴場は、真ん中に大きな湯船があり、外壁に沿ってシャワー・蛇口が付いている。刑務官の方によれば、風呂場は一番ケンカが起こりやすい場所で非常に気を使うと言う。実際、風呂場の入り口にある注意書きは20項目近くに及ぶ。そして、やはり20か国近くの言語で説明されていた。
入浴時間は15分であり、しゃべることは厳禁である。頭髪についても規定があり、揉み上げの長さの上限なども書かれている。シャワーは軽く体を流すため以外の使用は原則として禁じられていた。その他、ここでの規定は非常に細かい。
続いて、日本人受刑者の雑居房へ向かう。雑居房は文字通り数人の受刑者が同じ部屋で共同生活をする。4人が標準のようであった。日本の刑務所では、「社会生活に馴染ませる」との目的から原則は雑居房である。広さは8〜10畳くらいであろうか。畳敷で、ベッドではなく布団がある。私たちが見学したときは、たたまれて部屋の隅に置かれていた。部屋にはテレビ・便所・戸棚があり、いずれも共同しようである。ふと見ると、スポーツ新聞なども部屋の隅に置かれていて、生活の匂いを感じる。先に述べたように、府中刑務所では暴力団関係者の受刑者が多いため、この雑居房での部屋の割振りが非常に難しいと言う。抗争中の暴力団関係者を同室にしないよう、気を配っているそうである。
また、共同生活がうまくいっており生活態度のよい房のドアには「優秀シール」が貼られ、グループとして処遇が緩められる。例えば、テレビの視聴時間の延長などである。各房には放送回線が引かれ、受刑者による放送(主に受刑者のリクエストした音楽の紹介)がなされている。それにしても、畳敷のせいか、外国人房よりも暗くジメジメした印象を受けた。
続いて、日本人の独居房に入る。独居房に入る者は、どうしても共同生活に馴染めない者・資格などのために勉強する者・釈放が近い者(一般生活に近づけるため)である。外国人の独居房と広さは同じくらいで、違いとしては、畳敷であること・トイレの向きが横向きであること・ベッドではなく敷布団であることが挙げられる。外国人は独居房が原則で、日本人は雑居房が原則であるという違いがどうして生じてくるのか、疑問として残る。
最後に、刑務所内の講堂へ向かった。外観は「コンクリートのかたまり」にツル草がからまった感じである。しかし、内部は木造で椅子が並ぶ。入るとヒンヤリとした空気を感じる。ここでは、集会や歌手の慰問コンサート、宗教家の説教などが行われる。私たちが行ったときも、ある演歌歌手の慰問コンサートのための準備が行われていた。このような慰問コンサートは完全に第三者の善意によるもので、刑務所側から慰問を要請することはないとのこと。講堂は1000人しか収容能力がないため、コンサートや説教を行うときは2回に分けて行なうそうである。
この講堂も老朽化が激しく、近いうちに取り壊されると刑務官の方がおっしゃっていた。
以上で刑務所内の見学は終了し、再び庁舎へ向かう。刑務所に入るときに通った中門で、再度人数の確認を受け、庁舎に入ったのであった。



|