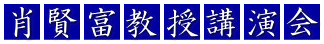
二、犯罪の被訴追者(被疑者・被告人)の権利について
五つ、重要な改正がある。先ず、被疑者・被告人の区別を明確にし、被疑者の権利を保護するようにしたことが挙げられる。現行法では、被訴追人は一律に「被告人」とされてきた。しかし、新法では、捜査段階と公訴提起段階までを「犯罪嫌疑者(被疑者)」、公判段階以降を「被告人」と定義し、それぞれの置かれた状況に応じた権利保障を計った。
次に、有罪無罪の判断は裁判所のみが下せるようにした。つまり、人民法院の裁判を経なければ、いかなる者も有罪とされないという原則、無罪推定の原則を採用した。
第三に、弁護制度の充実を計った。実際、新法は、現行法よりも、飛躍的に被訴追者の人権を保障しているのである。現行法では、公判の一週間前から弁護人を付けられることになっているが、高々一週間では充分な弁護も出来ず、刑事裁判の形骸化を招いていると指摘されていた。そのため、新法では、捜査が終わり次第、弁護人が訴訟当事者として参加しうることにした。つまり、警察が検察に起訴の手続きを請求してから三日以内に、検察は、被疑者に対して弁護人選任権を伝えなくてはならない。しかし、それだけではない。新法では、捜査段階でも、弁護士は、被疑者の代わりに不服申立、違法活動の告発が出来るし、捜査機関に対して聞き糾すことも、被疑者との接見を要求することもできるようになった。もっとも、捜査機関は、場合によ
り、接見の際に立会をつけることができるけれども。
そして新法では、被告人が経済的な理由から弁護人をつけていなくても、法律援助義務を負った弁護人がつけられることになった。さらにもし、被告人が、聾唖者や未成年、もしくは死刑に当たる罪を犯したとされている場合には、弁護人選任は裁判所の義務とされる。なお、法律援助義務は、全ての弁護士が負っている義務であり、指定された場合には拒否が許されない義務である。五月に採択された弁護士法にも法律援助義務の規定があり、弁護制
度の充実は大幅に進展したと言えよう。
改正の第四点としては、捜査過程における強制措置の整備が挙げられるであろう。もっとも、奇怪に思われる方もおられるかも知れない。収容審査制度を廃止し、逮捕条件、拘留条件を緩和したのである。ここで、「逮捕」とは、日本でいう勾留のことであり、「拘留」とは、日本でいう現行犯逮捕や緊急逮捕のことである。これは、現行法制度の下では、逮捕・拘留の要件が
厳しくてなかなか逮捕・拘留が実施されないために、警察慣行で収容が濫用されるようになったことに対応する改正である。収容審査制度とは、警察内部の慣行で法文規定はないが、容疑者と思えばいつでも誰でも収容するというものであり、かつ、大抵の場合この収容は長期に渡るものである。そのため、一見して人権侵害であるとされ、諸外国からの非難も「収容」に集中す
るようになっていて、早急な見直しを求められていた分野であった。
現行法の逮捕(日本でいう勾留)要件には、①重要な犯罪事実が既に明白であること、②それが懲役刑以上の犯罪に該当する犯罪事実であること、③逮捕以外の措置では、社会的危険性を防げないこと、という三要件が必要とされている。もっとも、そもそも取調をしていないから「重要な犯罪事実が既に明白であること」という①の要件を満たすことは事実上不可能であり、
無意味な要件とされてきた。そのため、「明白」を「証拠がある」に緩和した。
現行法の拘留(日本でいう現行犯逮捕や緊急逮捕)の要件も、三つある。
①現行犯か、重大な犯罪の容疑の存在すること、②逮捕、すなわち日本法にいう勾留が出来ること、③名前・住所・身分が不明であること、である。現在の実務では、①の「重大な」という点について揉め、とりあえず拘留されるという状況があるため、先ずは公益犯罪なら、連続重大事件に限らず拘留を認めることとした。②は廃止して、現行犯なら何でも拘留できるようにして、収容の代替とした。③については、氏名・住所・身分を黙秘していても拘留することを認めた。
最後に、刑事手続過程における被訴追者の権利の保護拡充を挙げておきたい。これは二つの点から成り立っている。先ず、起訴免除処分の廃止と不起訴処分の拡大がある。この起訴免除処分というのは中国独自の制度である。有罪であるが、以後二度と刑を科さないことを保障するという制度である。
実務において、有罪か無罪かは裁判官が決すべきであるにも係わらず、実質的に検察官が決めてしまっているという批判がかねてからあり、その批判に応えたものである。次に、第二点として、公判段階における職権主義の緩和を挙げる。つまり、検察官と弁護人との権限を拡大して、訴訟を当事者主義的にしたのである。このことに伴い、「廷前審理(予審)」が廃止され、証
拠提出の負担が弁護人・検察官に移り、判決を出すのは事件を審理した合議廷のみとなったという点で合議廷の役割が増大した。つまり、法廷を開く前に法廷の外で有罪無罪を決定してしまっている諸要因を排除したのである。
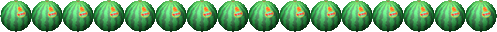



|