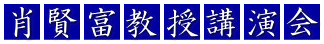
 三、犯罪の被害者について
三、犯罪の被害者について
こちらも五つ、重要な改正がある。先ず、被害者も訴訟当事者になることとなった。現行法では、訴訟参加者に過ぎないために、当事者としての権利が保障されていなかった。しかし、改正によって、公判期日に被告人の有罪を追求するために出席することが出来るようになった。被告人の有罪追求とは、起訴状記載事実を陳述すること、および被告人への質問のことである。
次に、被害者は、代理人に依託しても訴訟参加出来ることとなった。現行法では、「弁護」と名の付いた章以外に規定はなかった。が、新法は、「弁護」の他に「代理」の章を設けた。特に、新法四三条では、被害者か、その法定代理人、近親者が、捜査が終わり次第、訴訟代理人の選定が出来る旨を定めている。つまり、検察は、起訴をしたら、三日以内に、被害者、その法定代理人、被害者の近親者に対し、訴訟代理人選任権の」あることを伝えなくてはならなくなったのである。
第三に、被害者に、事件の捜査の開始を求める権利を認めた。現行法では「立案(立件)」という手続があり、警察が立案することしか認めない。新法では、警察が立案しない場合に、被害者が警察に対し、立案するように主張できることとなった。
第四に、被害者に、不服申立権と直接起訴権とを認めた。ともに、現行法には規定すら無いものである。しかし、新法では、警察が起訴しない場合に不起訴の決定を被害者に届けなければならないとし、被害者側が、上級の検察機関に、一週間以内に訴えでることを認めた。しかも、それでも起訴されない場合には、直接に人民法院に起訴できることを認め、その際、検察に、証拠を速やかに裁判所に移さねばならない旨の義務を課した。この結果、どのような事件であっても、被害者は訴えでられることになった。
最後に、被害者に、判決に対する控訴の権利を認めた。現行法では、検察に控訴をするように求めることしか許されていない。しかし、新法では、第一審の判決に不服のある場合に、被害者側に控訴の権利を認めた。
以上の改正を通じ、被害者の人権保障が進展するであろう。
|
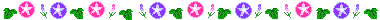



|