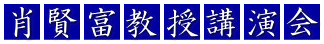
四、まとめ
今回の改正は、犯罪の被疑者、被告人の権利の伸張、犯罪の被害者の保護の徹底を二本の柱とするが、いづれも人権保障を狙いとした改革である。ただし、施行の方法については問題が残っている。こればかりは、施行してみなければなんとも判断し難い。そのため、中国の経験だけでなく、日本など諸外国の動向も参考にしていく。
五、質疑応答
質問
「そもそも中国に令状主義はあるのか。」
回答
「中国において、令状主義とは、強制処分には書面が必要であるということの意味しかもっていない。日本の逮捕に相当する「拘留」は、警察の判断だけで出来る。しかし、日本の勾留に相当する「逮捕」は、検察院または裁判所の出した許可状が事前に必要となる。もっとも、緊急性のある場合には、とりあえず逮捕した上で、追認の形で令状が出されることも許されてい
る。」
質問
「検察は起訴後も補充捜査をするのか。」
回答
「補充捜査という言葉の意味を、質問者がどの様に捉えておられるのかが分からないが、先ず、検察と警察との関係において、警察が検察に事件を送致した後に補充捜査をするかといえば、する。検察が警察に命じて行わせることもある。次に、裁判所と検察との関係において、検察が裁判所に事件を送致した後に補充捜査をするかについても、実際に行われる。
なお、捜査終了意見書は、無罪の場合でも出される。」
質問
「捜査段階における弁護人の地位について、教えて戴きたい。単なるボランティアの様なものと考えても良いのだろうか。」
回答
「微妙な問題である。捜査段階では、弁護人は、法律家として捜査手続に関与する。このことは、被告人のために弁護人が活動することを意味するが、弁護人が代理人の立場にたつことを意味するものではない。
なお、弁護人は、公判段階では訴訟参加者として参加する。どちらかといえば被告人に権利を与えているのであって、その条件として弁護人に活動を認めるという構造になっている。それ故、起訴時から弁護人を依頼ができるということの意味は、被疑者・被告人の依託により権利として参加できるようになるということであって、被訴追者にとってみれば、起訴の前後で、大して変わらない保護を受けていると言えよう。」
質問
「では、逮捕に対して、弁護人は不服申立ができるか。」
回答
「勿論できる。ただし、被疑者のためになされる、弁護人の代理行為としてではあるが。弁護人には、固有権はなく、代理権のみが認められる。そのため、弁護人独自の権限は、捜査段階では無いのである。もっとも、用
語としては弁護士の独立した主体性を認めていても、個々の規定を見る限り、弁護人には独自な活動は許されていない。この点で、あくまで被告人に由来する弁護権であることが確認される。」
質問
「弁護人が証拠開示を請求できるのは何時からか。」
回答
「証拠開示は、公判段階でなされる。つまり、起訴後である。それまでは被告人にも証拠開示請求は認められない。しかし、被訴追者側といえども検察と同様に証拠を見ることができる。国家機密についてはどうだか分からないが、思想犯であっても裁判所は全ての証拠を見ている。
なお、新法においても、起訴状一本主義は採用されなかった。そのため検察は起訴時に、証拠も全て一緒に出すのである。後藤先生が参加した一九九四年の会議のレポートにも起訴状一本主義の採用への勧告があった。
だが、大議論の末、慣行と裁判官の素質とを理由に、採用は見送られた。
起訴状一本主義は裁判官をバカにしているという評判があった。つまり、「証拠」らしいものがあるからといって、裁判官がそれだけで偏見を抱く訳では無いというのである。これは、裁判官の側から寄せられた意見である。
質問
「起訴状一本主義を採用しなかったことは、当事者が挙証責任を負うこととどう関係するのか。実際、中国で見た裁判では、裁判官が机の下からナイフを取り出し、証拠として被告人に示していたが、このようなことは、新法の下で許されるか。」
回答
「新法では、書面は送って、物証は法廷で呈示させることになっている。そして、裁判所は公判前に証拠を確かめなければならないという条文があるが、検察側・弁護側がどの様に証拠を区別するかは、条文からは何ともいえない。今後検討する。」
*質疑応答は次ページに続く




|